2011年08月07日
小説 桂女恋花 第二章
第二章 桂の里と西岡の土豪たち
一
九十九は、雨の中を、葛野大堰に沿って、ひたすら駆けた。今頃、桂の里は「騒然となっているに違いない」と気が急くばかりだった。
桂川は、丹波山地の大悲山付近に源を発する河川である。その右岸、現在の上桂から下桂にかけて、九十九たち、桂女の産する桂の里が広がっていた。当時は、この里を含む、上六ヶ郷付近一帯の惣領となっていた革嶋家の支配下にあった。
九十九が、久我畷から、北へ、桂の渡しまで帰ってきた頃には、少し日が翳り、辺りは薄暗くなり始めていた。幾千の日々を、川を行き来する船の安全を見守ってきた、土手沿いの愛宕常夜灯が、川面に映し出される。
「急ぎやあ~、早うせんと日が暮れきってしまうよってな」
小雨の中で、沈み行く夕日が創り出す、双子の虹を背景に、渡り舟の船頭や、褌姿の人足たちが、ゆったり、何とも優雅に荷駄の積み下ろしをしていた。
丹波や摂津からの木材の陸揚げ地であり、野菜や穀物、諸年貢、肥料糞尿の運搬にもこの渡り舟が使われた。
傍らに、嵐山付近で桂川を堰き止め、物集女・寺戸を経て、羽束師で再び桂川に注ぎ込む今井用水。かつて渡来氏族の秦一族が造った潅漑用水路があった。
西岡十一ヵ郷(上六郷・上桂、徳大寺、下桂、革嶋、下津林、寺戸、下五ヵ郷・牛が瀬、上久世、下久世、大藪、築山)が契約を結び、用水の掟の順守を誓い合い、維持・管理しており、おかげで、当時、この地域は、随分と活気を帯びていたのである。
湿った雑草の堤を、そろりと川岸に降りたった九十九は、あまりにも長閑な様子に驚かされた。
ちょうどそこに、里の配下の問丸の主人、痩せこけた小男の清兵衛が、船頭や人足を指示していたので、捕まえて問うた。
「都の公方様が、殺された。伝令は伝わっとうわなあ」
清兵衛は、地味な着流しの小袖の上から肩を掴まれ、驚いた様子をしている。
「あっ、これは九十九様、お帰りになられましたのやなあ。確かに聞いとります」
「確かにやない。いったい、この長閑さは、なんね?」
不可思議に思った九十九が捲し立てる。清兵衛が圧倒されている。
「確かに、小七郎様らが、お戻りになって、公方様のこと、お聞き申しました。皆も一時は、不安を隠せぬ様子やった。されど伊波多の婆さまが、案ずるなとおおせに。我ら太古より、神聖なる巫女の一族、禁裏様の御厨子所にお仕えし、天子様の膳に鮎を供する供御人の一族ぞ。禁裏様のお出入りお構いなし。川魚の扱いも、川上も通行勝手、と桂川のことでは、諸役免許を賜っておる。何も変わらぬ。と皆をお静めなさったのや」
九十九は「さすがに、婆や、動じとらへんな。婆の威厳は、凄まじく大きい。うちも里のこと、もっと誇りを持って、語れんとあかんわ」と改めて思う。
「それよりも、もっと大変なことに、なっとうし、館に行ってみなされ」
「もっと大変なこと? なんね」
「いったい、公方様殺害の急報より大変なことがあるのやろか」と不思議に思う九十九に、清兵衛が少し笑みを浮かべた。
「まあ、行けば分かりますよって……」
二
松尾社より罧原堤を横目に下り、今井用水の傍ら、松室の地から、上桂にかけて、月読命を祀る里の鎮守、月読神社があった。当時は、広大な敷地を有し、朝廷より最重視された延喜式内社である。
九十九は、上桂郷を囲う、堀と土塁の惣構を抜けた。郷の北門付近から繋がる、大きな石造りの鳥居をくぐる。眼前に迫る松尾山麓が、鮮やかな新緑に蔽われていた。
「月影、お前は、ここまでや。はい、ご褒美や」
と飼い葉桶にある干した萓や小笹を与え、、月影を、馬舎の敷き藁の上に入れた。
石段を百段ほども上がっていくと、傍らには、藁葺きの客殿があり、奥の庭園より流れ出ずる小川に、木橋が架けられている。橋を渡ると、朱、藍、橙の色彩鮮やかな、二階建て楼門に至る。
「いつもながらに、疲れるこっちゃ」
と思いつつ、もう一踏ん張り、さらに急な石段が続く。
周りを竹林に囲まれた参道は、鬱蒼として昼なお暗く神秘的な佇まいだ。途中、入母屋造りの石祠二体が祀られ「月読神社」の文字が刻まれている。聖徳太子社もあった。
解穢(かいわい)の水が沸き出る石造りの井戸、紙垂の巻かれた縁結びの木を横目に進むと、鮮やかな朱塗りの鳥居が現れた。鳥居をくぐると、松尾造りの祈祷殿と御本殿が、悠然と並んで鎮座し、手前には、木目調の欄干が設けられた舞殿をも併せ持つ。
祈祷殿の傍らには、大太鼓と大幣が飾られていた。桂の里は「月の影は桂の巨樹」と、その名を中国の故事に由来し、月の桂と愛される土地柄だ。象徴するかのように、沈丁花の花が咲き誇っていた。
何やら奥が騒がしいな、と思いながら、九十九は崖沿いに、へばりつくように生える桂の木の袂を抜けて、境内を進む。紙垂の巻かれた月延石の前に篝火が焚かれ、十数人の里の巫女たちが、一心に祈祷をしている。
「月読命某神社乃恐美恐美母 親王妃宮今年乃春乃頃与里御身体芽出度伎御吉兆……市杵島姫神介給布御儀式……御食御酒種種乃味物乎献奉里 ……恐美恐美母白須……」
と前列の二人が祝詞を捧げる。
「悪霊退散、悪霊退散……」
後ろの者どもが、白木の棒の先に、金箔、銀箔、五色の紙垂をつけた大麻(おおぬさ)を、左右に振り回し、その幣に穢れを吸いこもうと必死になっている。
「安産の祈祷や。誰か、産気づいたな、これだけの人数、相当、気合が入っとうなあ」
と思っていると、後列にいた巫女の一人、まだ齢若い下弦が、九十九に気がついた。
萱草色の緋袴の裾から、細くしなやかな足元を覗かせ、そっと近づき、耳元で囁く。
「九十九様、お帰りなさいませ」
「何があったんや?」
「ええ。かつて市杵島姫神様が、月読尊とともにこの地に降りたちし時、撫でて心身の安泰を祈願したと云われる月延石。この安産の石に、祈願しておりますのや」
「分かっとうし。月から延びてきた神石なんやな。何でそうしとんや、と聞いとうや」
九十九は、のんびりゆっくりと話す下弦に、少しいらついて問うた。「何でこの子は、いつもこんなに、のほほんとしとるんやろ。ほんま調子狂うわ」と思う。
あまり気にせぬ様子で、下弦が更にゆっくりと話す。
「かの、やんごとなきお方のためどす」
「何やて? かの姫様……、一つ月が早いんやないん」
「そやし、みんな大慌てどす。石清水八幡はんでも、祈祷が始まったそうどす」
「ほうかあ」
下弦は、不思議そうな表情をしている。
「それにしても、最近は、お公家様方の御内室のお産が、多おすなあ。何でですのん?」
伊波多は「そんなこと、うちに聞かれても、知らんわな」と思う。それでも、大真面目で問う、若い下弦に、何らかの返答を、してやらねばと思った。
「さあ、まあ、摂関家や青華家のやんごとなきお方たち、長らく政から遠のき、和歌や連歌に打ち興じておるわ。他にすることが全然ないんや、きっと。ふふっ」
九十九は男女の交わりを想像して「変なことを言ったかな」と少し気恥ずかしくなってしまった。
三
崖沿いに神社と併設して、桂の里の棟梁、伊波多の婆の住まう館がある。
竹林に包まれた正面には、防御機能を備えた木戸が設けられ、だだっ広い敷地の中、建物は、九間ほどの藁葺き、掘立式の木造造り。渡り廊下が繋ぐ離れには、欄干も設けられ、広い御産所があった。檜の板張りで、田舎には似つかわしくない、豪華な施設である。
庫裏の前では、大きな釜に湯が沸かされ、小袖の裾をたくし上げ、やはり頭は桂包み、白襷掛けの女たちが、右往左往している。
「もっとようけ要るし、急いで沸かすんや」
「気をつけや、ほんに熱いし、慌てず、ゆっくり運んだら、ええさかいなあ」
湯を運ぶ女たちの桶から、熱湯がこぼれ落ちる。皆顔を歪め、必死の形相だ。
九十九は「確かに、こりゃ、えらいこっちゃ」と思う。庫裏横の玄関から、急いで奥座敷に向かった。
周囲に畳を追回しに敷き、中央は板敷を残す、すべての灯が消されている。月明かりで、僅かに姿が認められる婆がいた。月読尊を祀る神棚の下で、大きな掛軸の前の褥に座す。
六十過ぎかと、思っているのだが「齢など数えたことがないわ」という婆のこと。孫娘の九十九さえ、本当の年齢を知らない。
久しぶりの面会だったが、紅の緋袴の巫女装束で座る婆を見て、一段と老けたように感じた。霊力の使いすぎではないかと、心配にさえなる。
「クキリクア クウンバン ウンタラカンマン ボロン ソワカ……、市杵島姫神よ、出でて神託を授け給え……ウンタラカンマン オ~ウォ~」
五芒星の真ん中に座し「天、地、玄、妙、行、神、変、通、力、勝」の十字を唱えては「エイ、ヤア」と刀印を打ち下ろす。
真っ白な長い髪の婆は、力強い重音を発し、囲炉裏の炭で、亀の甲羅を焼き、ひび割れの様子から、卜占を行なっている。亀の甲羅を床に叩きつけ叫んだ。
「うん、厳しいなあ、小凶と出ておる。助かれば良いが」
「婆様、なんで、灯り全部、落としてるん?」
不可思議に思った九十九は、婆に問う。「里帰りの挨拶もせなんだわ」と思った。
婆は木炭の残り火をも消し去る。九十九の顔を、下からじっと覗き込む。皺を寄せたが、少し笑みを浮かべた優しい顔で、まるで何かを伝授するかのように語りだした。
「ええか、火もまた、お産の穢れを受けるよってや。お産は穢れの一つやでなあ。そやから、都の高貴なお人たちは、洛中でお産はなされぬのや。九十九、座して聞かぬか」
九十九は「しまった、わざわざ婆の長い話を、焚き付けてしもうたわ」と思う。
何度となく聞かされたいつもの話を、婆がまた話し始めた。
「かつて、我らが始祖、月読尊が、比売大神様と市杵島姫神様と申す、それは美しき姉妹とともに、日ノ本に降り立った。やがて、豊葦原の中つ国に築かれた王国で、妹御であらせられる姫神様は、月よりの神石(隕石)を崇敬し、御心を静められ、大神様をご出産なされたのじゃ」
「うん、そやったな。ああ」
九十九は「しゃあない、最後まで付き合うわあ」と覚悟を決めた。
「え~こほん、語りを続けるぞ。ところがなあ、安らかな日々は続かなんだ。時を経ること十数年、発展する王国を恐れ、再三に亘って侵略が繰り返された。姫神様と大神様は、一族を守るため、ついに東遷し、王朝の歴史が始まったのじゃ。一方、年老いた月読尊は、安穏の地を求めて、湯津桂に寄って立った。これが、桂の里の起こりや。この神石は、月延石(月より来た石)と呼ばれておる。三つに割られた神石は、この月読の祠、糸島の鎮懐石八幡の社、あと一つが、壱岐の月読の社に祀られたのじゃ」
「うん、うん、その通り」
九十九に構わず、婆がさらに続けた。
「え~、こほん。それでじゃ。その後、帝や、今は五摂家に分かれておるがの、藤原の一族とともに、この京の地に、陰陽に基づき、理想郷ともいうべき、平安京を築きあげた。しかしじゃ、以後、我らが表に出ることは、もはやない。我らは陰に徹して、この平安の都の安泰に暗躍することを決意したのや。我が一族の宿命を背負って生まれた者、それが九十九、お前なのじゃ。良いか」
延々と続く長い話が、四半時も続いた。
「あ~、あっ」
九十九は「そろそろ終わりやなあ」と思いながら、思わずあくびをしてしまった。
気にもせぬ様子で、婆がようやっと最後のくだりを語る。
「よいか、人の一生の運は、臍の緒を切る産婆によって、与えられるのや。赤子を奪い去ろうとする物の怪より守り、命を吹き込む大切な役目、しかと引き継がねばならぬ」
九十九は「ようやっと本題に入れるわ」と思った。
「よう分かったし。時に婆様、公方様が殺され、この西岡あたりを三好党が放っては置かぬのやないか。我が里は、どうなるんや?」
婆は、しわくちゃの顔を、さらに寄せて、薄ら笑いを浮かべる。
「焦らずとも良い。この神聖なる桂の里に、天子様の臣下の臣下など、手出しできぬわ」
「革嶋の館は、どうなるん?」
「我ら革嶋と日常を一にしておるのも、川上の利が一致しておるからに過ぎぬ。良いか、九十九。我が後継として、どのようになっても、里の誇り貫き通すこと、忘れるでない」
「また、言うし。石清水八幡はんと御幸宮に、神官として姉様方がおられるやない。なんで、うちやのん」
九十九は、一番下の自分が、後継と言われることが、どうしても腑に落ちなかった。
「伊波多の後継は、選ばれし者……、まあ、ええわ。いずれ分かる。時に、明日の夕刻、向日神社にて、西岡被官衆の合議じゃ。あての名代として、おまはんが出るのや。ええか」
「へっ、分かったし」
九十九は「そんな大役を」と思いながらも、しぶしぶ了承した。するとそこへ、御産所よりの使いの者が催促に来た。
「婆さま、そろそろ、出るようや。よろしゅうに」
「九十九、おまはんも来るんや」「へっ」
九十九は、お産の立会いは初めてだったから、興味津々で、婆の後に続いた。

月読神社
四
静かな奥座敷から一転して、離れの御産所では、壮絶な闘いが繰り広げられている。
「う~う~、ふっふっふっ、う~うお~」
まるで龍神の声かとも、思われるような雄叫び。
妊婦の額から、肌蹴た白襦袢の首筋から、肩からすさまじい勢いで汗が流れ出る。
隣室の床板を外して盾とし、米俵を体の両側において、その間で、口に白布を噛みこみ、断末魔を思わせる凄まじい形相で踏ん張っている。
「う~、うお~、うお~」
苦しさで暴れる妊婦を、女たちが数人掛かりで押さえつける。
「いかん、体が冷えてきとる。足と腰をさすって、気を入れるんや」
産婆の叫び声とともに、女たちが両足と腰を、摩擦するかのごとくさすり始めた。
「ええか、もう少しや。気張りや」
「う~ふっふっう~ん」
「気張るんやあ」
と励まされれば、妊婦がぐっと踏ん張る。
「力抜けえ」
で一旦、力を抜く。
「ひーひーふぅ」
「ひーひーふぅ」
と産婆が耳元で復唱する。産婆の額からも汗が止め処ない。
「良し、体も温こうなってきた」
「さぁ、来るんや。ひーひーふぅ、ひーひーふぅ」
傍らで見ていた九十九は、お産というものは、こんなにも凄いのかと感嘆した。
どないしょう、されど手伝おうにも、圧倒されて、身動きが取れない。
「よっし、ええよ、ええよ、見えてきたし」
「う~、うお~」
産婆たちの声に励まされ、妊婦がさらに踏ん張る。
しかし、妊婦の顔色は真っ青だった。紫色の唇を震わせながら、産婆の衣装を揉みくちゃに掴み、息も絶え絶えに声を振絞った。
「ふう~ん、ふう、ふう」
「あかん、逆子や、みなで引っ張り出すえ」
「せえのお、よいしょ」
「うお~」
松尾山麓をも揺るがすほどの、妊婦の悲鳴が響き渡る。
ようやっと、引っ張り出すものの、赤子は泣きもせず、身動きもしない。急な破水で、臍の緒が首に絡みつき仮死状態だったのだ。その場に言いようもない緊張が、駆け巡る。九十九も焦った。顔から血の気が引くのを感じた。
「あかん」
産婆は赤ん坊の足首を掴み、逆さまにすると赤ん坊の背中を叩いた。
「ええか、泣け! 泣け! 泣かぬか!」
八半刻に足らぬほどの静寂。
「うわんぎゃあ~、あぎゃあ~」
と赤子が、大きな大きな声で産声を上げた。
「やったあ~」
「ほんに」
その場が歓喜に満ちた。
「良かったし、良かったし、うん」
女たちは、涙ぐんだ目で、互いの肩を叩き、縦に飛び跳ね、頬を摺り寄せる。
早産のために体は小さいが、元気な男子であった。在所の使者より届けられた守刀と掻巻(綿入れの夜着)を袂に置き、臍帯を切って縛り、傷跡を焼く儀式が行われた。
「よし、付いとるもんも付いとる」
と頷きながら、臍切り婆役の伊波多の婆が、すばやく臍の緒を切りとり、さっと鮮やかな手並みで結んだ。
生まれたばかりの赤子は胞衣(胎盤)と一緒に請衣という白羽二重に包まれ、産湯に浸かる。この時、古例に従い、桂川の水と月読神社の解穢れの井戸の水を合わせたものを使う。洗浄された胞衣が白木の胞衣桶に納められ、隣室の西北隅に置かれる。
産湯から上がった赤子は、襦袢と袖なし、御巻で巻かれた。
赤子が、元に返されると、妊婦は、力を使い切った弱弱しい手で、慈しむように顔を撫で始めた。その姿は、ふくよかな幸せに満ちているようだった。
九十九は、眼と鼻筋の間を流れ落ちる、止め処ない涙の温もりを感じた。「かつて、こんなに感動したことが、あったろうか」と思う。
「良かった、ほんに良かった……」
九十九が、境内に出たときには、もう夜が明けかけていた。
透き通った桂川に早朝の日が射して、照り返しがまぶしい。川面には、燕や東風鳥が落ちては上がり、落ちては上がりを繰り返す。鴨の親子が、とっとこととっとこと、と何とも危なげに、罧原の堤を斜めに横切っていく。
九十九は微笑ましい姿に「おまはんらも、頑張って生きるんや」と、励ましていた。
「お疲れさんどした」
と、下弦が愛らしい笑窪を浮かべ、会釈した。本人も疲れきった様子だ。
「この子も、よう頑張った。さっきはいらついて、すまんやったなあ」と、つくづく思う。
陽射しを避けて、額を腕で覆う。いつになく優しい口調の物言いが、自然に流れ出た。
「そっちこそ。今日は、ゆっくり休みや」
九十九は、公家衆に「することがないのやろ」と言った自分を恥ずかしく思っていた。
「命の誕生とは、こんなにも凄いのか」と感動に打ち震え「この命、決して粗末にはでけん」と心の中で、しみじみと思った。
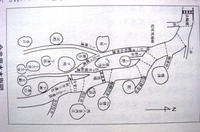
五
次の日の夕刻、九十九は、またも駆けていた。
九十九は、今井溝に沿って、一路ひたすら南西に駆けた。
田圃の畦や緑が濃さを増し、野原の所々に、ひときわ目立つ藪甘草の橙色の花に、心を奪われそうにもなる。
二里と少し、四半刻ほど駆けると、十一ヵ郷を抜けて、向日野から乙訓地域(現在の向日市や長岡京)に入った。この乙訓地域と、十一ヵ郷を合わせた地域が、西岡(にしのおか)と呼ばれている。
松尾社、天竜寺、東寺、石清水八幡といった寺社、近衛、鷹司など摂関家などの所領が入り乱れる土地であったが、今井溝を始めとする農業用水や、交通・交易など広域に係わることを、合同で対処する中、独立した惣国として発展してきた。
幕府の被官でもある国人衆が集まり合議がなされるのが、向日神社であった。地域の要所に城館を構える土豪たちである。
新緑薫る向日山の麓、元稲荷山古墳を始めとする古墳群を見ながら、鬱蒼とした鎮守の森を登る。大きな常夜灯と朱色の鳥居の間をくぐって、流造桧皮葺様式の境内に入る。
駆けつけた参集殿には、三つ巴の紋の描かれた向大明神の掛軸があり、大広間では、すでに三十人余の国衆たちが集まっていた。
男たちが喧々諤々迫力の論争を繰り広げている。
九十九は「かつてない事態に、皆、真剣なんや」と、つくづく思う。「まあ、ほんまの熊みたいや」と思う男が、一番最初に目に付いた。
「おのれ、三好党のものども、増長するのもええ加減にしや。国主を殺害するなど、言語道断や。奴らのような雑兵にや、決して屈せぬは」
小塩荘をはじめ高畠・大岡荘、勝龍寺領、西岡新馬場跡などに支配を及ぼす神足村の国衆・神足掃部が、舶来品の白熊の腰蓑をつけ、それこそ、まるで大熊のような、大きな体を揺らし、息巻いていた。
「そうや、我が神聖なる領土とて、三好一派の軍勢など一歩も入れへんわ。西岡土豪衆の力見せなあかん」
開田城主・中小路宗俊は、盤領の一つ身、白水干姿。元は菅原道真の一族という中小路家は、代々開田天満宮(現在の長岡天満宮)の神官でもあった。

かつての開田城
秦氏の末裔と称する物集女城主・忠重が、小袴の上に羽織った生絹の狩衣を整えながら、冷静な口調でさらに続いた。
「かの応仁の大乱、また続く細川家の抗争で、一度は分裂した我ら被官衆であった。しかし、その後は、向大明神のご加護の下、衆議一決、この西岡の地を守り抜いてきたやないか。西岡一揆の再来や」
今里の能勢頼広は、すでに赤胴の甲冑を着込み、戦闘態勢だ。
「そうや、奴らは必ず、桂川からの取水による水利灌漑、川上の渡の特需を欲するやろ。我らの生命線、決して渡すんやない。一揆も辞さず」
九十九は「みんな、それぞれ好き勝手な恰好してはるわ、あの熊の毛皮、もう暑うないんやろか」などと暢気に聞いていた。
乙訓地域とは、かつて、たった十年の幻の都・長岡京が営まれた地域である。
西岡の土豪たちは、幕府の御被官となっているものの、かつての山城の国一揆と並ぶ西岡一揆を起こし、百姓が国、惣国を創り上げてきた土地柄だ。それだけに独立心も強い。
年老衆の意見に、他の国衆も一斉に叫んだ。
「一揆」「そうや、惣国一揆や」
雰囲気に圧倒され、中々、口を挿めないでいた九十九だが、意を決して叫んだ。
「そうや、一揆や!」
女特有の甲高い声に皆が驚いた。
一瞬、場が静まり返り、一宣の傍らにいた秀存が、慌てて叱責した。
「九十九、そなた何故、ここにおるのや? 控えぬか」
「桂の里、伊波多の婆が名代にて、九十九でおます。皆の衆、以後お見知りおきを」
九十九は、力強く挨拶した。
秀存が「まさか」といった表情をしている。
「も、もしや、そなたは、婆の後継やったんか?」
「そうでおます、忍びの任ゆえ、隠しておりましたのや。かんにんや」
藍染羽織の上から腕を組み、静かに聞いていた革嶋一宣が、口を挿んだ。
「して、九十九、いや、九十九殿」
一宣らの礼を尽くす物言いに、九十九は「まあ、急に態度が変わったわあ」と、里の棟梁の威厳を垣間見たように思った。
「里の具申も、皆と同意と申されるのやな」
「へっ、うちら三好長慶殿に従うてきたは、公方様、ひいては禁裏様の意があってのもんや。長慶殿亡き後、国主を討った三好党や、まして松永弾正などに従う道理は、おまへん」
この時、月行事を務める一宣が、衆議をまとめた。
「皆の具申は、よう分かったし、おのおの方は、三好党を敵として、共に立ち向かうということで、ええんやな。皆、郷で軍勢を整え、我が惣国の拠点、青龍寺城に結集や」
「よっしゃ」「お~」
皆が異口同音に気勢を上げる。
しかし、九十九だけは、この時、年老衆の一人、鶏冠井(かいで)村を領する鶏冠井城主の光則が、静かに腕を組み、おざなりの同意を示しているのが、少し気になった。
鶏冠井村は、かつて長岡京の大内裏のあった地域(現在の西向日駅周辺)でもある。
年老衆、国衆らが次々に退座し、秀存も、退座の構えをしながら、九十九に要請する。
「九十九殿、里のお力をお貸し願えるか?」
「もちろんでおます。これより立ち戻り、至急、革嶋城へ駆けつけますよって」
「うん、しかと頼んます」
九十九は、無機質な口調は変わらぬものの、いつもとは違って、礼を尽くす秀存の言い様は、何となく心地よいものだと思った。
しかし、一方で難しい局面に来ていることを、感じ取っていた。

向日神社
六
九十九は、大急ぎで桂の里に戻った。
館の庭の竹灯篭に灯が燈され、広がる幽玄の世界。京唐紙の襖障子には、花鳥風月や跳ね馬が描かれ、灯籠の明かりに照らされた雲母が、炎の揺らめきとともに上品に光る。
襖をすべて開け切り、涼をとりながら、婆は、やはり卜占に取り組んでいた。
「婆様」
九十九は、逸る気持ちを抑えきれない。部屋に駆け込む九十九を、婆が左手で制する。
「待て、あっ!」
囲炉裏の上で、焼かれた亀の甲が、パカ~ン、と真っ二つに割れ、周囲に飛び散った。
九十九は「えっそんな! 最悪の占いが出た」と心中、穏やかでない。
「う~ん、大凶じゃな。九十九、この合戦、行くんやない」
「すでに知らせが入ってたんやな」
婆が静かにうなずく。
「西岡は、必ずしも強固な一枚岩やない。それぞれの惣中の集まりや。三好党もまた、最も取水豊かなこの地を欲するに、あらゆる手立てを尽くすはずや。何倍もの軍勢に攻められては、土豪衆に勝ち目はない。里を動くでない」
「婆様」
九十九は、今度ばかりは、占いに逆らう気になる。いかにも不服といった顔を造った。
婆の目をじっと見つめる。ふうっ、と溜息をつきながら、婆が優しい表情になった。
「おまはん、若もの(秀存)に惚れてとうなあ」
「何もかもお見通しなんやな」
「ええか、九十九。我が里の女子は、他から夫を迎え、女系相続が習い。里の家を継げるものでなければならん。おまはんの婿も、いずれ神託が下るやろ。諦めるんや」
九十九は、涙目になっていくのを感じた。
「うちかて分かってるし。そうやない。うちは、これまで受けた恩義を返さず、裏切って、ほんで、この桂の里が、幸せになれるとは思わへんのや。うちは一人になっても行くし」
「待ちや、九十九」
部屋から飛び出そうとした九十九は、一瞬、足を止めた。
後ろから、婆の声を聞く。
「市杵島姫神様のご加護のもと授かりし命、決して粗末にするんやない。肝に銘じるんや」
九十九は「婆様、ごめん、うちは、この感情を抑えることができひん」と詫びていた。
七
外に出ると、月読神社の境内には、上弦、下弦、地蔵、千百を始とする、くノ一衆、小七郎、与一を始とする男の乱波衆が結集していた。
「九十九様」
と総勢百人近くが一斉に合唱する。
「なんね、これは?」
驚く九十九に、小七郎が、片手を地面につけて、礼をとった。
「若の救援、婆様より、ご下命が下った。今日より、乱波衆の指揮は、おまはんが執りや」
「うちが?」
「婆様は、おまはんが、止めても聞かんことなど、はなからお見通しや。すでに手筈を、指示なされておったわ」
九十九は、「婆にやられたわ。何でもお見通しか」と思う。首を斜めに振り、上唇を舌で舐める。涙は止まらぬが、戻った笑みで、自分の顔が緩むのを感じた。
「九十九様、よろしゅうお願い申します」
と下弦が、愛らしい笑窪を見せながら、いつものようにおっとりとした調子で、九十九に近づき、采配を手渡した。「可愛い奴やなあ」と思う。
パン、パンパーン……。
九十九は、采配を手に取ると、涙をさっと拭き取り、神殿に二礼二拍一礼をした。
それからおもむろに皆に向き直り、采配を大きく振りながら、命を下した。
「みんな、行くよ」
「やあ~、出会え、出会え、そや出会え」と松尾山麓に、皆の合唱が木霊する。
九十九は、駆けた。日の本一と言われる、鬱蒼とした大竹林を抜け、今度は、九十九軍団となって、南へ一路、革嶋城へ駆け抜けた。
一
九十九は、雨の中を、葛野大堰に沿って、ひたすら駆けた。今頃、桂の里は「騒然となっているに違いない」と気が急くばかりだった。
桂川は、丹波山地の大悲山付近に源を発する河川である。その右岸、現在の上桂から下桂にかけて、九十九たち、桂女の産する桂の里が広がっていた。当時は、この里を含む、上六ヶ郷付近一帯の惣領となっていた革嶋家の支配下にあった。
九十九が、久我畷から、北へ、桂の渡しまで帰ってきた頃には、少し日が翳り、辺りは薄暗くなり始めていた。幾千の日々を、川を行き来する船の安全を見守ってきた、土手沿いの愛宕常夜灯が、川面に映し出される。
「急ぎやあ~、早うせんと日が暮れきってしまうよってな」
小雨の中で、沈み行く夕日が創り出す、双子の虹を背景に、渡り舟の船頭や、褌姿の人足たちが、ゆったり、何とも優雅に荷駄の積み下ろしをしていた。
丹波や摂津からの木材の陸揚げ地であり、野菜や穀物、諸年貢、肥料糞尿の運搬にもこの渡り舟が使われた。
傍らに、嵐山付近で桂川を堰き止め、物集女・寺戸を経て、羽束師で再び桂川に注ぎ込む今井用水。かつて渡来氏族の秦一族が造った潅漑用水路があった。
西岡十一ヵ郷(上六郷・上桂、徳大寺、下桂、革嶋、下津林、寺戸、下五ヵ郷・牛が瀬、上久世、下久世、大藪、築山)が契約を結び、用水の掟の順守を誓い合い、維持・管理しており、おかげで、当時、この地域は、随分と活気を帯びていたのである。
湿った雑草の堤を、そろりと川岸に降りたった九十九は、あまりにも長閑な様子に驚かされた。
ちょうどそこに、里の配下の問丸の主人、痩せこけた小男の清兵衛が、船頭や人足を指示していたので、捕まえて問うた。
「都の公方様が、殺された。伝令は伝わっとうわなあ」
清兵衛は、地味な着流しの小袖の上から肩を掴まれ、驚いた様子をしている。
「あっ、これは九十九様、お帰りになられましたのやなあ。確かに聞いとります」
「確かにやない。いったい、この長閑さは、なんね?」
不可思議に思った九十九が捲し立てる。清兵衛が圧倒されている。
「確かに、小七郎様らが、お戻りになって、公方様のこと、お聞き申しました。皆も一時は、不安を隠せぬ様子やった。されど伊波多の婆さまが、案ずるなとおおせに。我ら太古より、神聖なる巫女の一族、禁裏様の御厨子所にお仕えし、天子様の膳に鮎を供する供御人の一族ぞ。禁裏様のお出入りお構いなし。川魚の扱いも、川上も通行勝手、と桂川のことでは、諸役免許を賜っておる。何も変わらぬ。と皆をお静めなさったのや」
九十九は「さすがに、婆や、動じとらへんな。婆の威厳は、凄まじく大きい。うちも里のこと、もっと誇りを持って、語れんとあかんわ」と改めて思う。
「それよりも、もっと大変なことに、なっとうし、館に行ってみなされ」
「もっと大変なこと? なんね」
「いったい、公方様殺害の急報より大変なことがあるのやろか」と不思議に思う九十九に、清兵衛が少し笑みを浮かべた。
「まあ、行けば分かりますよって……」
二
松尾社より罧原堤を横目に下り、今井用水の傍ら、松室の地から、上桂にかけて、月読命を祀る里の鎮守、月読神社があった。当時は、広大な敷地を有し、朝廷より最重視された延喜式内社である。
九十九は、上桂郷を囲う、堀と土塁の惣構を抜けた。郷の北門付近から繋がる、大きな石造りの鳥居をくぐる。眼前に迫る松尾山麓が、鮮やかな新緑に蔽われていた。
「月影、お前は、ここまでや。はい、ご褒美や」
と飼い葉桶にある干した萓や小笹を与え、、月影を、馬舎の敷き藁の上に入れた。
石段を百段ほども上がっていくと、傍らには、藁葺きの客殿があり、奥の庭園より流れ出ずる小川に、木橋が架けられている。橋を渡ると、朱、藍、橙の色彩鮮やかな、二階建て楼門に至る。
「いつもながらに、疲れるこっちゃ」
と思いつつ、もう一踏ん張り、さらに急な石段が続く。
周りを竹林に囲まれた参道は、鬱蒼として昼なお暗く神秘的な佇まいだ。途中、入母屋造りの石祠二体が祀られ「月読神社」の文字が刻まれている。聖徳太子社もあった。
解穢(かいわい)の水が沸き出る石造りの井戸、紙垂の巻かれた縁結びの木を横目に進むと、鮮やかな朱塗りの鳥居が現れた。鳥居をくぐると、松尾造りの祈祷殿と御本殿が、悠然と並んで鎮座し、手前には、木目調の欄干が設けられた舞殿をも併せ持つ。
祈祷殿の傍らには、大太鼓と大幣が飾られていた。桂の里は「月の影は桂の巨樹」と、その名を中国の故事に由来し、月の桂と愛される土地柄だ。象徴するかのように、沈丁花の花が咲き誇っていた。
何やら奥が騒がしいな、と思いながら、九十九は崖沿いに、へばりつくように生える桂の木の袂を抜けて、境内を進む。紙垂の巻かれた月延石の前に篝火が焚かれ、十数人の里の巫女たちが、一心に祈祷をしている。
「月読命某神社乃恐美恐美母 親王妃宮今年乃春乃頃与里御身体芽出度伎御吉兆……市杵島姫神介給布御儀式……御食御酒種種乃味物乎献奉里 ……恐美恐美母白須……」
と前列の二人が祝詞を捧げる。
「悪霊退散、悪霊退散……」
後ろの者どもが、白木の棒の先に、金箔、銀箔、五色の紙垂をつけた大麻(おおぬさ)を、左右に振り回し、その幣に穢れを吸いこもうと必死になっている。
「安産の祈祷や。誰か、産気づいたな、これだけの人数、相当、気合が入っとうなあ」
と思っていると、後列にいた巫女の一人、まだ齢若い下弦が、九十九に気がついた。
萱草色の緋袴の裾から、細くしなやかな足元を覗かせ、そっと近づき、耳元で囁く。
「九十九様、お帰りなさいませ」
「何があったんや?」
「ええ。かつて市杵島姫神様が、月読尊とともにこの地に降りたちし時、撫でて心身の安泰を祈願したと云われる月延石。この安産の石に、祈願しておりますのや」
「分かっとうし。月から延びてきた神石なんやな。何でそうしとんや、と聞いとうや」
九十九は、のんびりゆっくりと話す下弦に、少しいらついて問うた。「何でこの子は、いつもこんなに、のほほんとしとるんやろ。ほんま調子狂うわ」と思う。
あまり気にせぬ様子で、下弦が更にゆっくりと話す。
「かの、やんごとなきお方のためどす」
「何やて? かの姫様……、一つ月が早いんやないん」
「そやし、みんな大慌てどす。石清水八幡はんでも、祈祷が始まったそうどす」
「ほうかあ」
下弦は、不思議そうな表情をしている。
「それにしても、最近は、お公家様方の御内室のお産が、多おすなあ。何でですのん?」
伊波多は「そんなこと、うちに聞かれても、知らんわな」と思う。それでも、大真面目で問う、若い下弦に、何らかの返答を、してやらねばと思った。
「さあ、まあ、摂関家や青華家のやんごとなきお方たち、長らく政から遠のき、和歌や連歌に打ち興じておるわ。他にすることが全然ないんや、きっと。ふふっ」
九十九は男女の交わりを想像して「変なことを言ったかな」と少し気恥ずかしくなってしまった。
三
崖沿いに神社と併設して、桂の里の棟梁、伊波多の婆の住まう館がある。
竹林に包まれた正面には、防御機能を備えた木戸が設けられ、だだっ広い敷地の中、建物は、九間ほどの藁葺き、掘立式の木造造り。渡り廊下が繋ぐ離れには、欄干も設けられ、広い御産所があった。檜の板張りで、田舎には似つかわしくない、豪華な施設である。
庫裏の前では、大きな釜に湯が沸かされ、小袖の裾をたくし上げ、やはり頭は桂包み、白襷掛けの女たちが、右往左往している。
「もっとようけ要るし、急いで沸かすんや」
「気をつけや、ほんに熱いし、慌てず、ゆっくり運んだら、ええさかいなあ」
湯を運ぶ女たちの桶から、熱湯がこぼれ落ちる。皆顔を歪め、必死の形相だ。
九十九は「確かに、こりゃ、えらいこっちゃ」と思う。庫裏横の玄関から、急いで奥座敷に向かった。
周囲に畳を追回しに敷き、中央は板敷を残す、すべての灯が消されている。月明かりで、僅かに姿が認められる婆がいた。月読尊を祀る神棚の下で、大きな掛軸の前の褥に座す。
六十過ぎかと、思っているのだが「齢など数えたことがないわ」という婆のこと。孫娘の九十九さえ、本当の年齢を知らない。
久しぶりの面会だったが、紅の緋袴の巫女装束で座る婆を見て、一段と老けたように感じた。霊力の使いすぎではないかと、心配にさえなる。
「クキリクア クウンバン ウンタラカンマン ボロン ソワカ……、市杵島姫神よ、出でて神託を授け給え……ウンタラカンマン オ~ウォ~」
五芒星の真ん中に座し「天、地、玄、妙、行、神、変、通、力、勝」の十字を唱えては「エイ、ヤア」と刀印を打ち下ろす。
真っ白な長い髪の婆は、力強い重音を発し、囲炉裏の炭で、亀の甲羅を焼き、ひび割れの様子から、卜占を行なっている。亀の甲羅を床に叩きつけ叫んだ。
「うん、厳しいなあ、小凶と出ておる。助かれば良いが」
「婆様、なんで、灯り全部、落としてるん?」
不可思議に思った九十九は、婆に問う。「里帰りの挨拶もせなんだわ」と思った。
婆は木炭の残り火をも消し去る。九十九の顔を、下からじっと覗き込む。皺を寄せたが、少し笑みを浮かべた優しい顔で、まるで何かを伝授するかのように語りだした。
「ええか、火もまた、お産の穢れを受けるよってや。お産は穢れの一つやでなあ。そやから、都の高貴なお人たちは、洛中でお産はなされぬのや。九十九、座して聞かぬか」
九十九は「しまった、わざわざ婆の長い話を、焚き付けてしもうたわ」と思う。
何度となく聞かされたいつもの話を、婆がまた話し始めた。
「かつて、我らが始祖、月読尊が、比売大神様と市杵島姫神様と申す、それは美しき姉妹とともに、日ノ本に降り立った。やがて、豊葦原の中つ国に築かれた王国で、妹御であらせられる姫神様は、月よりの神石(隕石)を崇敬し、御心を静められ、大神様をご出産なされたのじゃ」
「うん、そやったな。ああ」
九十九は「しゃあない、最後まで付き合うわあ」と覚悟を決めた。
「え~こほん、語りを続けるぞ。ところがなあ、安らかな日々は続かなんだ。時を経ること十数年、発展する王国を恐れ、再三に亘って侵略が繰り返された。姫神様と大神様は、一族を守るため、ついに東遷し、王朝の歴史が始まったのじゃ。一方、年老いた月読尊は、安穏の地を求めて、湯津桂に寄って立った。これが、桂の里の起こりや。この神石は、月延石(月より来た石)と呼ばれておる。三つに割られた神石は、この月読の祠、糸島の鎮懐石八幡の社、あと一つが、壱岐の月読の社に祀られたのじゃ」
「うん、うん、その通り」
九十九に構わず、婆がさらに続けた。
「え~、こほん。それでじゃ。その後、帝や、今は五摂家に分かれておるがの、藤原の一族とともに、この京の地に、陰陽に基づき、理想郷ともいうべき、平安京を築きあげた。しかしじゃ、以後、我らが表に出ることは、もはやない。我らは陰に徹して、この平安の都の安泰に暗躍することを決意したのや。我が一族の宿命を背負って生まれた者、それが九十九、お前なのじゃ。良いか」
延々と続く長い話が、四半時も続いた。
「あ~、あっ」
九十九は「そろそろ終わりやなあ」と思いながら、思わずあくびをしてしまった。
気にもせぬ様子で、婆がようやっと最後のくだりを語る。
「よいか、人の一生の運は、臍の緒を切る産婆によって、与えられるのや。赤子を奪い去ろうとする物の怪より守り、命を吹き込む大切な役目、しかと引き継がねばならぬ」
九十九は「ようやっと本題に入れるわ」と思った。
「よう分かったし。時に婆様、公方様が殺され、この西岡あたりを三好党が放っては置かぬのやないか。我が里は、どうなるんや?」
婆は、しわくちゃの顔を、さらに寄せて、薄ら笑いを浮かべる。
「焦らずとも良い。この神聖なる桂の里に、天子様の臣下の臣下など、手出しできぬわ」
「革嶋の館は、どうなるん?」
「我ら革嶋と日常を一にしておるのも、川上の利が一致しておるからに過ぎぬ。良いか、九十九。我が後継として、どのようになっても、里の誇り貫き通すこと、忘れるでない」
「また、言うし。石清水八幡はんと御幸宮に、神官として姉様方がおられるやない。なんで、うちやのん」
九十九は、一番下の自分が、後継と言われることが、どうしても腑に落ちなかった。
「伊波多の後継は、選ばれし者……、まあ、ええわ。いずれ分かる。時に、明日の夕刻、向日神社にて、西岡被官衆の合議じゃ。あての名代として、おまはんが出るのや。ええか」
「へっ、分かったし」
九十九は「そんな大役を」と思いながらも、しぶしぶ了承した。するとそこへ、御産所よりの使いの者が催促に来た。
「婆さま、そろそろ、出るようや。よろしゅうに」
「九十九、おまはんも来るんや」「へっ」
九十九は、お産の立会いは初めてだったから、興味津々で、婆の後に続いた。

月読神社
四
静かな奥座敷から一転して、離れの御産所では、壮絶な闘いが繰り広げられている。
「う~う~、ふっふっふっ、う~うお~」
まるで龍神の声かとも、思われるような雄叫び。
妊婦の額から、肌蹴た白襦袢の首筋から、肩からすさまじい勢いで汗が流れ出る。
隣室の床板を外して盾とし、米俵を体の両側において、その間で、口に白布を噛みこみ、断末魔を思わせる凄まじい形相で踏ん張っている。
「う~、うお~、うお~」
苦しさで暴れる妊婦を、女たちが数人掛かりで押さえつける。
「いかん、体が冷えてきとる。足と腰をさすって、気を入れるんや」
産婆の叫び声とともに、女たちが両足と腰を、摩擦するかのごとくさすり始めた。
「ええか、もう少しや。気張りや」
「う~ふっふっう~ん」
「気張るんやあ」
と励まされれば、妊婦がぐっと踏ん張る。
「力抜けえ」
で一旦、力を抜く。
「ひーひーふぅ」
「ひーひーふぅ」
と産婆が耳元で復唱する。産婆の額からも汗が止め処ない。
「良し、体も温こうなってきた」
「さぁ、来るんや。ひーひーふぅ、ひーひーふぅ」
傍らで見ていた九十九は、お産というものは、こんなにも凄いのかと感嘆した。
どないしょう、されど手伝おうにも、圧倒されて、身動きが取れない。
「よっし、ええよ、ええよ、見えてきたし」
「う~、うお~」
産婆たちの声に励まされ、妊婦がさらに踏ん張る。
しかし、妊婦の顔色は真っ青だった。紫色の唇を震わせながら、産婆の衣装を揉みくちゃに掴み、息も絶え絶えに声を振絞った。
「ふう~ん、ふう、ふう」
「あかん、逆子や、みなで引っ張り出すえ」
「せえのお、よいしょ」
「うお~」
松尾山麓をも揺るがすほどの、妊婦の悲鳴が響き渡る。
ようやっと、引っ張り出すものの、赤子は泣きもせず、身動きもしない。急な破水で、臍の緒が首に絡みつき仮死状態だったのだ。その場に言いようもない緊張が、駆け巡る。九十九も焦った。顔から血の気が引くのを感じた。
「あかん」
産婆は赤ん坊の足首を掴み、逆さまにすると赤ん坊の背中を叩いた。
「ええか、泣け! 泣け! 泣かぬか!」
八半刻に足らぬほどの静寂。
「うわんぎゃあ~、あぎゃあ~」
と赤子が、大きな大きな声で産声を上げた。
「やったあ~」
「ほんに」
その場が歓喜に満ちた。
「良かったし、良かったし、うん」
女たちは、涙ぐんだ目で、互いの肩を叩き、縦に飛び跳ね、頬を摺り寄せる。
早産のために体は小さいが、元気な男子であった。在所の使者より届けられた守刀と掻巻(綿入れの夜着)を袂に置き、臍帯を切って縛り、傷跡を焼く儀式が行われた。
「よし、付いとるもんも付いとる」
と頷きながら、臍切り婆役の伊波多の婆が、すばやく臍の緒を切りとり、さっと鮮やかな手並みで結んだ。
生まれたばかりの赤子は胞衣(胎盤)と一緒に請衣という白羽二重に包まれ、産湯に浸かる。この時、古例に従い、桂川の水と月読神社の解穢れの井戸の水を合わせたものを使う。洗浄された胞衣が白木の胞衣桶に納められ、隣室の西北隅に置かれる。
産湯から上がった赤子は、襦袢と袖なし、御巻で巻かれた。
赤子が、元に返されると、妊婦は、力を使い切った弱弱しい手で、慈しむように顔を撫で始めた。その姿は、ふくよかな幸せに満ちているようだった。
九十九は、眼と鼻筋の間を流れ落ちる、止め処ない涙の温もりを感じた。「かつて、こんなに感動したことが、あったろうか」と思う。
「良かった、ほんに良かった……」
九十九が、境内に出たときには、もう夜が明けかけていた。
透き通った桂川に早朝の日が射して、照り返しがまぶしい。川面には、燕や東風鳥が落ちては上がり、落ちては上がりを繰り返す。鴨の親子が、とっとこととっとこと、と何とも危なげに、罧原の堤を斜めに横切っていく。
九十九は微笑ましい姿に「おまはんらも、頑張って生きるんや」と、励ましていた。
「お疲れさんどした」
と、下弦が愛らしい笑窪を浮かべ、会釈した。本人も疲れきった様子だ。
「この子も、よう頑張った。さっきはいらついて、すまんやったなあ」と、つくづく思う。
陽射しを避けて、額を腕で覆う。いつになく優しい口調の物言いが、自然に流れ出た。
「そっちこそ。今日は、ゆっくり休みや」
九十九は、公家衆に「することがないのやろ」と言った自分を恥ずかしく思っていた。
「命の誕生とは、こんなにも凄いのか」と感動に打ち震え「この命、決して粗末にはでけん」と心の中で、しみじみと思った。
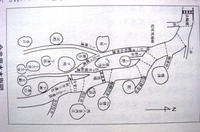
五
次の日の夕刻、九十九は、またも駆けていた。
九十九は、今井溝に沿って、一路ひたすら南西に駆けた。
田圃の畦や緑が濃さを増し、野原の所々に、ひときわ目立つ藪甘草の橙色の花に、心を奪われそうにもなる。
二里と少し、四半刻ほど駆けると、十一ヵ郷を抜けて、向日野から乙訓地域(現在の向日市や長岡京)に入った。この乙訓地域と、十一ヵ郷を合わせた地域が、西岡(にしのおか)と呼ばれている。
松尾社、天竜寺、東寺、石清水八幡といった寺社、近衛、鷹司など摂関家などの所領が入り乱れる土地であったが、今井溝を始めとする農業用水や、交通・交易など広域に係わることを、合同で対処する中、独立した惣国として発展してきた。
幕府の被官でもある国人衆が集まり合議がなされるのが、向日神社であった。地域の要所に城館を構える土豪たちである。
新緑薫る向日山の麓、元稲荷山古墳を始めとする古墳群を見ながら、鬱蒼とした鎮守の森を登る。大きな常夜灯と朱色の鳥居の間をくぐって、流造桧皮葺様式の境内に入る。
駆けつけた参集殿には、三つ巴の紋の描かれた向大明神の掛軸があり、大広間では、すでに三十人余の国衆たちが集まっていた。
男たちが喧々諤々迫力の論争を繰り広げている。
九十九は「かつてない事態に、皆、真剣なんや」と、つくづく思う。「まあ、ほんまの熊みたいや」と思う男が、一番最初に目に付いた。
「おのれ、三好党のものども、増長するのもええ加減にしや。国主を殺害するなど、言語道断や。奴らのような雑兵にや、決して屈せぬは」
小塩荘をはじめ高畠・大岡荘、勝龍寺領、西岡新馬場跡などに支配を及ぼす神足村の国衆・神足掃部が、舶来品の白熊の腰蓑をつけ、それこそ、まるで大熊のような、大きな体を揺らし、息巻いていた。
「そうや、我が神聖なる領土とて、三好一派の軍勢など一歩も入れへんわ。西岡土豪衆の力見せなあかん」
開田城主・中小路宗俊は、盤領の一つ身、白水干姿。元は菅原道真の一族という中小路家は、代々開田天満宮(現在の長岡天満宮)の神官でもあった。

かつての開田城
秦氏の末裔と称する物集女城主・忠重が、小袴の上に羽織った生絹の狩衣を整えながら、冷静な口調でさらに続いた。
「かの応仁の大乱、また続く細川家の抗争で、一度は分裂した我ら被官衆であった。しかし、その後は、向大明神のご加護の下、衆議一決、この西岡の地を守り抜いてきたやないか。西岡一揆の再来や」
今里の能勢頼広は、すでに赤胴の甲冑を着込み、戦闘態勢だ。
「そうや、奴らは必ず、桂川からの取水による水利灌漑、川上の渡の特需を欲するやろ。我らの生命線、決して渡すんやない。一揆も辞さず」
九十九は「みんな、それぞれ好き勝手な恰好してはるわ、あの熊の毛皮、もう暑うないんやろか」などと暢気に聞いていた。
乙訓地域とは、かつて、たった十年の幻の都・長岡京が営まれた地域である。
西岡の土豪たちは、幕府の御被官となっているものの、かつての山城の国一揆と並ぶ西岡一揆を起こし、百姓が国、惣国を創り上げてきた土地柄だ。それだけに独立心も強い。
年老衆の意見に、他の国衆も一斉に叫んだ。
「一揆」「そうや、惣国一揆や」
雰囲気に圧倒され、中々、口を挿めないでいた九十九だが、意を決して叫んだ。
「そうや、一揆や!」
女特有の甲高い声に皆が驚いた。
一瞬、場が静まり返り、一宣の傍らにいた秀存が、慌てて叱責した。
「九十九、そなた何故、ここにおるのや? 控えぬか」
「桂の里、伊波多の婆が名代にて、九十九でおます。皆の衆、以後お見知りおきを」
九十九は、力強く挨拶した。
秀存が「まさか」といった表情をしている。
「も、もしや、そなたは、婆の後継やったんか?」
「そうでおます、忍びの任ゆえ、隠しておりましたのや。かんにんや」
藍染羽織の上から腕を組み、静かに聞いていた革嶋一宣が、口を挿んだ。
「して、九十九、いや、九十九殿」
一宣らの礼を尽くす物言いに、九十九は「まあ、急に態度が変わったわあ」と、里の棟梁の威厳を垣間見たように思った。
「里の具申も、皆と同意と申されるのやな」
「へっ、うちら三好長慶殿に従うてきたは、公方様、ひいては禁裏様の意があってのもんや。長慶殿亡き後、国主を討った三好党や、まして松永弾正などに従う道理は、おまへん」
この時、月行事を務める一宣が、衆議をまとめた。
「皆の具申は、よう分かったし、おのおの方は、三好党を敵として、共に立ち向かうということで、ええんやな。皆、郷で軍勢を整え、我が惣国の拠点、青龍寺城に結集や」
「よっしゃ」「お~」
皆が異口同音に気勢を上げる。
しかし、九十九だけは、この時、年老衆の一人、鶏冠井(かいで)村を領する鶏冠井城主の光則が、静かに腕を組み、おざなりの同意を示しているのが、少し気になった。
鶏冠井村は、かつて長岡京の大内裏のあった地域(現在の西向日駅周辺)でもある。
年老衆、国衆らが次々に退座し、秀存も、退座の構えをしながら、九十九に要請する。
「九十九殿、里のお力をお貸し願えるか?」
「もちろんでおます。これより立ち戻り、至急、革嶋城へ駆けつけますよって」
「うん、しかと頼んます」
九十九は、無機質な口調は変わらぬものの、いつもとは違って、礼を尽くす秀存の言い様は、何となく心地よいものだと思った。
しかし、一方で難しい局面に来ていることを、感じ取っていた。

向日神社
六
九十九は、大急ぎで桂の里に戻った。
館の庭の竹灯篭に灯が燈され、広がる幽玄の世界。京唐紙の襖障子には、花鳥風月や跳ね馬が描かれ、灯籠の明かりに照らされた雲母が、炎の揺らめきとともに上品に光る。
襖をすべて開け切り、涼をとりながら、婆は、やはり卜占に取り組んでいた。
「婆様」
九十九は、逸る気持ちを抑えきれない。部屋に駆け込む九十九を、婆が左手で制する。
「待て、あっ!」
囲炉裏の上で、焼かれた亀の甲が、パカ~ン、と真っ二つに割れ、周囲に飛び散った。
九十九は「えっそんな! 最悪の占いが出た」と心中、穏やかでない。
「う~ん、大凶じゃな。九十九、この合戦、行くんやない」
「すでに知らせが入ってたんやな」
婆が静かにうなずく。
「西岡は、必ずしも強固な一枚岩やない。それぞれの惣中の集まりや。三好党もまた、最も取水豊かなこの地を欲するに、あらゆる手立てを尽くすはずや。何倍もの軍勢に攻められては、土豪衆に勝ち目はない。里を動くでない」
「婆様」
九十九は、今度ばかりは、占いに逆らう気になる。いかにも不服といった顔を造った。
婆の目をじっと見つめる。ふうっ、と溜息をつきながら、婆が優しい表情になった。
「おまはん、若もの(秀存)に惚れてとうなあ」
「何もかもお見通しなんやな」
「ええか、九十九。我が里の女子は、他から夫を迎え、女系相続が習い。里の家を継げるものでなければならん。おまはんの婿も、いずれ神託が下るやろ。諦めるんや」
九十九は、涙目になっていくのを感じた。
「うちかて分かってるし。そうやない。うちは、これまで受けた恩義を返さず、裏切って、ほんで、この桂の里が、幸せになれるとは思わへんのや。うちは一人になっても行くし」
「待ちや、九十九」
部屋から飛び出そうとした九十九は、一瞬、足を止めた。
後ろから、婆の声を聞く。
「市杵島姫神様のご加護のもと授かりし命、決して粗末にするんやない。肝に銘じるんや」
九十九は「婆様、ごめん、うちは、この感情を抑えることができひん」と詫びていた。
七
外に出ると、月読神社の境内には、上弦、下弦、地蔵、千百を始とする、くノ一衆、小七郎、与一を始とする男の乱波衆が結集していた。
「九十九様」
と総勢百人近くが一斉に合唱する。
「なんね、これは?」
驚く九十九に、小七郎が、片手を地面につけて、礼をとった。
「若の救援、婆様より、ご下命が下った。今日より、乱波衆の指揮は、おまはんが執りや」
「うちが?」
「婆様は、おまはんが、止めても聞かんことなど、はなからお見通しや。すでに手筈を、指示なされておったわ」
九十九は、「婆にやられたわ。何でもお見通しか」と思う。首を斜めに振り、上唇を舌で舐める。涙は止まらぬが、戻った笑みで、自分の顔が緩むのを感じた。
「九十九様、よろしゅうお願い申します」
と下弦が、愛らしい笑窪を見せながら、いつものようにおっとりとした調子で、九十九に近づき、采配を手渡した。「可愛い奴やなあ」と思う。
パン、パンパーン……。
九十九は、采配を手に取ると、涙をさっと拭き取り、神殿に二礼二拍一礼をした。
それからおもむろに皆に向き直り、采配を大きく振りながら、命を下した。
「みんな、行くよ」
「やあ~、出会え、出会え、そや出会え」と松尾山麓に、皆の合唱が木霊する。
九十九は、駆けた。日の本一と言われる、鬱蒼とした大竹林を抜け、今度は、九十九軍団となって、南へ一路、革嶋城へ駆け抜けた。
Posted by 篠田ほつう at 19:30│Comments(0)
│小説「桂女恋花」




