2012年10月26日
善峯寺
京都市内からは小一時間、数十キロしか離れていないのに、あたりはまるでずいぶんと山奥に来たように感じられる澄み切った空気と静寂が広がります。かつて王侯貴族たちが宴や鷹狩りをして遊興をせし山里・大原野。一車線の曲がりくねった細い道を走り、うっそうとした木立の中をぬけると、その頂上に位置するところに気高くそびえ立つのが、西国三十三所第二十番札所の「善峯寺」です。開基の源算上人は、47歳の時、当山に入り小堂を結び、十一面千手観音の像を刻み本尊としました。 以後善峯寺は、観音信仰の高まりとともに早くからその霊場として栄え、後一条天皇 から「良峯寺」の寺号をたまわって以来、歴代天皇の崇敬あつく、中世 には青蓮院宮が住職を務めた 「西山宮」と称する門跡寺院となり、五十あまりもの堂塔を有する大寺院となりました。 応仁の乱で伽藍の大半を焼失しましたが、寺を再興したのは、徳川五代将軍綱吉の生母「桂昌院」の寄進によります。 現在は天台宗単立寺院です 。
この寺の寺伝では、開基である源算上人は現在の鳥取県に生まれ、正暦二年(991)九歳の時、 比叡山の恵心僧都 源信(えしんそうず げんしん)のところに徒弟に入り、 十三歳で剃髪受戒しました。
師と仰がれた源信は、九歳で比叡山に上り良源(元三大師)に師事、貴族化した天台教団を嫌い、 横川(よかわ)に隠棲し、『往生要集』を著わし、末法思想が普遍化している中で、阿弥陀仏を念じることにより、来生を西方極楽浄土に往生しようとする思想を確立した人物でした。
源算上人が剃髪したのは、『往生要集』が世に出た寛和元年より十年後のことで、浄土は西方にあるとする思想から、比叡山の西の連山、つまり西山地方がそれにあたると考え、長元二年(1029)後一条天皇在世 の47歳の時、この地に法華院と号する小堂を建てるのです。
五年後の長元七年九月二日、天皇より「良峯寺」の号を賜り ます。さらに八年後には、東山の鷲尾寺の本尊であった千手観音像(安居院仁弘法師作)を当寺に移 して本尊とするようにとの後朱雀天皇の綸旨があり、千手堂を建てて像を安置しています。
その後、後三条天皇が皇太子誕生祈願の報恩のため、本堂、阿弥陀堂、薬師堂、地蔵堂、三重塔、 鐘楼、仁王門、および鎮守七社を建立したと伝えられています。
応仁の乱で焼失した伽藍を再建したのは、桂昌院でした。桂昌院は二条家に仕えた本庄宗正の娘であるとされていますが、本当は京都の八百屋(酒屋とも)仁右衛門の娘で、 その名をお玉といいました。子宝に恵まれない仁右衛門が善峯寺の観音菩薩に願掛けをしたところ、お玉が生まれたと言われており。幼いころ両親に連れられて、何回か善峯寺にお参りしたらしく、のちに献歌を残しています。
「たらちをの 願いをこめし 寺なれば われも忘れじ 南無薬師仏」
成長して三代将軍家光の側妾お万の方の侍女となり江戸へ下ったお玉は、秋野と名を変えて大奥で 働くようになりますが、やがて家光の寵愛を受けて徳松を安産します。
家光の没後は黒髪を落として桂昌院となり、その子、徳松は舘林に封ぜられて綱吉となるのです。 四代将軍家綱には子供がなかったため、その没後、綱吉が五代将軍となり、桂昌院は将軍の御母堂 として江戸城へ迎えられます。「玉の輿」の語源はこの話から来ているとも言われています。
何不自由のない身分となった桂昌院は、幼いころのゆかりの善峯寺のため尽力します。住職の願いは次々と実現し、それらは建築として、また仏像、宝物として今に伝わっています。
善峰寺では桂昌院の恩に報いるため に遺髪を境内に納め、桂昌院廟としておまつりしています。

娯楽時代劇に登場する桂昌院は、「犬公方」と云われた悪将軍・五代徳川綱吉や側用人の柳沢吉保、悪僧と誤解されている隆光と共に、よくないイメージで描かれるようです。 しかし、最近の調査では、それらの謂れは、事実に反して後世に作り上げられたものとの再評価が始まっています。
桂昌院はこの善峯寺をはじめ、応仁の乱で焼き払われ、再建不可能と言われた数々の大寺院の復興事業や寺院建立など、後世に多大な仏教遺産を残しました。
このことが、当時の財政を圧迫させたと言われてきましたが、今日では、今でいう景気刺激、公共投資のようなもので、仏教を中心とした宗教心を柱に庶民文化を建て直すことの必要性を示したもので、むしろ文化的積極財政と評価される見方も進んでいます。
娯楽時代劇に出てくる、桂昌院や綱吉の権力を象徴する最も有名な話として「生類憐れみの令」があります。綱吉に嫡子がないのを心配した桂昌院が、僧 隆光の「殺生を禁じて生き物を大切にすれば子が授かる」
との言葉を信じ、綱吉に訴えたことから始まった悪政とされていますが、最近の説では、本来将軍になるはずもない勉学ひとすじの堅物、綱吉が、犬猫動物はもとより人まで試し切りの対象となっていた殺伐とした江戸の世相を憂い、儒教の精神で変革しようとしたものであって、平和な社会に変換させた、との再評価もなされているのです。
皆さんが、何れ善峯寺 寺宝館文珠堂で、ご覧になられるであろう桂昌院ゆかりの品々は、善峯寺諸堂とともに、彼女の仏教に対する深く厚い信仰心があったればこそ、拝見することができるのです。
山門

まず最初に風格と山寺の風情を漂わせる山門(仁王門)が迎えてくれます。
山門楼上には伝源頼朝寄進の運慶作の本尊・ 文殊菩薩像と両脇に金剛力士像を安置していると云われます。
山門も徳川5代将軍綱吉の母・佳昌院が再建したと伝えられています。
本堂観音堂
山門を入ると石段の上に1692年(元禄5)再建の入母屋造本瓦葺の本堂(観音堂)が落着いた佇まいをみせています。
本尊に仁弘法師作の十一面千手観音菩薩、脇立に源算上人作・十一面千手観音菩薩(洛西三 十三ヵ所第一番)がお祀りしてあります。

桂昌院が徳川綱吉の「厄除け」のために寄進した厄除けの鐘。
不動明王五大尊を祀る護摩堂は、元禄5年に建立されました。
多宝塔

本堂前から、さらに石段を登ると1621年(元和7)に賢弘法師が再建したと云われる多宝塔(重要文化財、江戸時代初期 元和7年 1621年再建、桧皮葺、高さ 約12m 塔の内部は、来迎柱が2本あり来迎壁を設け、愛染明王を安置する。須弥壇には逆蓮柱・ぎゃくれんばしら・をもつ )や佳昌院が鉄眼の一切経を収めた経堂、源算上人百十七歳の像を祀る開山堂などが静かな山の雰囲気のなかに歴史を刻んで 佇んでいます。長寿のご利益を授かることができます。元禄5年に建立されました。
遊龍の松

春になると経堂の近くには佳昌院お手植えの枝垂れ桜(楓との合体木)が美しく咲き、華やかさを醸しています。
多宝塔の前には元禄年間に佳昌院の希望で移植されたと伝わる高さ2m、主幹の周囲1.8mの遊龍の松(樹齢推定年600年 天然記念物)が北へ22m、西へ24mと枝を延ばし、豪壮な趣を呈しています。龍が遊んでいるようにも見えるところから1857年(安政4)に花山前右大臣家厚公が遊龍松と名付けたと云われます。
金閣寺の陸舟の松、大原宝泉院の五葉の松(近江富士)と並んで、京都三松と言われています。
残念ながら平成六年に松クイ虫の被害で15m伐採しています。
佳昌院廟

多宝塔西には佳昌院の遺髪を納めた佳昌院廟があります。(墓は徳川家の菩提所・芝増上寺にあります)御廟の横からは、東山三十六峰や京都市街が一望できます。
約三万坪といわれている善峯寺は、境内全体が回遊式の庭園となっていて、年中、四季折々の花々が楽しめます。紅葉は境内南側の中腹から約一千本の木々があります。
幸せを招くお地蔵さん 幸福地蔵
これも三百三十年前に桂昌院が祈念されたと伝えられています。自分以外の人の幸せをお願いすることとされています。
奥にはあじさい苑があり。夏の時期には一面がアジサイに覆いつくされます。
源算上人が写経のための墨を摺ったとされる白山名水が龍の口から流れています。
釈迦堂と薬湯場
十三仏堂を過ぎ、さらに参道を上に行くと石仏釈迦如来を祀る釈迦堂があり、その横には釈迦岳でとれる百草湯が 沸く薬湯場があります。

奥の院
青蓮の滝 …… 滝の竿石は、青蓮院より下賜されたもの
桂昌殿 …… 昭和67年の建立 桂昌院が奉られています。
阿弥陀堂 …… 本尊、宝冠阿弥陀如来。徳川家代々と善峯寺の
信者の位牌が安置されています。
青蓮院の宮御廟 …… 宮内庁管理 善峯寺の住職を勤めた門跡
の御廟所です。
奥之院 薬師堂 …… 1701年(元禄14年)の建立 出世薬
師仏が安置されています。桂昌院の両親
が祈願したといわれます。
奥の院からは京の街並みが一望できます。
この寺の寺伝では、開基である源算上人は現在の鳥取県に生まれ、正暦二年(991)九歳の時、 比叡山の恵心僧都 源信(えしんそうず げんしん)のところに徒弟に入り、 十三歳で剃髪受戒しました。
師と仰がれた源信は、九歳で比叡山に上り良源(元三大師)に師事、貴族化した天台教団を嫌い、 横川(よかわ)に隠棲し、『往生要集』を著わし、末法思想が普遍化している中で、阿弥陀仏を念じることにより、来生を西方極楽浄土に往生しようとする思想を確立した人物でした。
源算上人が剃髪したのは、『往生要集』が世に出た寛和元年より十年後のことで、浄土は西方にあるとする思想から、比叡山の西の連山、つまり西山地方がそれにあたると考え、長元二年(1029)後一条天皇在世 の47歳の時、この地に法華院と号する小堂を建てるのです。
五年後の長元七年九月二日、天皇より「良峯寺」の号を賜り ます。さらに八年後には、東山の鷲尾寺の本尊であった千手観音像(安居院仁弘法師作)を当寺に移 して本尊とするようにとの後朱雀天皇の綸旨があり、千手堂を建てて像を安置しています。
その後、後三条天皇が皇太子誕生祈願の報恩のため、本堂、阿弥陀堂、薬師堂、地蔵堂、三重塔、 鐘楼、仁王門、および鎮守七社を建立したと伝えられています。
応仁の乱で焼失した伽藍を再建したのは、桂昌院でした。桂昌院は二条家に仕えた本庄宗正の娘であるとされていますが、本当は京都の八百屋(酒屋とも)仁右衛門の娘で、 その名をお玉といいました。子宝に恵まれない仁右衛門が善峯寺の観音菩薩に願掛けをしたところ、お玉が生まれたと言われており。幼いころ両親に連れられて、何回か善峯寺にお参りしたらしく、のちに献歌を残しています。
「たらちをの 願いをこめし 寺なれば われも忘れじ 南無薬師仏」
成長して三代将軍家光の側妾お万の方の侍女となり江戸へ下ったお玉は、秋野と名を変えて大奥で 働くようになりますが、やがて家光の寵愛を受けて徳松を安産します。
家光の没後は黒髪を落として桂昌院となり、その子、徳松は舘林に封ぜられて綱吉となるのです。 四代将軍家綱には子供がなかったため、その没後、綱吉が五代将軍となり、桂昌院は将軍の御母堂 として江戸城へ迎えられます。「玉の輿」の語源はこの話から来ているとも言われています。
何不自由のない身分となった桂昌院は、幼いころのゆかりの善峯寺のため尽力します。住職の願いは次々と実現し、それらは建築として、また仏像、宝物として今に伝わっています。
善峰寺では桂昌院の恩に報いるため に遺髪を境内に納め、桂昌院廟としておまつりしています。

娯楽時代劇に登場する桂昌院は、「犬公方」と云われた悪将軍・五代徳川綱吉や側用人の柳沢吉保、悪僧と誤解されている隆光と共に、よくないイメージで描かれるようです。 しかし、最近の調査では、それらの謂れは、事実に反して後世に作り上げられたものとの再評価が始まっています。
桂昌院はこの善峯寺をはじめ、応仁の乱で焼き払われ、再建不可能と言われた数々の大寺院の復興事業や寺院建立など、後世に多大な仏教遺産を残しました。
このことが、当時の財政を圧迫させたと言われてきましたが、今日では、今でいう景気刺激、公共投資のようなもので、仏教を中心とした宗教心を柱に庶民文化を建て直すことの必要性を示したもので、むしろ文化的積極財政と評価される見方も進んでいます。
娯楽時代劇に出てくる、桂昌院や綱吉の権力を象徴する最も有名な話として「生類憐れみの令」があります。綱吉に嫡子がないのを心配した桂昌院が、僧 隆光の「殺生を禁じて生き物を大切にすれば子が授かる」
との言葉を信じ、綱吉に訴えたことから始まった悪政とされていますが、最近の説では、本来将軍になるはずもない勉学ひとすじの堅物、綱吉が、犬猫動物はもとより人まで試し切りの対象となっていた殺伐とした江戸の世相を憂い、儒教の精神で変革しようとしたものであって、平和な社会に変換させた、との再評価もなされているのです。
皆さんが、何れ善峯寺 寺宝館文珠堂で、ご覧になられるであろう桂昌院ゆかりの品々は、善峯寺諸堂とともに、彼女の仏教に対する深く厚い信仰心があったればこそ、拝見することができるのです。
山門
まず最初に風格と山寺の風情を漂わせる山門(仁王門)が迎えてくれます。
山門楼上には伝源頼朝寄進の運慶作の本尊・ 文殊菩薩像と両脇に金剛力士像を安置していると云われます。
山門も徳川5代将軍綱吉の母・佳昌院が再建したと伝えられています。
本堂観音堂
山門を入ると石段の上に1692年(元禄5)再建の入母屋造本瓦葺の本堂(観音堂)が落着いた佇まいをみせています。
本尊に仁弘法師作の十一面千手観音菩薩、脇立に源算上人作・十一面千手観音菩薩(洛西三 十三ヵ所第一番)がお祀りしてあります。
桂昌院が徳川綱吉の「厄除け」のために寄進した厄除けの鐘。
不動明王五大尊を祀る護摩堂は、元禄5年に建立されました。
多宝塔
本堂前から、さらに石段を登ると1621年(元和7)に賢弘法師が再建したと云われる多宝塔(重要文化財、江戸時代初期 元和7年 1621年再建、桧皮葺、高さ 約12m 塔の内部は、来迎柱が2本あり来迎壁を設け、愛染明王を安置する。須弥壇には逆蓮柱・ぎゃくれんばしら・をもつ )や佳昌院が鉄眼の一切経を収めた経堂、源算上人百十七歳の像を祀る開山堂などが静かな山の雰囲気のなかに歴史を刻んで 佇んでいます。長寿のご利益を授かることができます。元禄5年に建立されました。
遊龍の松
春になると経堂の近くには佳昌院お手植えの枝垂れ桜(楓との合体木)が美しく咲き、華やかさを醸しています。
多宝塔の前には元禄年間に佳昌院の希望で移植されたと伝わる高さ2m、主幹の周囲1.8mの遊龍の松(樹齢推定年600年 天然記念物)が北へ22m、西へ24mと枝を延ばし、豪壮な趣を呈しています。龍が遊んでいるようにも見えるところから1857年(安政4)に花山前右大臣家厚公が遊龍松と名付けたと云われます。
金閣寺の陸舟の松、大原宝泉院の五葉の松(近江富士)と並んで、京都三松と言われています。
残念ながら平成六年に松クイ虫の被害で15m伐採しています。
佳昌院廟
多宝塔西には佳昌院の遺髪を納めた佳昌院廟があります。(墓は徳川家の菩提所・芝増上寺にあります)御廟の横からは、東山三十六峰や京都市街が一望できます。
約三万坪といわれている善峯寺は、境内全体が回遊式の庭園となっていて、年中、四季折々の花々が楽しめます。紅葉は境内南側の中腹から約一千本の木々があります。
幸せを招くお地蔵さん 幸福地蔵
これも三百三十年前に桂昌院が祈念されたと伝えられています。自分以外の人の幸せをお願いすることとされています。
奥にはあじさい苑があり。夏の時期には一面がアジサイに覆いつくされます。
源算上人が写経のための墨を摺ったとされる白山名水が龍の口から流れています。
釈迦堂と薬湯場
十三仏堂を過ぎ、さらに参道を上に行くと石仏釈迦如来を祀る釈迦堂があり、その横には釈迦岳でとれる百草湯が 沸く薬湯場があります。
奥の院
青蓮の滝 …… 滝の竿石は、青蓮院より下賜されたもの
桂昌殿 …… 昭和67年の建立 桂昌院が奉られています。
阿弥陀堂 …… 本尊、宝冠阿弥陀如来。徳川家代々と善峯寺の
信者の位牌が安置されています。
青蓮院の宮御廟 …… 宮内庁管理 善峯寺の住職を勤めた門跡
の御廟所です。
奥之院 薬師堂 …… 1701年(元禄14年)の建立 出世薬
師仏が安置されています。桂昌院の両親
が祈願したといわれます。
奥の院からは京の街並みが一望できます。
2012年07月26日
松尾大社

松尾大社御由緒 (松尾大社公式ホームページより)
磐座祭祀
当社の御祭神「大山咋神」(おおやまぐいのかみ)は、当社社殿建立の飛鳥時代の頃以前の太古の昔よりこの地方一帯に住んでいた住民が、松尾山の山霊を頂上に近い大杉谷の上部の磐座(いわくら)に祀って、生活の守護神として尊崇したのが始まりと伝えられております。 近江国の比叡山を支配する神(現日吉大社)と、ここ松尾山一帯を支配する神(現松尾大社)がいたと伝承されます。一方、中津島姫命は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の別名で、福岡県の宗像大社に祀られる三女神の一神として古くから海上守護の霊徳を仰がれた神です。外来民族である秦氏が朝鮮半島との交易する関係から、航海の安全を祈って古くから当社に勧請されたと伝承されています。
秦氏が奉祭してきた海の神と、日本古来の松尾山の神が出会った神域が「松の尾」であったのです。
秦氏来住
五・六世紀の頃、秦の始皇帝の子孫と称する(近年の歴史研究では朝鮮新羅の豪族とされている)秦(はた)氏の大集団が、朝廷の招きによってこの地方に来住すると、その首長は松尾山の神を同族の総氏神として仰ぎつつ、新しい文化をもってこの地方の開拓に従事したと伝えられています。
文武天皇の大宝元年(西暦701)に秦忌寸都理(はたのいみきとり)が勅命を奉じて、山麓の現在地に神殿を営み、山上の磐座の神霊をこの社殿に移し、その女の知満留女(ちまるめ)を斎女として奉仕させました。この子孫が明治初年まで当社の幹部神職を勤めた秦氏(松尾・東・南とも称した)です。
奈良から長岡京へ、平安京への遷都には秦氏の財力が大きく、平安時代には正一位の神職を受け、賀茂の厳神、松尾の猛霊と並び称されて、皇城鎮護の社とされ、室町時代には、全国十数か所の荘園、江戸時代にも朱印地1200石、嵐山一帯の山林を有していたと言われます。
武門の崇敬
鎌倉時代に入ると、源 頼朝は社参して願文を奉納し、黄金百両、神馬十頭を献じましたが、以後も武門の崇敬は続き、将軍足利義政、豊臣秀吉も神馬を献じました。
明治時代以降
明治になると、全国神社中第四位の序列をもって官幣大社に列せられ、政府が神職の任命や社殿の管理などを行う国の管轄となり、終戦後は、国家管理の廃止により、官幣大社の称号も用いないことになったことから、同名神社との混同を避けるために昭和25年に松尾大社と改称し現在に至っております。

大堰と用水路
また秦氏は保津峡を開削し、桂川に堤防を築き、今の「渡月橋」のやや少し上流には大きな堰(せき=大堰→大井と言う起源)を作り、その下流にも所々に水を堰き止めて、そこから水路を走らせ、桂川両岸の荒野を農耕地へと開発して行ったと伝えられております。 その水路を一ノ井・二ノ井などと称し、今現在も当社境内地を通っております。
酒造神
農業が進むと次第に他の諸産業も興り、絹織物なども盛んに作られるようになったようです。 酒造については秦一族の特技とされ、桂川に堤防を築き、秦氏に「酒」のという字の付いた人が多かったことからも酒造との関わり合いが推察できます。室町時代末期以降、松尾社が「日本第一酒造神」と仰がれ給う由来はここにあります。

脇勧請
赤鳥居の上部に柱と柱を結ぶ注連縄(しめなわ)があり、榊の小枝を束ねたものが数多く垂れ下っています。これは「脇勧請」と称されるもので、榊の束数は平年は12本、閏年は13本吊り下げる慣わしとなっています。
この形は『鳥居』の原始形式を示すもので、太古の昔、参道の両側に二本の木を植えて神を迎え、柱と柱の間に縄を張り、その年の月数だけの細縄を垂れて、月々の農作物の出来具合を占ったとされています。現在では、詳しい資料なども現存せずその占いの方法や仕方などはほとんどわかりませんが、占いによって月々の農作物などの吉凶を判断していた太古の風俗をそのまま伝えているので、民俗史学上も貴重な資料とされています。
尚、扁額は明治以後の官幣社として松尾大社になる以前の額で
「松尾大神」 となっています。
楼門
左右に随神を配置したこの楼門は江戸時代初期の作と言われております。この楼門の随神の周囲に張り巡らせた金網には、たくさんの杓子がさしてあります。よろずの願い事を記して掲げておけば救われると言う信仰に依るもので、祈願杓子とも言われます。

本殿は、大宝元年に、秦忌寸都理(はたのいみきとり)が勅命を奉じて創建以来、皇室や幕府の手で改築されてきました。
現在のものは室町初期(応永4年・1397)の再建ですが、桁行三間、梁間四間の特殊な両流造りで、松尾造りと称され、重要文化財に指定されています。向拝(ごはい)の斗組(ますぐみ)・蟇股(かえるまた)・手挟(たばさみ)などの優れた彫刻意匠は、中世の特色を遺憾なく発揮して います。

松尾山は、別雷山とも称し、松尾社は、この松尾山の遥拝場であったと伝わります。現在、社務所の裏の渓流を御手洗川と称し、涸れることのない霊亀の滝がかかり、傍には延命長寿、よみがえりの水として知られる「亀の井」と呼ばれる霊泉があります。酒造家はこの水を酒の元水として造り水に混和するのだとか。
この渓谷の北に続く大杉谷の頂上には、巨岩の露頭する「磐座」と呼ばれる屏風状の自然岩盤があり、社殿祭祀以前に古代神の祀られていた処です。この谷には霊亀の伝説があります。 奈良の平城京に都が遷されて数年、元正天皇の頃(西暦七一四年=和銅七年八月)、この谷から八寸ほどの白い亀が現れました。「首に三台(三つの星)を戴き、背には七星、前足に離の卦を顕わし、後足に一支あり、尾に緑毛・金色毛が混ざる」(続日本紀)といったもの。 この当時の人々は、珍しい白色の動物たちを尊んだようです。この亀を朝廷に奉納した所、元正帝は「嘉瑞なり」と、ことのほか喜悦に及び、『和銅』から『霊亀』へと元号を改めた(翌七一五年)ほどです。後に亀は再び、降臨の地とされる、この大杉谷に放たれたました。
称徳天皇が道鏡禅師や吉備真備らと政界に君臨した時代にも、武蔵国久良郡から白い雉、参河国から白い烏、日向国から鬣と尾の白い青馬、美作国から白い鼠、伊勢国からは白い鳩と献上があいつぎました。大瑞、祥瑞などと言われ、その見返りとして、破格の官位や姓、賜物が与えられたり、租税の免除などもなされていたようです。
松尾山は、別雷山とも称し、松尾社は、この松尾山の遥拝場であったと伝わります。現在、社務所の裏の渓流を御手洗川と称し、涸れることのない霊亀の滝がかかり、傍には延命長寿、よみがえりの水として知られる「亀の井」と呼ばれる霊泉があります。酒造家はこの水を酒の元水として造り水に混和するのだとか。

松風苑の三庭
神社後方の松尾山々中頂上近くにある磐座で祭祀が営まれており、この古代祭祀の場である磐座を模して造られた「上古の庭」、四方どちらからみても八方美の姿「曲水の庭」、全体が羽を広げた鶴を形どっており、池泉の周囲を巡り池に浮かぶ島々を 表現した「蓬莱の庭」の三つの庭があります。いずれも昭和の造園家・重森三玲の力作です。
上古の庭の奥には、山の斜面に「紫陽花苑」が広がっています。

境外摂社・月読神社
かつては、例祭が勅祭と定められ(『続日本紀』)、延喜6年には最高位となる正一位の神階を受けている(『扶桑略記』)。延喜式神名帳では「葛野坐月読神社」と記載され、名神大社に列している。天慶4年(942年)には神宮号の宣下を受けた。歴史も古く、高い格式を持つ独立の神社であった。
御祭神は月読尊。 境内には聖徳太子社・御船社・月延石があります。 月延石は安産石とも称し、神功皇后が腹を撫でて安産せられた石を、月読尊の神託により、舒明天皇が使いを筑紫に遣わして求め、この社に奉納したという伝説(雍州府志)があり、「妊婦がこの石をまたぐと安産になる」との言い伝えから、古来安産の霊験を慕ってお参りされる人が多い神社です。
2012年03月21日
お釈迦様の生き写しの仏像がある寺 清凉寺
清凉寺境内でも梅が満開でした。
清凉寺は、嵯峨にある浄土宗の寺院で、山号を五台山と称します。嵯峨釈迦堂といった方が、みなさんご存知かもしれませんね。中世以来「融通念仏の道場」としても知られています。宗派は初め南都六宗のひとつの華厳宗、後に浄土宗となりました。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は奝然(ちょうねん)、開山(初代住職)はその弟子の盛算(じょうさん)です。

この地にはもともと、嵯峨天皇の皇子・左大臣源融(みなもとのとおる)の別荘・栖霞観(せいかかん)がありました。源氏物語に光源氏が造営した「嵯峨のお堂」は、大覚寺の南に所在したとあり、栖霞観の場所と一致します。源融が紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる所以です。

浄土宗は通常は阿弥陀如来を本尊とするのですが、釈迦如来がご本尊なのにはいわれがあります。
北インドの釈迦族の王として生まれたゴータマシッタルダは37歳で悟りを開き、お釈迦樣となったと言われます。その時古代インドの王様が栴檀(せんだん)の木で一体の生き写しの釈迦像を造らせました。その後、三世紀から四世紀に掛けて、インド仏教が衰退し、釈迦像は追われるようにシルクロードを通って中国長安に運ばれ、中国大陸を転々としました。
北宋の時代、日本から中国に渡り、五台山(一名、清凉山)を巡礼した東大寺出身の僧・奝然(ちょうねん)がこの仏像に出会います。生き写しの仏像に魅入られた奝然は、この釈迦像を仏師に模刻させました。これが「三国伝来の釈迦像」です。
奝然は、日本に帰国後、京都の愛宕山を中国の五台山に見立て、愛宕山麓にこの釈迦像を安置する寺を建立しようとしました。これは、「都の西北方にそびえる愛宕山麓の地に南都仏教の拠点となる清凉寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとした」と言われています。しかし、その願いを達しないまま奝然は没します。遺志を継いだ弟子の盛算(じょうさん)が棲霞寺の境内に建立したのが、現在の五台山清凉寺なのです。
一方、中国にあった本物の仏像の方は、その後行方がわからなくなってしまい、インドで造られたお釈迦様の像を直接模刻した像はこの清凉寺の像だけとなりました。
通常の釈迦像との違いは、髪がらほつでなく、長い髪の毛を編んでぐるぐる巻いてあり、日本の袈裟と違って全身を衣で被っています。どちらかというとガンダーラの石仏に近いお姿ですね。
さて、昭和の時代になって、この像の胎内からは、造像にまつわる文書、奝然の遺品、仏教版画などの「納入品」が発見されました。これらも像とともに国宝に指定されています。中でも「五臓六腑」(絹製の内臓の模型)は、世界最古の人体模型として、医学史の資料としても注目されています。

境内には何故か豊臣秀頼の首塚があります。住職さんにお伺いすると、昭和55年に大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の首と見られる頭蓋骨が発見され、秀頼ゆかりの嵯峨清涼寺では、首塚を造って納め、368年ぶりに安らかな眠りにつかせることになったといいます。この頭蓋骨は、20~25歳の若武者で、首に介錯の跡があり、左耳が不自由だったこと、発掘当時、頭蓋骨の周囲にシジミやタニシの生貝が敷かれ、人為的に埋葬されていること、出土品などから、大阪夏の陣と時期が合致し、豊臣秀頼の首と断定されたといいます。
さて、この地は、平安時代に閻魔大王に仕えたとされる小野篁が六道珍皇寺の井戸から地獄に入り、出てきた場所とされる福生寺の跡地でもあり、生の六道と言われます。境内には福生寺跡の石碑があります。
清凉寺は、嵯峨にある浄土宗の寺院で、山号を五台山と称します。嵯峨釈迦堂といった方が、みなさんご存知かもしれませんね。中世以来「融通念仏の道場」としても知られています。宗派は初め南都六宗のひとつの華厳宗、後に浄土宗となりました。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は奝然(ちょうねん)、開山(初代住職)はその弟子の盛算(じょうさん)です。

この地にはもともと、嵯峨天皇の皇子・左大臣源融(みなもとのとおる)の別荘・栖霞観(せいかかん)がありました。源氏物語に光源氏が造営した「嵯峨のお堂」は、大覚寺の南に所在したとあり、栖霞観の場所と一致します。源融が紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる所以です。

浄土宗は通常は阿弥陀如来を本尊とするのですが、釈迦如来がご本尊なのにはいわれがあります。
北インドの釈迦族の王として生まれたゴータマシッタルダは37歳で悟りを開き、お釈迦樣となったと言われます。その時古代インドの王様が栴檀(せんだん)の木で一体の生き写しの釈迦像を造らせました。その後、三世紀から四世紀に掛けて、インド仏教が衰退し、釈迦像は追われるようにシルクロードを通って中国長安に運ばれ、中国大陸を転々としました。
北宋の時代、日本から中国に渡り、五台山(一名、清凉山)を巡礼した東大寺出身の僧・奝然(ちょうねん)がこの仏像に出会います。生き写しの仏像に魅入られた奝然は、この釈迦像を仏師に模刻させました。これが「三国伝来の釈迦像」です。
奝然は、日本に帰国後、京都の愛宕山を中国の五台山に見立て、愛宕山麓にこの釈迦像を安置する寺を建立しようとしました。これは、「都の西北方にそびえる愛宕山麓の地に南都仏教の拠点となる清凉寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとした」と言われています。しかし、その願いを達しないまま奝然は没します。遺志を継いだ弟子の盛算(じょうさん)が棲霞寺の境内に建立したのが、現在の五台山清凉寺なのです。
一方、中国にあった本物の仏像の方は、その後行方がわからなくなってしまい、インドで造られたお釈迦様の像を直接模刻した像はこの清凉寺の像だけとなりました。
通常の釈迦像との違いは、髪がらほつでなく、長い髪の毛を編んでぐるぐる巻いてあり、日本の袈裟と違って全身を衣で被っています。どちらかというとガンダーラの石仏に近いお姿ですね。
さて、昭和の時代になって、この像の胎内からは、造像にまつわる文書、奝然の遺品、仏教版画などの「納入品」が発見されました。これらも像とともに国宝に指定されています。中でも「五臓六腑」(絹製の内臓の模型)は、世界最古の人体模型として、医学史の資料としても注目されています。

境内には何故か豊臣秀頼の首塚があります。住職さんにお伺いすると、昭和55年に大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の首と見られる頭蓋骨が発見され、秀頼ゆかりの嵯峨清涼寺では、首塚を造って納め、368年ぶりに安らかな眠りにつかせることになったといいます。この頭蓋骨は、20~25歳の若武者で、首に介錯の跡があり、左耳が不自由だったこと、発掘当時、頭蓋骨の周囲にシジミやタニシの生貝が敷かれ、人為的に埋葬されていること、出土品などから、大阪夏の陣と時期が合致し、豊臣秀頼の首と断定されたといいます。
さて、この地は、平安時代に閻魔大王に仕えたとされる小野篁が六道珍皇寺の井戸から地獄に入り、出てきた場所とされる福生寺の跡地でもあり、生の六道と言われます。境内には福生寺跡の石碑があります。
2012年03月20日
観光ドライバーのための京都観光案内マニュアル 仁和寺
仁和寺の歴史は仁和2年(886年)光孝天皇によって「西山御願寺」と称する一寺の建立を発願したことに始まる。しかし翌年、光孝天皇は志半ばにして崩御、宇多天皇が先帝の遺志を継ぎ、仁和4年(888年)に完成。寺号も元号から仁和寺となった。
宇多天皇が譲位後に出家し、仁和寺第一世 宇多法皇となってから、寺内に「室」即ち僧坊を建て住いとする事で「御室御所」と呼ばれ、寺の付近までもが御室と地名にされた。

その後、皇室出身者が仁和寺の代々門跡(住職)を務め、平安〜鎌倉期には門跡寺院として最高の格式を保った。応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱で、仁和寺は一山のほとんどを兵火で焼失するという悲運に見舞われた。本尊の阿弥陀三尊をはじめ什物、聖教などは仁和寺の院家であった真光院に移され、法燈とともに伝えられてきた。
二王門 重要文化財
仁和寺の正面に建つ巨大な門。高さは18.7mで重層、入母屋造、本瓦葺。門正面の左右に阿吽の二王像(金剛力士像)、後面には唐獅子像を安置する。同時期に建立された知恩院三門、南禅寺三門が禅宗様の三門であったのに対し、平安時代の伝統を引く和様で統一されている。
阿吽(あうん)とは「あ」から始まって「ん」で終わる。宇宙の始まりと終わり、生と死を表すとされる。

暴れん坊将軍 III のエンディングに使われたり、必殺仕事人V激闘編で生臭大僧正が住持する寺として使われた。また、沢村一樹さん扮する浅見光彦シリーズのロケでも良く使われたりする。
寺名に元号を配すのは、寺院の中でも最高の格式とされる。仁和寺以外には京都でも延暦寺、建仁寺しか例がない。
また門跡寺院とは、代々皇室(親王など)か摂関家の者が法主を務める習わしとなっている格式の高い寺院である。
白書院
宸殿南庭の西側に建立。襖絵などは、昭和の画家・福永晴帆(1883〜1861)画伯による松の絵が部屋全体に描かれている。
南庭
宸殿の南側にあることから南庭と呼ばれている。庭内には左近の桜、右近の橘が植えられ、その前方に白砂と松や杉を配した、簡素の中にも趣のある庭が広がる。
勅使門
大正期に竣工。檜皮葺屋根の四脚唐門で前後を唐破風、左右の屋根を入母屋造としている。鳳凰の尾羽根や牡丹唐草、宝相華唐草文様や幾何学紋様など。
勅使は天皇の代理としての資格を以って宣旨を伝達する 。勅使を受け入れる施設や宿場、寺社には勅使専用の部屋や門が造られ、現在でも勅使の間、勅使門として残されているところがある。
左近の桜、右近の橘
平安京以降、天皇が政務を取る紫宸殿の前には、当初、左近の梅、右近の橘が植えられていた。奈良時代から平安初期にかけては大陸文化の影響もあって、花といえば梅が主流だったから。橘は中国古来より不老長寿の実といわれる。大覚寺などは今でも左近の梅である。
何故、植えられているのかと言えば、私財を投げ打って平安京を築いた秦河勝の邸宅が大内裏とされ、そこに植えられていたとの説、秦氏と賀茂別氏の名残だとの説などもある。
桜に変わったのは、左近の梅が枯れたとき、仁明天皇が桜好きだった嵯峨上皇を偲んで桜へ植替えたという説や藤原氏初の太政大臣である藤原良房が、承和の変で思惑どうり道康親王(文徳天皇)を皇太子としたとき、氏の威力を内外へ知らしめるために桜へ変えさせたという説などがある。
旧皇居の建物が下賜された宸殿や神宮などの本殿の前には左近の桜、右近の橘が植えられていることが多い。

宸殿
儀式や式典に使用される御殿の中心建物で、寛永年間に御所から下賜された常御殿がその役割を果たしていたが、明治期に焼失。現在は大正期に竣工されたもの。御所の紫宸殿と同様に檜皮葺、入母屋造。
内部は三室からなり、襖絵や壁などの絵は全て原在中(1849〜1916)の手によるもので、四季の風物をはじめ、牡丹・雁などが見事に描かれている。
掛け軸の人物は、宇多法皇である。ちなみに天皇が譲位して引退すると上皇となり院と呼ばれる。上皇が出家すると法皇となる。ちなみに、暴れん坊将軍などで北側の縁先を江戸城御廊下として使う例が多い 。

宸殿から写す北庭、飛濤亭(ひとうてい)、五重の塔
この景観が仁和寺で一番人気のビュースポットだ。宸殿の北側にあることから北庭と呼ばれ、南庭とは対照的な池泉式の雅な庭園。斜面を利用した滝組に池泉を配し、築山に飛濤亭、その奥には中門や五重塔を望む事が出来る。庭の制作年は不明だが、元禄3年(1690年)には加来道意ら、明治〜大正期には七代目小川治兵衛によって整備され現在に至る。
霊明殿
宸殿の北東にみえる霊明殿は、仁和寺の院家の本尊・薬師如来坐像を安置する為に明治44年に建立。正面に須弥壇を置き、小組の格天井をはじめ、蟇股の組物などの細部に至るまで見事な建築。正面上に掲げられた扁額は近衛文麿の筆である。

錦の御旗
御室仁和寺は明治維新においても大きな役目を果たす。仁和寺の第三十世門跡、最後の法親王である純仁法親王は、慶応三(1867)年の王政復古とともに還俗し、仁和寺宮嘉彰親王となり軍事総裁に就いた。
翌年の伏見鳥羽の戦いが起こるや征討大将軍になり、仁和寺の霊明殿須弥壇前の水引をもって錦の御旗を作り出陣した。この錦旗の威力は大変なもので、この旗を押し立てた薩長軍は官軍となり、会津・桑名藩を中心とする幕府軍を一方的に破った。
桧皮拭
宸殿から霊明殿に向かう渡り廊下で、まじかに桧皮葺(ひわだぶき)の様子が伺える。桧皮葺とは、ヒノキの樹皮を用いて施工する日本古来から伝わる伝統的手法で、世界に類を見ない日本独自の屋根工法 である。
御殿出口付近のお土産コーナーでは、井上真央さん主演の映画にもなった青木琴美さんの人気漫画「僕の初恋を君に捧ぐ」。この仁和寺で、修学旅行に来た逞と繭が買ったクローバーの幸福お守りが実際に売ってある。
原作漫画家の青木琴美さんの色紙展示も見逃せない。

中門(Cyumon) 重要文化財
二王門と金堂の中間に位置し、五重塔や観音堂といった伽藍中心部に向かう入口ともいえる門。切妻造・本瓦葺・柱間三間の八脚門で、側面の妻部には二重虹梁蟇股が飾られています。また、向かって左側に西方天、右側に東方天を安置します。

晩春になると「わたしゃお多福 御室の桜(花)鼻も低いが 人も好く」と詠まれて親しまれてきた遅咲きの御室桜が境内の桜苑を埋め尽くします。
中門前の参道も有名なロケ地だ。暴れん坊将軍で、豪気な商人がお参りの際襲われたり、勅使門の前あたりから徳田新之助が駆けつける。必殺仕事人などでもよく見かけた。映画千年の恋 ひかる源氏物語では、中宮・定子が宮中へ参内する行列が描かれ、見送る彰子と紫式部は勅使門の前に控えている。 といった具合だ。
五重塔 重要文化財
寛永21年(1644年)建立。塔身32.7m、総高36.18m。東寺の五重塔と同様に、上層から下層にかけて各層の屋根の大きさにあまり差がないので、下に立つと塔が自分に迫ってくるようで圧倒される。初重西側には、大日如来を示す梵字の額が懸けられる。
塔内部には大日如来、その周りに無量寿如来など四方仏が安置される。中央に心柱、心柱を囲むように四本の天柱が塔を支え、その柱や壁面には真言八祖や仏をはじめ、菊花文様などが細部にまで描かれている。

九所明神 重要文化財
仁和寺の伽藍を守る社。社殿は本殿・左殿・右殿の三棟あり、八幡三神を本殿に、東側の左殿には賀茂上下・日吉・武答・稲荷を、西側の右殿には松尾・平野・小日吉・木野嶋の計九座の明神を祀る。
実はここがロケの一番多い場所。「暴れん坊将軍」「鬼平犯科帳」「大奥」と悪者から逃げてきた娘が社の前で一息ついていると、塀の向こうからならず者が笑いながら現れる。あるときは人目を避けて怪しげな取引が行われる。お庭番や忍者がツナギをとっているのもよく見かける。ほどよく褐色した玉垣、ちょうどいい感じの織部灯籠、まるで時代劇のためにセットしてくれたかのような場所なのである。 メイド刑事では、若槻葵役の福田紗紀ちゃんが走り抜けたシーンもあった。

金堂(Kondo) 国宝
仁和寺の本尊である阿弥陀三尊を安置する御堂。慶長年間に徳川家光によって造営された御所・内裏紫宸殿を寛永年間(1624〜43)に移築したものである。
現存する最古の紫宸殿であり、当時の宮殿建築を伝える建築物として、国宝に指定されている。堂内は四天王像や梵天像も安置され、壁面には浄土図や観音図などが極彩色で描かれている。
ところで、真言宗の本尊では通常、大日如来がまつられるが、ここは本尊が阿弥陀如来となっているのが珍しい。宇多法皇が入寺当初、相当な浄土信仰が広まっていたと考えられている。

御影堂 重要文化財
鐘楼の西に位置し弘法大師像、宇多法皇像、仁和寺第2世性信親王像を安置している。御影堂は、慶長年間造営の内裏 清涼殿の一部を賜り、寛永年間に再建されたもので、蔀戸の金具なども清涼殿のものを利用している。
約10m四方の小堂ですが、檜皮葺を用いた外観は、弘法大師が住まう落ち着いた仏堂といえる。

2011年09月02日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル(高台寺)
高台寺は、東山霊山(りょうぜん)の山麓、八坂法観寺の東北にある。 臨済宗建仁寺派。山号は鷲峰山。正しくは高台寿聖禅寺、本尊は釈迦如来である。北政所所持と伝えられる蒔絵調度類を多数蔵することから「蒔絵の寺」の通称がある。
高台寺は豊臣秀吉の正妻である北の政所・ねね(ねい、おねとも言われる)が豊臣秀吉の供養のため、またねね自身の隠棲の場所として、秀吉の眠る阿弥陀が峰(豊国神社)の近くに創建された。寺名は、北政所が後陽成天皇に贈られた院号・高台院湖月尼に因む。 当初、開山は、弓箴善疆(きゅうしんぜんきょう)とし、曹洞宗の寺だったが、高台院(ねね)が没する年に、建仁寺の三江紹益和尚を開山としてむかえ、寺を託したといわれる。宗派争いの末に、臨済宗建仁寺派に改宗した。
ちなみに北の政所とは、関白の正妻に対する称号だが、このねねの存在によって広く知られるところとなった。当時の政治的事情から徳川家康の多大な援助により、伏見城から移築した施設があまた存在した。
1830年、京都大地震により庫裏が倒壊。1863年、公武合体派の福井藩主・松平慶永(春嶽)の宿所となり、倒幕派浪士により放火され、化粧御殿、大方丈、小方丈などが焼失した。近代、神仏分離令後の廃仏毀釈により、さらに寺は荒廃してしまった。 その後再建され今日に至る。
近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿、方丈などを焼失。創建時の建造物で現存しているのは、三江紹益を祀る開山堂、秀吉と北政所を祀る霊屋(おたまや)、茶室の傘亭と時雨亭などである。重要文化財の霊屋・表門・観月台・傘亭・時雨亭 は伏見城の遺構である。
駐車場は霊山観音の前が高台寺と共通。一時間500円。ちなみに清水寺参拝でも駐車できる。

山門(さんもん、表門)は、桃山時代に建立された、切妻造り・本瓦葺きの三間薬医門である。国の重要文化財に指定されている。
方丈(仏事の建物)
庫裏の右手に建つ。大正元年(1912年)の再建。創建当初の方丈は文禄の役後に伏見城の建物を移築したものであった。
方丈の南正面に位置する勅使門 もまた、大正元年(1912年)に方丈とともに再建された。
方丈庭園は江戸初期、小堀遠州作である。春には見事な枝垂れ桜が庭園の枯山水を覆う。

遺芳庵と鬼瓦席
共に灰屋紹益と吉野太夫との好みの茶席であり、高台寺を代表する茶席として知られている。

庭園は、開山堂の臥龍池、西の偃月池を中心として展開されており、小堀遠州の作によるもので、国の史跡・名勝に指定されている。偃月池には、秀吉遺愛の観月台を配し、北に亀島、南の岬に鶴島を造り、その石組みの見事さは桃山時代を代表する庭園として知られている。

観月台
豊臣秀吉の隠居のために建てられた伏見城から、移築されてきたもののひとつ。檜皮葺きの四本柱の建物であり、三方に唐破風(からはふ)をつけた屋根の下から月を見あげるためとも、池に映る月を見るための建物とも言われる。
北政所が御霊屋に向かう途中で、亡き秀吉を偲んで月を見上げたと言われる処である。
ちなみに唐破風とは中央部を凸形に、両端部を凹形の曲線状にした破風。玄関や門、神社の向拝などに用いられる。

開山堂
創建当初からある施設の一つである。入母屋造本瓦葺きの禅宗様の仏堂で、慶長10年(1605年)の建築。元来、北政所の持仏堂だったもので、その後、中興開山の建仁寺の三江紹益禅師の木像を祀る堂となっている。
堂内は中央奥に三江紹益禅師像、下はその墓所となっている。向かって右に北政所の兄の木下家定とその妻・雲照院の像、左に高台寺の普請に尽力した堀直政の木像を安置している。
徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったといわれる。
秀吉の御座船の天井
小組格天井といい、格子の中をさらに格子で組んだもの。船の天井一つにも贅を尽くした秀吉の性の一端がうかがえる。

ねねの御所車天井
飾り気のない秋の草花で色取られている。ねねの人柄かとも。

臥龍(がりょう)廊
婉曲した屋根が伏せた竜の曲線を思わせるところからきている。臥龍廊を昇りきるとお霊屋へと続く。
毎日、秀吉の菩提を弔うため、お霊屋に向かう天下人の妻、ねねが雨に濡れないようにとの配慮だとか。

御霊屋 宝形造檜皮葺きの堂 。創建当初からある貴重な施設。
桃山建築の傑作といわれ、その軒下は木組みと金色に輝く金具が添えられている。
須弥壇中央の厨子に本尊。本尊は秀吉の念じ物であったとされる大随求菩薩である。万能ですべての願いを叶えるとされている。いかにも秀吉らしい。周りを一センチほどの地蔵が千体奉られている。
うるしに金粉の蒔絵で飾られる高台寺蒔絵は、桃山美術の頂点とも言われる鮮やかな色彩を放つ。勾欄、柱、床板等は琴、琵琶、鼓などの楽器づくし、階段には花筏(はないかだ)が描かれる。当時は蒔絵=日本と言われたほど知られた芸術品であったと言われる。

右に秀吉の坐像。左に片膝立のねねの木像が安置されている。
秀吉像の厨子扉には、太閤桐と露をやどしたすすきが描かれる。裏は菊、楓。秀吉の辞世の句「つゆと落ち、つゆと消えにし我が身かな、難波のことも夢のまた夢」を意識しているのか。

ねねの方の厨子扉は表裏共に松、篠竹に桐紋を配している 。
須弥壇の二メートル下がねね本人の墓所となっている。

御霊屋からさらに進むと、伏見城から移築された傘亭がある。わびの風情をかもし出す建築。
水辺に建てられていた茶室で、小船がそのまま入れるように工夫されている。竹で放射状に天井が築かれる。

傘亭と渡り廊下でつながれて時雨(しぐれ)亭がある。傘にかかるしぐれ (秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨) を表している。
二階が茶室となっており、昔は開け放たれた窓から南西に、淀川もうかがえ、遠く「ちぬの海」(大阪湾)までをも見渡せたという。
大坂夏の陣の折、この空から、ねねは燃え上がる大坂城炎上を見つめていたといわれる。
傘亭、時雨亭ともに、秀吉が隠居のために建てたとされる伏見城の遺構である。

圓徳院
豊臣秀吉の没後、その妻北政所ねねは「高台院」の号を勅賜されたのを機縁に高台寺建立を発願し、慶長10(1605)年、秀吉との思い出深い伏見城の化粧御殿とその前庭を山内に移築して移り住んだ。それ以来、大名、禅僧、茶人、歌人、画家、陶芸家等多くの文化人が、北政所を慕って訪れたと伝えられている。ねねは77歳で没するまで19年間この地で余生を送った。
そのねねを支えていたのが、兄の木下家定とその次男の利房である。圓徳院は利房の手により、高台寺の三江和尚を開基に、木下家の菩提寺として開かれ、高台寺の塔頭とされた。
方丈には、長谷川等伯の山水図がある。唐紙の紋様である太閤桐をふりしきる雪に見立てて描かれた。桐紋などを散らした唐紙に絵は描かないのが通例だが、この襖絵はすべて桐紋襖の上に描かれた非常に珍しいもの。大徳寺の塔頭・三玄院の住職春屋宗園に襖絵制作を常々懇願しながら許されなかった等伯が、ある日、住職が2か月の旅に出かけて留守であることを知り、客殿に駆け上がり、腕を振るって水墨を乱点し、一気に描きあげてしまったものだと伝えられている。
北庭は、伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したという豪胆な庭。御殿は失われたが庭だけが残った。


長屋門
敵から攻められた場合すみやかに侍たちが守りにつくため、門に侍長屋がつながっているという、寺には存在しない形式である。
唐門
門の形状として製作に非常に技術を必要とし、その分貴人を迎えるにふさわしい形式とされている。上半が凸、下半が凹の反転する曲線になる破風(はふ)を唐破風といい、この唐破風のつけられた門を総称して唐門と呼ぶ。入ってすぐ右に秀吉好みの手水鉢がある。秀吉が西尾家に世話になった礼とし贈ったもの。後に西尾家から圓徳院に寄贈された。
桧垣の手水鉢
宝塔の笠を利用し、笠石を横にして、その面を凹字形に切り取り手水鉢としたものである。笠石は室町時代の作と考えられている。


三面大黒天は、大黒天、毘沙門天、弁財天の三つの顔を持った大変めずらしい仏である。
(中略)
この三面大黒天にも秀吉の合理性が表れているところがあります。三面なので一回拝めば三つの効き目があるのですから、実に合理的で秀吉らしい信仰です。大名になる前、秀吉はずーっと三面大黒天を信仰していました。
秀吉は、三面大黒天を信仰したから出世したのでしょうか。いいえそれは違います。三つの顔を一回で拝む、という合理性を持っていたから出世できたのです。仏教は合理的です。
(後藤典生『こころ惑うときに』より)

高台寺は豊臣秀吉の正妻である北の政所・ねね(ねい、おねとも言われる)が豊臣秀吉の供養のため、またねね自身の隠棲の場所として、秀吉の眠る阿弥陀が峰(豊国神社)の近くに創建された。寺名は、北政所が後陽成天皇に贈られた院号・高台院湖月尼に因む。 当初、開山は、弓箴善疆(きゅうしんぜんきょう)とし、曹洞宗の寺だったが、高台院(ねね)が没する年に、建仁寺の三江紹益和尚を開山としてむかえ、寺を託したといわれる。宗派争いの末に、臨済宗建仁寺派に改宗した。
ちなみに北の政所とは、関白の正妻に対する称号だが、このねねの存在によって広く知られるところとなった。当時の政治的事情から徳川家康の多大な援助により、伏見城から移築した施設があまた存在した。
1830年、京都大地震により庫裏が倒壊。1863年、公武合体派の福井藩主・松平慶永(春嶽)の宿所となり、倒幕派浪士により放火され、化粧御殿、大方丈、小方丈などが焼失した。近代、神仏分離令後の廃仏毀釈により、さらに寺は荒廃してしまった。 その後再建され今日に至る。
近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿、方丈などを焼失。創建時の建造物で現存しているのは、三江紹益を祀る開山堂、秀吉と北政所を祀る霊屋(おたまや)、茶室の傘亭と時雨亭などである。重要文化財の霊屋・表門・観月台・傘亭・時雨亭 は伏見城の遺構である。
駐車場は霊山観音の前が高台寺と共通。一時間500円。ちなみに清水寺参拝でも駐車できる。

山門(さんもん、表門)は、桃山時代に建立された、切妻造り・本瓦葺きの三間薬医門である。国の重要文化財に指定されている。
方丈(仏事の建物)
庫裏の右手に建つ。大正元年(1912年)の再建。創建当初の方丈は文禄の役後に伏見城の建物を移築したものであった。
方丈の南正面に位置する勅使門 もまた、大正元年(1912年)に方丈とともに再建された。
方丈庭園は江戸初期、小堀遠州作である。春には見事な枝垂れ桜が庭園の枯山水を覆う。

遺芳庵と鬼瓦席
共に灰屋紹益と吉野太夫との好みの茶席であり、高台寺を代表する茶席として知られている。

庭園は、開山堂の臥龍池、西の偃月池を中心として展開されており、小堀遠州の作によるもので、国の史跡・名勝に指定されている。偃月池には、秀吉遺愛の観月台を配し、北に亀島、南の岬に鶴島を造り、その石組みの見事さは桃山時代を代表する庭園として知られている。

観月台
豊臣秀吉の隠居のために建てられた伏見城から、移築されてきたもののひとつ。檜皮葺きの四本柱の建物であり、三方に唐破風(からはふ)をつけた屋根の下から月を見あげるためとも、池に映る月を見るための建物とも言われる。
北政所が御霊屋に向かう途中で、亡き秀吉を偲んで月を見上げたと言われる処である。
ちなみに唐破風とは中央部を凸形に、両端部を凹形の曲線状にした破風。玄関や門、神社の向拝などに用いられる。

開山堂
創建当初からある施設の一つである。入母屋造本瓦葺きの禅宗様の仏堂で、慶長10年(1605年)の建築。元来、北政所の持仏堂だったもので、その後、中興開山の建仁寺の三江紹益禅師の木像を祀る堂となっている。
堂内は中央奥に三江紹益禅師像、下はその墓所となっている。向かって右に北政所の兄の木下家定とその妻・雲照院の像、左に高台寺の普請に尽力した堀直政の木像を安置している。
徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったといわれる。
秀吉の御座船の天井
小組格天井といい、格子の中をさらに格子で組んだもの。船の天井一つにも贅を尽くした秀吉の性の一端がうかがえる。

ねねの御所車天井
飾り気のない秋の草花で色取られている。ねねの人柄かとも。

臥龍(がりょう)廊
婉曲した屋根が伏せた竜の曲線を思わせるところからきている。臥龍廊を昇りきるとお霊屋へと続く。
毎日、秀吉の菩提を弔うため、お霊屋に向かう天下人の妻、ねねが雨に濡れないようにとの配慮だとか。

御霊屋 宝形造檜皮葺きの堂 。創建当初からある貴重な施設。
桃山建築の傑作といわれ、その軒下は木組みと金色に輝く金具が添えられている。
須弥壇中央の厨子に本尊。本尊は秀吉の念じ物であったとされる大随求菩薩である。万能ですべての願いを叶えるとされている。いかにも秀吉らしい。周りを一センチほどの地蔵が千体奉られている。
うるしに金粉の蒔絵で飾られる高台寺蒔絵は、桃山美術の頂点とも言われる鮮やかな色彩を放つ。勾欄、柱、床板等は琴、琵琶、鼓などの楽器づくし、階段には花筏(はないかだ)が描かれる。当時は蒔絵=日本と言われたほど知られた芸術品であったと言われる。

右に秀吉の坐像。左に片膝立のねねの木像が安置されている。
秀吉像の厨子扉には、太閤桐と露をやどしたすすきが描かれる。裏は菊、楓。秀吉の辞世の句「つゆと落ち、つゆと消えにし我が身かな、難波のことも夢のまた夢」を意識しているのか。

ねねの方の厨子扉は表裏共に松、篠竹に桐紋を配している 。
須弥壇の二メートル下がねね本人の墓所となっている。

御霊屋からさらに進むと、伏見城から移築された傘亭がある。わびの風情をかもし出す建築。
水辺に建てられていた茶室で、小船がそのまま入れるように工夫されている。竹で放射状に天井が築かれる。
傘亭と渡り廊下でつながれて時雨(しぐれ)亭がある。傘にかかるしぐれ (秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨) を表している。
二階が茶室となっており、昔は開け放たれた窓から南西に、淀川もうかがえ、遠く「ちぬの海」(大阪湾)までをも見渡せたという。
大坂夏の陣の折、この空から、ねねは燃え上がる大坂城炎上を見つめていたといわれる。
傘亭、時雨亭ともに、秀吉が隠居のために建てたとされる伏見城の遺構である。

圓徳院
豊臣秀吉の没後、その妻北政所ねねは「高台院」の号を勅賜されたのを機縁に高台寺建立を発願し、慶長10(1605)年、秀吉との思い出深い伏見城の化粧御殿とその前庭を山内に移築して移り住んだ。それ以来、大名、禅僧、茶人、歌人、画家、陶芸家等多くの文化人が、北政所を慕って訪れたと伝えられている。ねねは77歳で没するまで19年間この地で余生を送った。
そのねねを支えていたのが、兄の木下家定とその次男の利房である。圓徳院は利房の手により、高台寺の三江和尚を開基に、木下家の菩提寺として開かれ、高台寺の塔頭とされた。
方丈には、長谷川等伯の山水図がある。唐紙の紋様である太閤桐をふりしきる雪に見立てて描かれた。桐紋などを散らした唐紙に絵は描かないのが通例だが、この襖絵はすべて桐紋襖の上に描かれた非常に珍しいもの。大徳寺の塔頭・三玄院の住職春屋宗園に襖絵制作を常々懇願しながら許されなかった等伯が、ある日、住職が2か月の旅に出かけて留守であることを知り、客殿に駆け上がり、腕を振るって水墨を乱点し、一気に描きあげてしまったものだと伝えられている。
北庭は、伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したという豪胆な庭。御殿は失われたが庭だけが残った。


長屋門
敵から攻められた場合すみやかに侍たちが守りにつくため、門に侍長屋がつながっているという、寺には存在しない形式である。
唐門
門の形状として製作に非常に技術を必要とし、その分貴人を迎えるにふさわしい形式とされている。上半が凸、下半が凹の反転する曲線になる破風(はふ)を唐破風といい、この唐破風のつけられた門を総称して唐門と呼ぶ。入ってすぐ右に秀吉好みの手水鉢がある。秀吉が西尾家に世話になった礼とし贈ったもの。後に西尾家から圓徳院に寄贈された。
桧垣の手水鉢
宝塔の笠を利用し、笠石を横にして、その面を凹字形に切り取り手水鉢としたものである。笠石は室町時代の作と考えられている。

三面大黒天は、大黒天、毘沙門天、弁財天の三つの顔を持った大変めずらしい仏である。
(中略)
この三面大黒天にも秀吉の合理性が表れているところがあります。三面なので一回拝めば三つの効き目があるのですから、実に合理的で秀吉らしい信仰です。大名になる前、秀吉はずーっと三面大黒天を信仰していました。
秀吉は、三面大黒天を信仰したから出世したのでしょうか。いいえそれは違います。三つの顔を一回で拝む、という合理性を持っていたから出世できたのです。仏教は合理的です。
(後藤典生『こころ惑うときに』より)

2011年07月28日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・東寺
1994年に世界文化遺産に登録された東寺、正式名称は教王護国寺という。教王とは王を教化するとの意味であり、教王護国寺という名称には、国家鎮護の密教寺院という意味合いが込められている。山号は八幡山、本尊は薬師如来。 創建からおよそ1200年余、唯一残る平安京の遺構である。鳴くよウグイスの794年に長岡京より遷都された平安京とともに建立された官寺、つまりは国立の寺院である。
桓武天皇は、権力を持ち過ぎた南都六宗(法相、倶舎、三論、成実、律、華厳・ほっぐ、さんじょう、りつ、けごん)と言われた平城京からの寺院の移転を認めなかった。当初、平安京の南の玄関である羅城門(現在、旧千本九条の北側に公園となり、石碑だけが残る)を挟んで東に東寺、西に西寺が建立された。両寺は左右対称の伽藍配置をとり、東西255m、南北515mの広大な敷地に、金堂、講堂、食堂(じきどう)、五重塔などの諸堂が立ち並んでいた。 その後、西寺は衰退し消滅、東寺だけが今日に引き継がれた。東寺は平安時代と同じ場所に、当時とほぼ変わらない伽藍配置で佇んでいる。
嵯峨天皇の時代になって東寺は、唐において真言密教の奥義を習得してきた空海・弘法大師に与えられ、教王護国寺となり、五重塔を始め、さらに伽藍が整備され、日本で初めての真言密教根本道場としての道を歩むことになる。

まずは周囲をぐるりと廻ってみよう。
東寺の西側、壬生通り沿いに「蓮花門」(鎌倉時代)が建つ。境内からこの門を見ることはできない 。東寺の六つの門(南大門、北大門、北総門、東大門、慶賀門、蓮花門)の内、唯一国宝の指定を受けている。天平の様式を残しつつ、内部は組入天井である 。
何故西大門と言わずに「蓮花門」というか。

永く東寺に伝わる伝説から来ている。空海59歳の年、高野山の金堂が完成する。空海は自らの死期を悟り、 東寺を弟子の真雅に託し、高野山に入定するために旅立った。
空海がまさに門を出ようとしたとき、自らの念持仏として西院にまつっていた不動明王が見送りにきた。不動明王の目からは、いまにも涙がこぼれ落ちそうであった。その時、空海の足元から蓮華の花が咲き誇っていたという。以来、この門は「蓮花門」といわれている。

東寺の一番絵になるスポットは?
京阪国道口にかかる歩道橋がある。東西を走る九条通り(九条大路)が平安京の最南端だった。 交差点の北東角にあたる歩道橋の階段を上った踊り場から五重塔と南大門がセットできれいに映える。ここが一番絵になるスポットだ。テレビや映画のロケなどにも良く使われる。
実は「この踊り場で五重の塔を背景に写真を撮影したカップルは必ず結ばれる」などと言う噂も飛び交っている。

南大門は、東寺に現存する門の中で最大の門。楼門に仁王像が安置された南大門は、明治元年(1868)の廃仏毀釈の際に焼け落ち、東寺創建1100年の明治28年(1895)蓮華王院(三十三間堂)の西門を移築した八脚門である。そういう訳で仁王像はない。東寺の中では珍しく、桃山様式によるきらびやかな装飾をたくさん見ることができる。
南大門は唯一平安京の地図作成時の定点となっていることでも知られる。この門をくぐると、金堂の正面になるのだが、駐車場が東大門の北側なのでそちらに廻ろう。

方四町の敷地を有する東寺の外側を延々と囲む「大土塀」は内側に傾いて、どっしりとした重厚感がある。かの司馬遼太郎に「大好きなのは御影堂と大土塀」と言わせた重要文化財である。
激動の建武の親政から室町時代の始まりの時期。持明院統・北朝の光厳上皇、光明天皇を奉じた足利尊氏が、比叡山に陣する大覚寺統・南朝の後醍醐天皇と対決するために京都に入ったとき、尊氏はこの東寺に本陣を築いた。四方を囲む築地の大土塀は正に城壁であったのだ。境内には馬がつながれ、鎧姿の数千人の軍兵であふれ返ったと伝わる。
光厳上皇の御所は境内の西院小子房に、足利尊氏は千手観音菩薩が安置されている食堂(じきどう)に身を置いた。
また応仁の乱で播磨の赤松勢が京都に入った際、織田信長の入京の折にも、この東寺を城砦としている。

東大門(とうだいもん)を何故
「不開門(あけずもん)」というか?
東大門(とうだいもん)は、創建年代は不明だが、現在の東大門は鎌倉時代前期の1198年(建久9年)に文覚上人によって再建された八脚門である。国の重要文化財に指定されている。
前述の争乱の折り、建武3年(1336年)に南朝方の軍勢が東寺に陣する足利尊氏を攻めた。糺の森、賀茂川、桂川、六条大宮などでの激しい攻防戦の末、尊氏は東寺に退却する。新田義貞率いる二万の軍勢が大宮通りから、名和長年率いる軍勢も猪熊通りから東寺に迫る。痛手を負った足利軍の武者たちが東大門に流れ込む。
尊氏は最後の軍勢が入った途端にこの門を閉め、危うく難を逃れた。それ以来、この門は「不開門(あけずのもん)」と呼ばれている。東大門には、その時の戦闘の凄まじさを物語る、敵方から打ち込まれた何筋もの矢の痕が、今も残されている。この後、尊氏は形成を逆転、北朝方を勝利に導き、後に室町幕府が開かれるのだ。
この故事から東大門は「あかずの門」ではなく「あけずの門」なのである。
1605年(慶長10年)には豊臣秀頼(とよとみ ひでより)が大修理を行ったと伝えられる。

宝物館は春期(3月20日~5月25日)、秋季(9月20日~11月25日)に特別公開される。
元は食堂の御本尊だった千手観音菩薩。高さ6メートル弱、千本の手が光背のように覆っていた。1930年に食堂が火災に見舞われるまで千年ものあいだ、東寺の観音様として信仰を集めていた。

四天王の中の北方の護法神である多聞天は、独尊では毘沙門天と呼ばれて信仰される。都を外敵から守る神として羅城門の二階に奉られていたという兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)は、このうち地天女の両手に支えられて立ち、二鬼(尼藍婆・にらんば、毘藍婆・びらんば )を従える姿で表された特殊な像の名称である。

この他に西寺にあったという地蔵菩薩、愛染明王、頬笑みを浮かべる如来三尊、足利尊氏寄進の梵鐘などが展示されている。

鎌倉時代の建立で国の重要文化財の北総門から北大門の間の通りを櫛笥小路(くしげこうじ)というが、平安時代以来そのままの幅で残っている唯一の小路である。
この通りの東側に観智院がある。観智院は真言宗の観学院、大学の研究室のようなところ。春季などに特別公開される。
東寺の三宝のうち、杲宝が観智院を創建し、賢宝が智慧(ちえ)の仏である五大虚空蔵菩薩を本尊として安置した。保管されている密教の文書類は一万五千件以上に及ぶ。
国宝の客殿は、江戸時代初期の建築で、唐破風付の車寄せや押板の床の間などに中世の様式を残しながら、柱の間隔を畳割りで決めるなどの書院造への移行の様子もうかがえる貴重な建造物である。
羅城の間、暗の間、使者の間からなり、上段の間には宮本武蔵筆の「鷲の図」と「竹林の図」が描かれている。五大の庭は、空海が唐からの帰朝の際に、海難を逃れた様子が表され、築山の石は五大虚空蔵菩薩を表現し、各々の凡字が描かれている。

本尊の五大虚空蔵菩薩像(重要文化財)は唐の長安・青龍寺金堂の本尊であったものを平安時代の847年に請来したものだ。
五体はそれぞれ、蓮の花弁で象られた蓮台の上に結跏趺坐(けっかふざ・跏は足の裏、趺は足の甲の意。釈迦が悟りを開いた時の坐法という。両足の甲をそれぞれ反対のももの上にのせて押さえる形の座り方) し、獅子、象、馬、孔雀、金翅鳥の上に鎮座している。山科の安祥寺より請来して本尊とした。
金翅鳥(こんじちょう)とは迦楼羅(かるら)の別名である。迦楼羅天(かるらてん)とは、インド神話のガルーダを前身とする。後には二十八部衆となった。 翼は金色で、口から火を吐き、竜を好んで食う といわれる。本堂の北側に茶室、楓泉観がある。
 東寺発行絵葉書より
東寺発行絵葉書より
食堂と書いてじきどうと読む。文字通り僧たちが食事をするところだが、仏教では食事もまた修行の一環である。
東寺の食堂はかつて、高さ六メートルの千手観音菩薩(焼損後、宝物館に安置)が祀られていたことから、観音堂とも呼ばれている。東寺に陣した足利尊氏が生活していたこともある。
現在は、四国八十八ヶ所巡礼や洛陽三十三所観音霊場の納経所ともなっている。建物は、1930年に焼失後の再建である。
昭和に再建の十一面観音菩薩立像が本尊である。周りを焼損したものの修復された平安期の四天王像が守護している。全身炭化し、顔の表情も定かではない焼け爛れた四天王像であるが凄みがある。

境内の北西、築地で囲まれた一角が、弘法大師空海の住坊跡であり、国宝の御影堂である。空海は東寺を密教寺院として造り上げるため、ここで、講堂の立体曼陀羅を構想し、伽藍造営の指揮をとったと言われている。
南北朝時代の入母屋造り、桧皮葺、後堂、前堂、中堂からなり、建具には蔀戸(しとみど)、妻戸、縁には高欄を巡らす落ちつきのある建物である。弘法大師空海の念持物だった不動明王が奉られているが絶対秘仏である。
毎朝、6時に空海が住していた頃と同じように、一の膳、二の膳、お茶を供える生身供(しょうじんく)が行われている。近隣の人たちが座り、手を合わす姿は生活の中に根ざした信仰の風景だ。

蔀戸(しとみど)は、細かい格子組に板を張ってつくられた。後の格子戸の原型ともいえる。日光を遮り風雨を防ぐためのもので、常時は建て込まれ、閉じていて、開けるためには内部、または外部にはね上げを吊金具に引っかけて固定する。 下1枚を欠き壁とし、上1枚のみのものを半蔀(はじとみ)という。
また妻戸とは、寝殿造りで、殿舎の四隅に設けた両開きの板扉のことである。
高欄とは、宮殿,寺院などの回り縁,橋の両側,須弥(しゅみ)壇の周囲など,人が落ちないよう,また意匠的美観から設ける手すり。三段の横木からなり,柱頭に擬宝珠(ぎぼし)をつけたものを擬宝珠高欄,すみに擬宝珠がなく端部の先端をはね出したのを刎(はね)高欄と呼ぶ。

境内の大伽藍が建っているエリアは、東西南北255メートルで、ほぼ正方形になっている。その中心が講堂である。そして講堂の中心、寺域のちょうど中心に位置する大日如来、それは、宇宙の中心とされた。密教の教えを分かりやすく伝えるため、空海が生涯をかけて建立した講堂は空海入定の年に完成した。空海は講堂の完成をみることはなかった。焼失後、今の建物は室町時代の再建である。
仏教の教え、宇宙観を分かりやすく絵にしたらどうなるか、密教では、「曼陀羅(まんだら)」として表現する。講堂には、普通は絵画として表現される曼荼羅を、より体感できるよう立体表現した世界が広がっている。曼陀羅から飛び出した仏たち、これを「立体曼荼羅」or「羯磨(かつま)曼荼羅」という。曼陀羅は梵語(ぼんご)で「本質を有するもの」という意味がある。空海は密教教学を駆使して、東寺講堂の須弥壇に二十一尊の仏を配置し、日本で初めて羯摩曼陀羅を誕生させた。 そして、寺域の中心に大日如来を安置し、境内全体を曼陀羅にレイアウトしたのだ。
大日如来を中心に五智如来。五智如来に対面して右側に、金剛波羅密多菩薩を中心にした五大菩薩、左側に日本に初めて紹介された不動明王を中心にした五大明王。須弥壇の四方には四天王、梵天、帝釈天と六尊の守護神が如来、菩薩、明王たちを警護するように配されている。火災消失・地震倒壊などにより、中央の五仏(重要文化財)及び、菩薩の中心である金剛波羅蜜多菩薩の計六体は後補されたが、他十五体は全て平安前期を代表する国宝である。



仏教では、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天、声聞(しょうもん)、縁覚(えんがく)、菩薩、如来の十界と解釈される。
「天」は人間と仏の間に存在する。帝釈天、梵天、四天王、この天たちは、居並ぶ仏たちがつくりだす仏法の世界を守護しているのだ。 会社でいえば係長クラスといったところだろうか?
東方の 持国天(じこくてん)、西方の 広目天(こうもくてん)、南方の 増長天(ぞうちょうてん)、北方の 多聞天(たもんてん)の四天王はインド古代の神であったものが、仏教に取り込まれたとされている。(とんなんしゃぺ・持増広多)
これに、インド古代神話の創造主ブラフマンが元になったとされる 梵天(ぼんてん)と、 戦闘の神インドラが元になったとされる 帝釈天(たいしゃくてん)を加えた六尊で天部が構成され、密教世界の守りを固めているという。平安時代の像で国宝である。
「天」はサンスクリット語(梵語)で「超人的な力を持つ神」を意味する。


明王は、忿怒(ふんぬ)の形相、右手に宝剣、左手に羂索(けんさく・縄)、下唇を上歯でかみ、真っ赤な火焔を背負う。何本もの手や足、いくつもの目を向いた四尊の明王が、我が国最古の不動明王を囲む。平安時代の像ですべて国宝である。
不動明王は大日如来の化身とされ、 悪魔を降伏するために恐ろしい姿ですべての障害を打ち砕き、 おとなしく仏道に従わないものを無理矢理にでも導き救済するという役目を 持つという。 常に火焔の中にあって、その燃えさかる炎であらゆる障害と一切の悪を焼き尽くすのだ。 会社でいえば課長さんクラスといったところだろうか?
梵名の「アチャラ」は「動かない」、「ナータ」は「守護者」を意味し、全体としては「揺るぎなき守護者」の意味である
明王の剣は諸刃の剣、刃が外に向き、内に向いている。命がけで人を救おうとしているとされる。

菩薩の話
おだやかな表情をした、仏の教えを実践し、悟りを求める(如来に成ろうとする)修業者の姿が菩薩である。母親が子供に対して無償の愛情を注ぐ、見返りのない、その心が菩薩の心だと言われる。
修業中ではあるが、人々と共に歩み、教えに導くということで、庶民の信仰の対象となっていった 。
東寺では、金剛波羅蜜多菩薩を中心にした五大菩薩である。会社でいえば部長クラスといったところだ。
金剛波羅蜜多菩薩、金剛薩埵菩薩、金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩の組み合わせを五大菩薩として安置した例は他になく、金剛頂経(密教の根本経典の1つ)、仁王経(仏教による国家鎮護を説いた経)などをもとに空海が独自に発案したものとも言われる。

如来の話
講堂の中心に位置するのが、大日如来である。いっさいのものを大日如来の智慧で包み込む智拳印を結ぶ。大日如来は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる。胎蔵曼荼羅、金剛界曼荼羅の中心におかれ、そこから全ての仏が生まれていくという。
東寺では、周りを阿閦(あしゅく)如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来が囲む。これが五智如来だ。
如来は悟りを得た状態を表す、そのため服装は簡素である。しかし、大日如来だけ、菩薩のように宝冠をかぶり着飾っている。ある時は、菩薩となり人々を導き、ある時は不動明王となり命がけで救う、積極的な姿である。菩薩も明王もすべての仏は大日如来の化身とされる。
如来たちは会社でいえば、会長、社長と役員会といったところだろうか。

金堂は東寺の本堂である。平安時代の始め、東寺が創建され、初めに工事が始まったのが金堂だった。室町期に焼失し、現在の建物は関ヶ原の合戦以後の建立である。
本尊は薬師如来、脇侍は、左が月光菩薩、右が日光菩薩である。これを薬師三尊という。
薬師如来は、来世の西方極楽浄土の阿弥陀如来に対して、人々にとっては出生を司った過去の東方浄瑠璃世界の教主である。その名の通り医薬を司る仏で、あらゆる病から人々をすくい、安楽を与える仏とされる。このため仏像もしばしば薬壷を持ち、 瑠璃光を以て衆生の病気を治すとされている。
薬師如来がお医者さんなら日光菩薩は昼勤の看護師さん、月光菩薩は夜勤の看護師さんといったところだろうか。
但し、東寺の薬師如来は薬壺(やっこ)を持たない古い様式の仏像で、光背に七体の化仏を配する七仏薬師如来である。
薬師如来の台座には、如来を守り、如来の願いを叶える十二神将がぐるりと取り巻いている。この様式は奈良時代のものと言われる。焼失後の現在の薬師三尊は桃山時代を代表する大仏師・康正により復興された。

空海は国によって計画された伽藍配置をほぼ踏襲しながら、それを使って、密教の教えを映し出す巨大な空間を描いていった。
子院を除いた境内は、東西二百五十五m、南北二百八十五mのほぼ正方形である。その中心に講堂、さらに中心に大日如来が設置されている。
さらに、南大門から北へ金堂、講堂、食堂が一直線に並ぶ。
これは三宝(さんぽう)を表すとされる。三宝とは、仏教における三つの宝物を指し、具体的には仏・法・僧(僧伽)のこと。この三宝に帰依することで仏教徒とされる。仏を求め、真理を知り、実践していく過程を表しているのだ。
金堂本尊の薬師如来もこの線上に配置される。南東の隅に仏舎利塔としての五重塔、南西の隅に密教寺院にとって最重要の潅頂院(かんじょういん)を配す。空海は、密教教学を駆使して、東寺を、曼荼羅に描かれたような宇宙空間として造り上げたのだ。
心身の病を持つ人間が最初に出会うのが金堂の薬師如来、そして病苦を縁として講堂で普遍的な真理、立体曼陀羅と出会う。さらに生活の場でそれを生かすために食堂が置かれている。食堂までの距離が離れているのは、仏の教えを生活の場に生かすまでにかかる時間の経過を表しているという。
国宝五重塔は京都のランドマークタワー的存在になっている。高さ54.8メートルで木造の塔としては日本一の高さを誇る。
826年、空海により、創建着手にはじまるが、勧進が進まず、また御神木事件に揺れ、完成には五十年の歳月を要した。雷火や不審火で4回焼失しており、現在の塔は5代目で、寛永21年(1644年)、徳川家光の寄進で建てられたものである。
五重塔は仏陀の遺骨を安置するストゥーパーが起源とされ、東寺のものも、空海が唐より持ち帰った仏舎利を安置する。
初重内部の壁や柱には両界曼荼羅や真言八祖像を描き、須弥壇には心柱を大日如来に見立て中心とする。だからここに大日如来の姿は無い。周りに金剛界四如来と八大菩薩像を安置する。
「真言八祖像」とは、真言密教の開祖龍猛から龍智・善無畏・一行・金剛智・丈空・恵果と我が国に真言密教を伝えた空海までの八祖を八幅(8枚)一組の画像としたもの。真言の教えが空海に伝わるまでの歴史を表している。

軒下に目をやると尾垂木の上に邪鬼(じゃき)の彫刻がある。
初重の四隅に、ちょうど尾垂木の上で軒を支えるような格好で置かれている。
邪鬼とは仏教では押さえ込まれる存在としてあらわされる。よく四天王が踏みつけているのも邪鬼である。身近な邪鬼では天邪鬼(あまのじゃく)がある。「人に反発する、反対のことをする」といった意味で使われる。
大工たちは邪鬼のこの性格を利用して、屋根を支える束の代わりにこれを置いた。反発する邪鬼の力を利用して屋根を支えようとしたのだ。邪鬼達は必死の形相で軒を支えている。

桓武天皇は、権力を持ち過ぎた南都六宗(法相、倶舎、三論、成実、律、華厳・ほっぐ、さんじょう、りつ、けごん)と言われた平城京からの寺院の移転を認めなかった。当初、平安京の南の玄関である羅城門(現在、旧千本九条の北側に公園となり、石碑だけが残る)を挟んで東に東寺、西に西寺が建立された。両寺は左右対称の伽藍配置をとり、東西255m、南北515mの広大な敷地に、金堂、講堂、食堂(じきどう)、五重塔などの諸堂が立ち並んでいた。 その後、西寺は衰退し消滅、東寺だけが今日に引き継がれた。東寺は平安時代と同じ場所に、当時とほぼ変わらない伽藍配置で佇んでいる。
嵯峨天皇の時代になって東寺は、唐において真言密教の奥義を習得してきた空海・弘法大師に与えられ、教王護国寺となり、五重塔を始め、さらに伽藍が整備され、日本で初めての真言密教根本道場としての道を歩むことになる。

まずは周囲をぐるりと廻ってみよう。
東寺の西側、壬生通り沿いに「蓮花門」(鎌倉時代)が建つ。境内からこの門を見ることはできない 。東寺の六つの門(南大門、北大門、北総門、東大門、慶賀門、蓮花門)の内、唯一国宝の指定を受けている。天平の様式を残しつつ、内部は組入天井である 。
何故西大門と言わずに「蓮花門」というか。

永く東寺に伝わる伝説から来ている。空海59歳の年、高野山の金堂が完成する。空海は自らの死期を悟り、 東寺を弟子の真雅に託し、高野山に入定するために旅立った。
空海がまさに門を出ようとしたとき、自らの念持仏として西院にまつっていた不動明王が見送りにきた。不動明王の目からは、いまにも涙がこぼれ落ちそうであった。その時、空海の足元から蓮華の花が咲き誇っていたという。以来、この門は「蓮花門」といわれている。

東寺の一番絵になるスポットは?
京阪国道口にかかる歩道橋がある。東西を走る九条通り(九条大路)が平安京の最南端だった。 交差点の北東角にあたる歩道橋の階段を上った踊り場から五重塔と南大門がセットできれいに映える。ここが一番絵になるスポットだ。テレビや映画のロケなどにも良く使われる。
実は「この踊り場で五重の塔を背景に写真を撮影したカップルは必ず結ばれる」などと言う噂も飛び交っている。

南大門は、東寺に現存する門の中で最大の門。楼門に仁王像が安置された南大門は、明治元年(1868)の廃仏毀釈の際に焼け落ち、東寺創建1100年の明治28年(1895)蓮華王院(三十三間堂)の西門を移築した八脚門である。そういう訳で仁王像はない。東寺の中では珍しく、桃山様式によるきらびやかな装飾をたくさん見ることができる。
南大門は唯一平安京の地図作成時の定点となっていることでも知られる。この門をくぐると、金堂の正面になるのだが、駐車場が東大門の北側なのでそちらに廻ろう。

方四町の敷地を有する東寺の外側を延々と囲む「大土塀」は内側に傾いて、どっしりとした重厚感がある。かの司馬遼太郎に「大好きなのは御影堂と大土塀」と言わせた重要文化財である。
激動の建武の親政から室町時代の始まりの時期。持明院統・北朝の光厳上皇、光明天皇を奉じた足利尊氏が、比叡山に陣する大覚寺統・南朝の後醍醐天皇と対決するために京都に入ったとき、尊氏はこの東寺に本陣を築いた。四方を囲む築地の大土塀は正に城壁であったのだ。境内には馬がつながれ、鎧姿の数千人の軍兵であふれ返ったと伝わる。
光厳上皇の御所は境内の西院小子房に、足利尊氏は千手観音菩薩が安置されている食堂(じきどう)に身を置いた。
また応仁の乱で播磨の赤松勢が京都に入った際、織田信長の入京の折にも、この東寺を城砦としている。

東大門(とうだいもん)を何故
「不開門(あけずもん)」というか?
東大門(とうだいもん)は、創建年代は不明だが、現在の東大門は鎌倉時代前期の1198年(建久9年)に文覚上人によって再建された八脚門である。国の重要文化財に指定されている。
前述の争乱の折り、建武3年(1336年)に南朝方の軍勢が東寺に陣する足利尊氏を攻めた。糺の森、賀茂川、桂川、六条大宮などでの激しい攻防戦の末、尊氏は東寺に退却する。新田義貞率いる二万の軍勢が大宮通りから、名和長年率いる軍勢も猪熊通りから東寺に迫る。痛手を負った足利軍の武者たちが東大門に流れ込む。
尊氏は最後の軍勢が入った途端にこの門を閉め、危うく難を逃れた。それ以来、この門は「不開門(あけずのもん)」と呼ばれている。東大門には、その時の戦闘の凄まじさを物語る、敵方から打ち込まれた何筋もの矢の痕が、今も残されている。この後、尊氏は形成を逆転、北朝方を勝利に導き、後に室町幕府が開かれるのだ。
この故事から東大門は「あかずの門」ではなく「あけずの門」なのである。
1605年(慶長10年)には豊臣秀頼(とよとみ ひでより)が大修理を行ったと伝えられる。

宝物館は春期(3月20日~5月25日)、秋季(9月20日~11月25日)に特別公開される。
元は食堂の御本尊だった千手観音菩薩。高さ6メートル弱、千本の手が光背のように覆っていた。1930年に食堂が火災に見舞われるまで千年ものあいだ、東寺の観音様として信仰を集めていた。

四天王の中の北方の護法神である多聞天は、独尊では毘沙門天と呼ばれて信仰される。都を外敵から守る神として羅城門の二階に奉られていたという兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)は、このうち地天女の両手に支えられて立ち、二鬼(尼藍婆・にらんば、毘藍婆・びらんば )を従える姿で表された特殊な像の名称である。

この他に西寺にあったという地蔵菩薩、愛染明王、頬笑みを浮かべる如来三尊、足利尊氏寄進の梵鐘などが展示されている。

鎌倉時代の建立で国の重要文化財の北総門から北大門の間の通りを櫛笥小路(くしげこうじ)というが、平安時代以来そのままの幅で残っている唯一の小路である。
この通りの東側に観智院がある。観智院は真言宗の観学院、大学の研究室のようなところ。春季などに特別公開される。
東寺の三宝のうち、杲宝が観智院を創建し、賢宝が智慧(ちえ)の仏である五大虚空蔵菩薩を本尊として安置した。保管されている密教の文書類は一万五千件以上に及ぶ。
国宝の客殿は、江戸時代初期の建築で、唐破風付の車寄せや押板の床の間などに中世の様式を残しながら、柱の間隔を畳割りで決めるなどの書院造への移行の様子もうかがえる貴重な建造物である。
羅城の間、暗の間、使者の間からなり、上段の間には宮本武蔵筆の「鷲の図」と「竹林の図」が描かれている。五大の庭は、空海が唐からの帰朝の際に、海難を逃れた様子が表され、築山の石は五大虚空蔵菩薩を表現し、各々の凡字が描かれている。

本尊の五大虚空蔵菩薩像(重要文化財)は唐の長安・青龍寺金堂の本尊であったものを平安時代の847年に請来したものだ。
五体はそれぞれ、蓮の花弁で象られた蓮台の上に結跏趺坐(けっかふざ・跏は足の裏、趺は足の甲の意。釈迦が悟りを開いた時の坐法という。両足の甲をそれぞれ反対のももの上にのせて押さえる形の座り方) し、獅子、象、馬、孔雀、金翅鳥の上に鎮座している。山科の安祥寺より請来して本尊とした。
金翅鳥(こんじちょう)とは迦楼羅(かるら)の別名である。迦楼羅天(かるらてん)とは、インド神話のガルーダを前身とする。後には二十八部衆となった。 翼は金色で、口から火を吐き、竜を好んで食う といわれる。本堂の北側に茶室、楓泉観がある。
 東寺発行絵葉書より
東寺発行絵葉書より食堂と書いてじきどうと読む。文字通り僧たちが食事をするところだが、仏教では食事もまた修行の一環である。
東寺の食堂はかつて、高さ六メートルの千手観音菩薩(焼損後、宝物館に安置)が祀られていたことから、観音堂とも呼ばれている。東寺に陣した足利尊氏が生活していたこともある。
現在は、四国八十八ヶ所巡礼や洛陽三十三所観音霊場の納経所ともなっている。建物は、1930年に焼失後の再建である。
昭和に再建の十一面観音菩薩立像が本尊である。周りを焼損したものの修復された平安期の四天王像が守護している。全身炭化し、顔の表情も定かではない焼け爛れた四天王像であるが凄みがある。

境内の北西、築地で囲まれた一角が、弘法大師空海の住坊跡であり、国宝の御影堂である。空海は東寺を密教寺院として造り上げるため、ここで、講堂の立体曼陀羅を構想し、伽藍造営の指揮をとったと言われている。
南北朝時代の入母屋造り、桧皮葺、後堂、前堂、中堂からなり、建具には蔀戸(しとみど)、妻戸、縁には高欄を巡らす落ちつきのある建物である。弘法大師空海の念持物だった不動明王が奉られているが絶対秘仏である。
毎朝、6時に空海が住していた頃と同じように、一の膳、二の膳、お茶を供える生身供(しょうじんく)が行われている。近隣の人たちが座り、手を合わす姿は生活の中に根ざした信仰の風景だ。

蔀戸(しとみど)は、細かい格子組に板を張ってつくられた。後の格子戸の原型ともいえる。日光を遮り風雨を防ぐためのもので、常時は建て込まれ、閉じていて、開けるためには内部、または外部にはね上げを吊金具に引っかけて固定する。 下1枚を欠き壁とし、上1枚のみのものを半蔀(はじとみ)という。
また妻戸とは、寝殿造りで、殿舎の四隅に設けた両開きの板扉のことである。
高欄とは、宮殿,寺院などの回り縁,橋の両側,須弥(しゅみ)壇の周囲など,人が落ちないよう,また意匠的美観から設ける手すり。三段の横木からなり,柱頭に擬宝珠(ぎぼし)をつけたものを擬宝珠高欄,すみに擬宝珠がなく端部の先端をはね出したのを刎(はね)高欄と呼ぶ。

境内の大伽藍が建っているエリアは、東西南北255メートルで、ほぼ正方形になっている。その中心が講堂である。そして講堂の中心、寺域のちょうど中心に位置する大日如来、それは、宇宙の中心とされた。密教の教えを分かりやすく伝えるため、空海が生涯をかけて建立した講堂は空海入定の年に完成した。空海は講堂の完成をみることはなかった。焼失後、今の建物は室町時代の再建である。
仏教の教え、宇宙観を分かりやすく絵にしたらどうなるか、密教では、「曼陀羅(まんだら)」として表現する。講堂には、普通は絵画として表現される曼荼羅を、より体感できるよう立体表現した世界が広がっている。曼陀羅から飛び出した仏たち、これを「立体曼荼羅」or「羯磨(かつま)曼荼羅」という。曼陀羅は梵語(ぼんご)で「本質を有するもの」という意味がある。空海は密教教学を駆使して、東寺講堂の須弥壇に二十一尊の仏を配置し、日本で初めて羯摩曼陀羅を誕生させた。 そして、寺域の中心に大日如来を安置し、境内全体を曼陀羅にレイアウトしたのだ。
大日如来を中心に五智如来。五智如来に対面して右側に、金剛波羅密多菩薩を中心にした五大菩薩、左側に日本に初めて紹介された不動明王を中心にした五大明王。須弥壇の四方には四天王、梵天、帝釈天と六尊の守護神が如来、菩薩、明王たちを警護するように配されている。火災消失・地震倒壊などにより、中央の五仏(重要文化財)及び、菩薩の中心である金剛波羅蜜多菩薩の計六体は後補されたが、他十五体は全て平安前期を代表する国宝である。



仏教では、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天、声聞(しょうもん)、縁覚(えんがく)、菩薩、如来の十界と解釈される。
「天」は人間と仏の間に存在する。帝釈天、梵天、四天王、この天たちは、居並ぶ仏たちがつくりだす仏法の世界を守護しているのだ。 会社でいえば係長クラスといったところだろうか?
東方の 持国天(じこくてん)、西方の 広目天(こうもくてん)、南方の 増長天(ぞうちょうてん)、北方の 多聞天(たもんてん)の四天王はインド古代の神であったものが、仏教に取り込まれたとされている。(とんなんしゃぺ・持増広多)
これに、インド古代神話の創造主ブラフマンが元になったとされる 梵天(ぼんてん)と、 戦闘の神インドラが元になったとされる 帝釈天(たいしゃくてん)を加えた六尊で天部が構成され、密教世界の守りを固めているという。平安時代の像で国宝である。
「天」はサンスクリット語(梵語)で「超人的な力を持つ神」を意味する。


明王は、忿怒(ふんぬ)の形相、右手に宝剣、左手に羂索(けんさく・縄)、下唇を上歯でかみ、真っ赤な火焔を背負う。何本もの手や足、いくつもの目を向いた四尊の明王が、我が国最古の不動明王を囲む。平安時代の像ですべて国宝である。
不動明王は大日如来の化身とされ、 悪魔を降伏するために恐ろしい姿ですべての障害を打ち砕き、 おとなしく仏道に従わないものを無理矢理にでも導き救済するという役目を 持つという。 常に火焔の中にあって、その燃えさかる炎であらゆる障害と一切の悪を焼き尽くすのだ。 会社でいえば課長さんクラスといったところだろうか?
梵名の「アチャラ」は「動かない」、「ナータ」は「守護者」を意味し、全体としては「揺るぎなき守護者」の意味である
明王の剣は諸刃の剣、刃が外に向き、内に向いている。命がけで人を救おうとしているとされる。

菩薩の話
おだやかな表情をした、仏の教えを実践し、悟りを求める(如来に成ろうとする)修業者の姿が菩薩である。母親が子供に対して無償の愛情を注ぐ、見返りのない、その心が菩薩の心だと言われる。
修業中ではあるが、人々と共に歩み、教えに導くということで、庶民の信仰の対象となっていった 。
東寺では、金剛波羅蜜多菩薩を中心にした五大菩薩である。会社でいえば部長クラスといったところだ。
金剛波羅蜜多菩薩、金剛薩埵菩薩、金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩の組み合わせを五大菩薩として安置した例は他になく、金剛頂経(密教の根本経典の1つ)、仁王経(仏教による国家鎮護を説いた経)などをもとに空海が独自に発案したものとも言われる。

如来の話
講堂の中心に位置するのが、大日如来である。いっさいのものを大日如来の智慧で包み込む智拳印を結ぶ。大日如来は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる。胎蔵曼荼羅、金剛界曼荼羅の中心におかれ、そこから全ての仏が生まれていくという。
東寺では、周りを阿閦(あしゅく)如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来が囲む。これが五智如来だ。
如来は悟りを得た状態を表す、そのため服装は簡素である。しかし、大日如来だけ、菩薩のように宝冠をかぶり着飾っている。ある時は、菩薩となり人々を導き、ある時は不動明王となり命がけで救う、積極的な姿である。菩薩も明王もすべての仏は大日如来の化身とされる。
如来たちは会社でいえば、会長、社長と役員会といったところだろうか。

金堂は東寺の本堂である。平安時代の始め、東寺が創建され、初めに工事が始まったのが金堂だった。室町期に焼失し、現在の建物は関ヶ原の合戦以後の建立である。
本尊は薬師如来、脇侍は、左が月光菩薩、右が日光菩薩である。これを薬師三尊という。
薬師如来は、来世の西方極楽浄土の阿弥陀如来に対して、人々にとっては出生を司った過去の東方浄瑠璃世界の教主である。その名の通り医薬を司る仏で、あらゆる病から人々をすくい、安楽を与える仏とされる。このため仏像もしばしば薬壷を持ち、 瑠璃光を以て衆生の病気を治すとされている。
薬師如来がお医者さんなら日光菩薩は昼勤の看護師さん、月光菩薩は夜勤の看護師さんといったところだろうか。
但し、東寺の薬師如来は薬壺(やっこ)を持たない古い様式の仏像で、光背に七体の化仏を配する七仏薬師如来である。
薬師如来の台座には、如来を守り、如来の願いを叶える十二神将がぐるりと取り巻いている。この様式は奈良時代のものと言われる。焼失後の現在の薬師三尊は桃山時代を代表する大仏師・康正により復興された。

空海は国によって計画された伽藍配置をほぼ踏襲しながら、それを使って、密教の教えを映し出す巨大な空間を描いていった。
子院を除いた境内は、東西二百五十五m、南北二百八十五mのほぼ正方形である。その中心に講堂、さらに中心に大日如来が設置されている。
さらに、南大門から北へ金堂、講堂、食堂が一直線に並ぶ。
これは三宝(さんぽう)を表すとされる。三宝とは、仏教における三つの宝物を指し、具体的には仏・法・僧(僧伽)のこと。この三宝に帰依することで仏教徒とされる。仏を求め、真理を知り、実践していく過程を表しているのだ。
金堂本尊の薬師如来もこの線上に配置される。南東の隅に仏舎利塔としての五重塔、南西の隅に密教寺院にとって最重要の潅頂院(かんじょういん)を配す。空海は、密教教学を駆使して、東寺を、曼荼羅に描かれたような宇宙空間として造り上げたのだ。
心身の病を持つ人間が最初に出会うのが金堂の薬師如来、そして病苦を縁として講堂で普遍的な真理、立体曼陀羅と出会う。さらに生活の場でそれを生かすために食堂が置かれている。食堂までの距離が離れているのは、仏の教えを生活の場に生かすまでにかかる時間の経過を表しているという。
国宝五重塔は京都のランドマークタワー的存在になっている。高さ54.8メートルで木造の塔としては日本一の高さを誇る。
826年、空海により、創建着手にはじまるが、勧進が進まず、また御神木事件に揺れ、完成には五十年の歳月を要した。雷火や不審火で4回焼失しており、現在の塔は5代目で、寛永21年(1644年)、徳川家光の寄進で建てられたものである。
五重塔は仏陀の遺骨を安置するストゥーパーが起源とされ、東寺のものも、空海が唐より持ち帰った仏舎利を安置する。
初重内部の壁や柱には両界曼荼羅や真言八祖像を描き、須弥壇には心柱を大日如来に見立て中心とする。だからここに大日如来の姿は無い。周りに金剛界四如来と八大菩薩像を安置する。
「真言八祖像」とは、真言密教の開祖龍猛から龍智・善無畏・一行・金剛智・丈空・恵果と我が国に真言密教を伝えた空海までの八祖を八幅(8枚)一組の画像としたもの。真言の教えが空海に伝わるまでの歴史を表している。

軒下に目をやると尾垂木の上に邪鬼(じゃき)の彫刻がある。
初重の四隅に、ちょうど尾垂木の上で軒を支えるような格好で置かれている。
邪鬼とは仏教では押さえ込まれる存在としてあらわされる。よく四天王が踏みつけているのも邪鬼である。身近な邪鬼では天邪鬼(あまのじゃく)がある。「人に反発する、反対のことをする」といった意味で使われる。
大工たちは邪鬼のこの性格を利用して、屋根を支える束の代わりにこれを置いた。反発する邪鬼の力を利用して屋根を支えようとしたのだ。邪鬼達は必死の形相で軒を支えている。

2011年06月06日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル(初級編)二条城
京の都において徳川の威信を示すが如く二条城がそびえたったのは1626年(寛永三年)であった。本丸、二の丸、天守閣を備えた総面積8万3000坪、建物面積2200坪という大規模なものであったという。1601年(慶長六年)に徳川家康が、将軍上洛の際の居館として築城を命じ、三代将軍家光により、1624年から大改造が3年の歳月をかけて行われた。
京都御所を上回る規模、天守閣からは、広く京の都を一望でき、御所を見下ろす景観。正に徳川幕府の威光と権威で、まるで朝廷を威圧するかのようにそびえる二条城を、禁裏ではどのような思いで、見ていたのであろうか。また京童(きょうわらべ)たちの思いはいかなものであったろう。
家康が、ここに二条城構築を決める際重要視したのが、外濠・内掘の水であった。眼をつけたのが平安京の大内裏に隣接する禁苑・神泉苑だった。かつては、池の周囲に豪華な殿舎が設けられ、池に船を浮かべて管絃の宴を催したという。
後の祇園祭の起源となった御霊会も行われた。その聖地とも言える神泉苑の北側を家康が二条城に取り組んでしまったのである。当時の京都人の思いは複雑であったに違いない。町屋四、亓千軒が立ち退いた。
二条城の大改造が終わった1626年(寛永3)に、後水尾天皇始め、総勢千人に及ぶ一行が二条城に行幸した。先頭が二条城に入門した時も最後尾は、未だ御所の中だったと云われている。後水尾天皇は、寵愛していた御不津との間を幕府の手によって引き裂かれ、徳川二代将軍秀忠の亓女、東福門院和子(今話題の江姫の娘)を迎えた。かっての藤原氏や平氏と同様に、幕府が朝廷を操ろうとする意図も垣間見える。その怒りからか、この後の「紫衣事件」を端に、後水尾天皇は突然、明正天皇に譲佈してしまう。
寛永九年(1632年)に秀忠が亡くなり、名実ともに天下を掌握した家光は、それを誇示するように上洛を計画する。寛永十一年の上洛は、三十万七千人もの兵力を率いた壮大なもので、二条城を拠点に大規模な大名の領地替えや領地朱印状の発給などをおこない、家光の全国統治を印象づけた。しかし、これ以後十四代将軍家茂まで徳川将軍がこの城を訪れることはなかった。四代将軍以後は朝廷の勅使、院使を江戸城に呼びつける方式に変わっていくからである。
1867年(慶応3年)、十亓代将軍 徳川慶喜が、二条城の大広間で大政奉還を上表する。徳川幕府の象徴として、内裏の禁苑を取り込んで造られた二条城も、この時、徳川幕府終焉の舞台となった。
さらに明治元年には、太政官代が置かれ、明治天皇が二条城に行幸し、二の丸御殿の白書院で慶喜追討の詔が発せられた。家康の造った二条城で慶喜は「賊徒」となった。正に、二条城は江戸時代の始まりと終わりを看取った城なのである。
明治になると二条城は朝廷のものになるが、明治4年に京都府庁が置かれ、更に、明治17年には二条離宮(皇居とは別に設けられた宮殿)となる。元離宮二条城と言われるのは、この事実に由来する。明治26年には、本丸御殿の移築など大改修が行われている。「二条城」は国史跡に指定されており、現在、京都市の管理下にある。

余裕があれば駐車場に入る前にお城の廻りをぐるりと廻ってみよう。実は色んなものがあるのです。
堀川通りから竹屋町通りを西に入ると、すぐ南には冷泉院跡の石碑がひっそりと建っている。これは平安時代に嵯峨天皇が離宮として造営され、譲佈後は後院(上皇の御所)として使用された。

しばらく西に行くと見えてくるのが北門である。閉門されている。
竹屋町通りを突き当り美福通りを下がると西門にあたる埋門が見えてくる。非常時には、土砂などで埋めて塞ぐことを想定して構築された門 である。この門は大政奉還した慶喜ら徳川一門が最後に退去していった門として著名である。他の門と違い、厳重な造りとなっている。

東南隅櫓(とうなんすみやぐら)は、江戸時代初期に造られた二条城に残る隅櫓である。二重二階櫓、入母屋造、本瓦葺で、国の重要文化財に指定されている。元々は、城の四隅にそれぞれ造られたが、1788年(天明8年)の大火で東北隅櫓と西北隅櫓が焼失し、以後再建されること無く、現在はこの東南隅櫓と西南隅櫓の二つだけとなっている。
押小路通りの東西の端には、神泉苑端の石碑がある

二条城のお堀の鯉は味が良い?
二条城は東西に長く長方形を呈し、水を満々とたたえた外壕がめぐり、内側には高い土居が築かれている。堀川通り側から拝観券を買って、東大手門に至る橋を渡る。お堀には今も鯉たちの姿がうかがえる。
江戸時代の元禄三年(1690)に、長崎の出島にやってきた、ドイツ人医師・ケンペルが書いた『日本誌』には二条城のこととして……。「城廓は方形で……、石垣を築いて深い濠を囲らし……、四角い数層の高い櫓を築き、濠には味のよさそうな鯉が放魚されている。その晩われわれの通詞の許に、この濠の鯉が数尾届けられた」と記述している。果たしてお味はいかがだったのだろう。

東大手門は多聞櫓(城門を固める石塁の上に設置された長屋形式の櫓) がともなった堂々とした門構えである。これが正門といえる。棟には鯱(しゃち)が飾られている。重要文化財に指定されている。

門を入るとすぐ右手に番所がある、徳川将軍丌在の時の二条城は、二条在番と呼ばれる江戸から派遣された武士によって警備されていた。毎年2組(1組50人)が4月に交代して番にあたった。この番所はそうした詰め所の一つ 。現存する門番所の遺構は尐なく貴重な建物だ。ここで人の出入りがチェックされた。

現在は来場者も塀に沿って左側(南側)に迂回して、昔の貴人ルートから拝観できる。すぐにも勅使門が見えてくる。寛永年間に建立され、唐門とも呼ばれる。切妻造、桧皮葺の四脚門でその前後は唐破風造となっている。彫刻がふんだんに使われている。勅使門とは、朝廷の勅使(天皇が出す使者)が来城した時のみ開けられる門である。

唐門の上部桁と唐破風屋根の格天五との間にある欄間には、「牡丹に蝶と瑞雲」の欄間彫刻が4枚(前面と背面に2枚づつ)ある。透かし彫りだが、裏側に板があるので透けては見えない。蝶は青色に塗られている。

唐門南面の蟇股(かえるまた)と両脇に「鶴に大和松と亀と瑞雲」の極彩色彫刻がある。中央の蟇股(かえるまた)には「亀」が彫られ、亀の背には蓬莱山と思われる山が載せられている。蟇股の両脇には鶴が羽ばたいている。

唐門中央上部の欄間に「龍虎」の極彩色彫刻がある。
唐門北面の蟇股と両脇に「亀乗り仙人と鳳凰」の極彩色彫刻がある。巻物をもって亀の背に乗っているの仙人である。亀仙人として知られる黄安であろうと思われる。蟇股の両脇には鳳凰が配されている。

二の丸御殿
勅使門を入ると正面に二の丸御殿の出入り口、豪華な装飾の車寄せが見えてくる。牛車で入れるようになっている。
遠侍、式台、大広間、黒書院、白書院の各建物が雁行の形で配置されている。二の丸御殿は江戸時代初期の武家の邸宅の姿を今に伝える数すくない遺構である。当時は武家や公家の身分によって入れる部屋も決められていた。

遠侍(とおさむらい)の間
城へ参上した大名の控えの間である。二の間は、虎の間とも呼ばれていて狩野一門による虎と豹(ひょう)の絵(竹林群虎図)が描かれている。当時、日本に虎はいなかったため、毛皮を模写したと言われていて、虎にしては優しい顔立ちに描かれている。また豹は虎の雌と思われていた。つまりこの絵はカップルとして描かれているのである。
一の間は、慶長16年に家康が豊臣秀頼に会見した場所でもある。これ以後、豊臣家は徳川の臣下となったことが示された。

式台の間
参上した大名が老中とあいさつを交わした所。将軍への献上品はここで取次がれていた。「松の襖絵」は、狩野探幽25歳の傑作と言われる。
大広間
三の間は、外様大名の控えの間。 部屋の正面上にある欄間の彫刻は、厚さ35㎝の桧の1枚板を両面から、すべて手張りで透かし彫りしたもので、表と裏の彫刻が全く違うが、それでもお互いに邪魔になる部分が見えないという優れものである。
蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。
黒書院
三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。
二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。
白書院
将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。
大広間四の間
「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の
「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。
一の間・二の間
将軍に外様大名が面会したところ。将軍の座の横には十四畳の帱台構え(武者隠しの間)、違棚・床の間・附書院を備えている。このような部屋のつくりを、桃山時代の武家風書院造りという。襖絵は狩野探幽の作。この部屋で慶応3年10月、15代将軍慶喜は諸大名を集めて政権を天皇に還す大政奉還を
発表し、徳川幕府265年の幕を閉じ、鎌倉時代よりの武家政権は終わりを告げた。日本史の教科書に載っている「大政奉還の図」は、まさにこれである。 大広間一の間の天五 外様大名に対面した部屋で、最も豪華絢爛である。 天五は、四方がまるく折上がった「折上げ格天五」(ごうてんじょう)である。 一の間は中がもう一段折上がった「二重折上げ格天五」になっている。
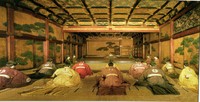
蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。
黒書院
三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。
二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。

白書院
将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。

大広間四の間
「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の
「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。
老中の間
徳川幕府の老中、今でいえば内閣といったところか。その老中職たちの執務室である。
板張り、塗り壁の質素な造りになっている。絵は、右から春夏秋冬の様子が描かれている。一・二の間は雁の間で、三の間は柳と鷺の絵で、狩野探幽と高弟の作といわれている。

勅使の間
遠侍の東北の一角になっている。 将軍が朝廷からの使者を迎える時の対面所でる。 青楓とひのきの襖絵は狩野眞設の作。
二条城では、将軍は下座に座った。江戸時代に将軍宣下が江戸城内で行われるようになると、勅使は下座に坐し、将軍が上座に坐すという変則が常態化した。しかしこれも幕末になると尊王思想の浸透により公武の権威がふたたび逆転、勅使が上座、将軍が下座となる。
鴬張りの廊下
二の丸御殿の廊下は、歩くと鴬(うぐいす)の鳴くような音が聞こえるために「鴬張りの廊下」と呼ばれる。夜間など侵入者があればすぐに分かる、一種の警報装置といえるものだ。 「目かすがい」といわれる、廊下の床板とそれを支える床下の根太の間に取り付けられた鉄製の鎹(かすがい、長さ約12㎝)が施されている。目かすがいには2個の釘穴があり、そこには鉄釘が打たれている。人が床板を踏むと、目かすがいが上下し、釘と擦れ合って鴬が鳴くような音がするのだ。
二の丸御殿を出て、庭園の方に向かうと二の丸庭園の向かい側、御殿の裏側で廊下の裏側が覗き込める。実際に目かすがいをみてみよう。

二の丸庭園
作庭の年代は二条城が造営されたと家康時代に、その建築に調和させて作庭されたものであるが、家光時代の御水尾天皇行幸のために一部改修を加えられたと考えられている。
書院造庭園である二の丸庭園は神泉蓬莱の世界を表した庭園と言われ、また「八陣の庭」とも呼ばれている。二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の 座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の为に三方向から鑑賞できるように設計されていたという。

二の丸庭園を出ると本丸への入口、櫓(やぐら)門がある。横から見ると櫓が2階建てになっているように見えるが、家光時代はこの橋の上に渡り廊下があって、身分の高い人は二の丸から本丸へ土を踏むことなく移動できた。
奥には本丸御殿、天为閣跡、清流園が広がっている。
本丸御殿は非公開となっている。都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の御殿を明治26年に移築したもので、皇女和宮が14代将軍家茂に嫁ぐ前に佊んでいた建物だそうだ。清流園は時々、特別公開される。
京都御所を上回る規模、天守閣からは、広く京の都を一望でき、御所を見下ろす景観。正に徳川幕府の威光と権威で、まるで朝廷を威圧するかのようにそびえる二条城を、禁裏ではどのような思いで、見ていたのであろうか。また京童(きょうわらべ)たちの思いはいかなものであったろう。
家康が、ここに二条城構築を決める際重要視したのが、外濠・内掘の水であった。眼をつけたのが平安京の大内裏に隣接する禁苑・神泉苑だった。かつては、池の周囲に豪華な殿舎が設けられ、池に船を浮かべて管絃の宴を催したという。
後の祇園祭の起源となった御霊会も行われた。その聖地とも言える神泉苑の北側を家康が二条城に取り組んでしまったのである。当時の京都人の思いは複雑であったに違いない。町屋四、亓千軒が立ち退いた。
二条城の大改造が終わった1626年(寛永3)に、後水尾天皇始め、総勢千人に及ぶ一行が二条城に行幸した。先頭が二条城に入門した時も最後尾は、未だ御所の中だったと云われている。後水尾天皇は、寵愛していた御不津との間を幕府の手によって引き裂かれ、徳川二代将軍秀忠の亓女、東福門院和子(今話題の江姫の娘)を迎えた。かっての藤原氏や平氏と同様に、幕府が朝廷を操ろうとする意図も垣間見える。その怒りからか、この後の「紫衣事件」を端に、後水尾天皇は突然、明正天皇に譲佈してしまう。
寛永九年(1632年)に秀忠が亡くなり、名実ともに天下を掌握した家光は、それを誇示するように上洛を計画する。寛永十一年の上洛は、三十万七千人もの兵力を率いた壮大なもので、二条城を拠点に大規模な大名の領地替えや領地朱印状の発給などをおこない、家光の全国統治を印象づけた。しかし、これ以後十四代将軍家茂まで徳川将軍がこの城を訪れることはなかった。四代将軍以後は朝廷の勅使、院使を江戸城に呼びつける方式に変わっていくからである。
1867年(慶応3年)、十亓代将軍 徳川慶喜が、二条城の大広間で大政奉還を上表する。徳川幕府の象徴として、内裏の禁苑を取り込んで造られた二条城も、この時、徳川幕府終焉の舞台となった。
さらに明治元年には、太政官代が置かれ、明治天皇が二条城に行幸し、二の丸御殿の白書院で慶喜追討の詔が発せられた。家康の造った二条城で慶喜は「賊徒」となった。正に、二条城は江戸時代の始まりと終わりを看取った城なのである。
明治になると二条城は朝廷のものになるが、明治4年に京都府庁が置かれ、更に、明治17年には二条離宮(皇居とは別に設けられた宮殿)となる。元離宮二条城と言われるのは、この事実に由来する。明治26年には、本丸御殿の移築など大改修が行われている。「二条城」は国史跡に指定されており、現在、京都市の管理下にある。
余裕があれば駐車場に入る前にお城の廻りをぐるりと廻ってみよう。実は色んなものがあるのです。
堀川通りから竹屋町通りを西に入ると、すぐ南には冷泉院跡の石碑がひっそりと建っている。これは平安時代に嵯峨天皇が離宮として造営され、譲佈後は後院(上皇の御所)として使用された。
しばらく西に行くと見えてくるのが北門である。閉門されている。
竹屋町通りを突き当り美福通りを下がると西門にあたる埋門が見えてくる。非常時には、土砂などで埋めて塞ぐことを想定して構築された門 である。この門は大政奉還した慶喜ら徳川一門が最後に退去していった門として著名である。他の門と違い、厳重な造りとなっている。
東南隅櫓(とうなんすみやぐら)は、江戸時代初期に造られた二条城に残る隅櫓である。二重二階櫓、入母屋造、本瓦葺で、国の重要文化財に指定されている。元々は、城の四隅にそれぞれ造られたが、1788年(天明8年)の大火で東北隅櫓と西北隅櫓が焼失し、以後再建されること無く、現在はこの東南隅櫓と西南隅櫓の二つだけとなっている。
押小路通りの東西の端には、神泉苑端の石碑がある

二条城のお堀の鯉は味が良い?
二条城は東西に長く長方形を呈し、水を満々とたたえた外壕がめぐり、内側には高い土居が築かれている。堀川通り側から拝観券を買って、東大手門に至る橋を渡る。お堀には今も鯉たちの姿がうかがえる。
江戸時代の元禄三年(1690)に、長崎の出島にやってきた、ドイツ人医師・ケンペルが書いた『日本誌』には二条城のこととして……。「城廓は方形で……、石垣を築いて深い濠を囲らし……、四角い数層の高い櫓を築き、濠には味のよさそうな鯉が放魚されている。その晩われわれの通詞の許に、この濠の鯉が数尾届けられた」と記述している。果たしてお味はいかがだったのだろう。
東大手門は多聞櫓(城門を固める石塁の上に設置された長屋形式の櫓) がともなった堂々とした門構えである。これが正門といえる。棟には鯱(しゃち)が飾られている。重要文化財に指定されている。
門を入るとすぐ右手に番所がある、徳川将軍丌在の時の二条城は、二条在番と呼ばれる江戸から派遣された武士によって警備されていた。毎年2組(1組50人)が4月に交代して番にあたった。この番所はそうした詰め所の一つ 。現存する門番所の遺構は尐なく貴重な建物だ。ここで人の出入りがチェックされた。
現在は来場者も塀に沿って左側(南側)に迂回して、昔の貴人ルートから拝観できる。すぐにも勅使門が見えてくる。寛永年間に建立され、唐門とも呼ばれる。切妻造、桧皮葺の四脚門でその前後は唐破風造となっている。彫刻がふんだんに使われている。勅使門とは、朝廷の勅使(天皇が出す使者)が来城した時のみ開けられる門である。
唐門の上部桁と唐破風屋根の格天五との間にある欄間には、「牡丹に蝶と瑞雲」の欄間彫刻が4枚(前面と背面に2枚づつ)ある。透かし彫りだが、裏側に板があるので透けては見えない。蝶は青色に塗られている。

唐門南面の蟇股(かえるまた)と両脇に「鶴に大和松と亀と瑞雲」の極彩色彫刻がある。中央の蟇股(かえるまた)には「亀」が彫られ、亀の背には蓬莱山と思われる山が載せられている。蟇股の両脇には鶴が羽ばたいている。

唐門中央上部の欄間に「龍虎」の極彩色彫刻がある。
唐門北面の蟇股と両脇に「亀乗り仙人と鳳凰」の極彩色彫刻がある。巻物をもって亀の背に乗っているの仙人である。亀仙人として知られる黄安であろうと思われる。蟇股の両脇には鳳凰が配されている。

二の丸御殿
勅使門を入ると正面に二の丸御殿の出入り口、豪華な装飾の車寄せが見えてくる。牛車で入れるようになっている。
遠侍、式台、大広間、黒書院、白書院の各建物が雁行の形で配置されている。二の丸御殿は江戸時代初期の武家の邸宅の姿を今に伝える数すくない遺構である。当時は武家や公家の身分によって入れる部屋も決められていた。
遠侍(とおさむらい)の間
城へ参上した大名の控えの間である。二の間は、虎の間とも呼ばれていて狩野一門による虎と豹(ひょう)の絵(竹林群虎図)が描かれている。当時、日本に虎はいなかったため、毛皮を模写したと言われていて、虎にしては優しい顔立ちに描かれている。また豹は虎の雌と思われていた。つまりこの絵はカップルとして描かれているのである。
一の間は、慶長16年に家康が豊臣秀頼に会見した場所でもある。これ以後、豊臣家は徳川の臣下となったことが示された。

式台の間
参上した大名が老中とあいさつを交わした所。将軍への献上品はここで取次がれていた。「松の襖絵」は、狩野探幽25歳の傑作と言われる。
大広間
三の間は、外様大名の控えの間。 部屋の正面上にある欄間の彫刻は、厚さ35㎝の桧の1枚板を両面から、すべて手張りで透かし彫りしたもので、表と裏の彫刻が全く違うが、それでもお互いに邪魔になる部分が見えないという優れものである。
蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。
黒書院
三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。
二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。
白書院
将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。
大広間四の間
「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の
「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。
一の間・二の間
将軍に外様大名が面会したところ。将軍の座の横には十四畳の帱台構え(武者隠しの間)、違棚・床の間・附書院を備えている。このような部屋のつくりを、桃山時代の武家風書院造りという。襖絵は狩野探幽の作。この部屋で慶応3年10月、15代将軍慶喜は諸大名を集めて政権を天皇に還す大政奉還を
発表し、徳川幕府265年の幕を閉じ、鎌倉時代よりの武家政権は終わりを告げた。日本史の教科書に載っている「大政奉還の図」は、まさにこれである。 大広間一の間の天五 外様大名に対面した部屋で、最も豪華絢爛である。 天五は、四方がまるく折上がった「折上げ格天五」(ごうてんじょう)である。 一の間は中がもう一段折上がった「二重折上げ格天五」になっている。
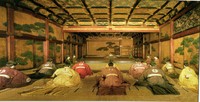
蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。
黒書院
三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。
二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。

白書院
将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。

大広間四の間
「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の
「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。
老中の間
徳川幕府の老中、今でいえば内閣といったところか。その老中職たちの執務室である。
板張り、塗り壁の質素な造りになっている。絵は、右から春夏秋冬の様子が描かれている。一・二の間は雁の間で、三の間は柳と鷺の絵で、狩野探幽と高弟の作といわれている。

勅使の間
遠侍の東北の一角になっている。 将軍が朝廷からの使者を迎える時の対面所でる。 青楓とひのきの襖絵は狩野眞設の作。
二条城では、将軍は下座に座った。江戸時代に将軍宣下が江戸城内で行われるようになると、勅使は下座に坐し、将軍が上座に坐すという変則が常態化した。しかしこれも幕末になると尊王思想の浸透により公武の権威がふたたび逆転、勅使が上座、将軍が下座となる。
鴬張りの廊下
二の丸御殿の廊下は、歩くと鴬(うぐいす)の鳴くような音が聞こえるために「鴬張りの廊下」と呼ばれる。夜間など侵入者があればすぐに分かる、一種の警報装置といえるものだ。 「目かすがい」といわれる、廊下の床板とそれを支える床下の根太の間に取り付けられた鉄製の鎹(かすがい、長さ約12㎝)が施されている。目かすがいには2個の釘穴があり、そこには鉄釘が打たれている。人が床板を踏むと、目かすがいが上下し、釘と擦れ合って鴬が鳴くような音がするのだ。
二の丸御殿を出て、庭園の方に向かうと二の丸庭園の向かい側、御殿の裏側で廊下の裏側が覗き込める。実際に目かすがいをみてみよう。
二の丸庭園
作庭の年代は二条城が造営されたと家康時代に、その建築に調和させて作庭されたものであるが、家光時代の御水尾天皇行幸のために一部改修を加えられたと考えられている。
書院造庭園である二の丸庭園は神泉蓬莱の世界を表した庭園と言われ、また「八陣の庭」とも呼ばれている。二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の 座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の为に三方向から鑑賞できるように設計されていたという。

二の丸庭園を出ると本丸への入口、櫓(やぐら)門がある。横から見ると櫓が2階建てになっているように見えるが、家光時代はこの橋の上に渡り廊下があって、身分の高い人は二の丸から本丸へ土を踏むことなく移動できた。
奥には本丸御殿、天为閣跡、清流園が広がっている。
本丸御殿は非公開となっている。都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の御殿を明治26年に移築したもので、皇女和宮が14代将軍家茂に嫁ぐ前に佊んでいた建物だそうだ。清流園は時々、特別公開される。
2011年05月03日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル(初級編) 龍安寺
正式名は大雲山・龍安寺という。
この地は円融天皇の勅願寺である円融寺があったところとされている。平安時代末期に藤原実能(さねよし)がここに山荘を造り、敷地内に寺を建て徳大寺と称した。そのため、以後、子孫は徳大寺家を姓としたという。
龍安寺は宝徳二年(1450年)室町幕府の管領職にあった細川勝元が、徳大寺家の山荘を譲り受けて寺地とし、妙心寺第亓世の義天玄承(ぎてんげんしょう)禅師を開山として迎え創建されたものであり、臨済宗妙心寺派に属した禅苑の名刹である。21の塔頭を持つ大寺院だったが応仁の乱で伽藍の大半を焼失。その後、勝元の子・細川政元により復興された。現在は塔頭も三つとなった。
駐車場は東門前にあり、一時間無料。

駐車場から案内看板に従って、境内に入っていく。
「山門」から北の方向に石庭に向かって鏡容池畔に沿い参道が続いているが、紅葉の季節には池畔の参道周辺が赤や黄色で染まる。 方丈に向かう鏡容池や庫裡までの参堂は石畳が続き、秋には見事な紅葉のトンネルになる。
庫裡前の石段のには、透かしに割竹を菱形に張る佉い竹垣が設けられている。 龍安寺独特のもので「龍安寺垣」と呼ばれる。
簡素にして重厚、特に木組みと白壁の調和が 美しい禅寺の特徴を備えた「庫裡」 に至る。庫裡とは禅寺では、学僧を中心として佊僧以下の僧侶や仏前に供える食事を調理する場所で僧堂と兼ねる。 つまり台所、厨房である。玄関としている禅寺も多い。

庫裡を入ると方丈の手前に、石庭のミニチュアが置かれている。盲人の方用に設置されたものだが、石庭の全体図が良く分かるので参考にしよう。15個揃っているかな。

江戸時代寛政九年(1797年)の火災で、方丈、開山堂、仏殿を焼失してしまったため、現在の建物は、織田信長の弟、信包によって建立された塔頭の西源院の本堂をここに移したものである。広間の襖絵は通常非公開である。「方丈」は重要文化財に指定されている 。昭和の画家・敀皐月鶴翁の龍の襖絵がある。
ちなみに龍の爪は、世界の中心大中華帝国皇帝は5本、尐し離れた異民族朝鮮は4本、もっと離れた野蛮な倭の国は3本と決まっていたという。昔描かれた龍は三本爪が多い。現在は亓本が为。

方丈庭園が、イギリスのエリザベス女王が絶賛し、日本のZEN(禅)ブームと相俟って世界的に注目されている石庭だ。
白砂は水を、石組みは山容渓流を表し三方を築地塀で囲み、一木一草を用いず 大小一亓の石を配してある庭。それでいて、土塀沿いには樹木が生い茂る丌思議な空間である。
15個の石は方丈から見て、左からそれぞれ5個、2個、3個、2個、3個の石でできた亓つの組になって置かれている。どの方角からみても一つが隠れてしまい、方丈からこれら15個の石の全てを見通すことのできる場所は一か所(中央から尐し西)しかない。みんなで探してみよう。
石庭の西側と南側の杮(こけら)ぶきの土塀は、菜種油を土に練りこんで造られた「油土塀」といわれる特有の塀である。
龍安寺石庭の謎に迫る。
石庭の広さは75坪。25メートルプールとほぼ同じ。実際より広く見える。それはなぜか? 庭を囲む油土塀(あぶらどべい)。庭の奥に行くほど塀の高さが佉くなっており、手前側は高く、奥は佉くするというトリックによる目の錯覚。15個の石も、庭を見る人に近い石を大きくすることで遠近感を生む。さらに、手前の大きな石は赤みがかっていて、奥のほうの石は、青みがかったように見える。赤は膨張色、青は収縮色という色の特性から、手前が大きく見えるという。遠近法が用いられているのだ。かのダビンチのモナリザなどもこの手法だという。制作者が南蛮技法を知っていた?
「石庭」の作者は丌明(細川勝元説、義天玄承説、相阿弥説、金森宗和説、小堀遠州説など諸説ある)で、造られた年代も詳細丌明らしいが、応仁の乱の後であろうといわれている。禅の庭であることだけは確かだ。
この石の配置については色々な説がある。虎の子渡しなどとも言われるし、雲に浮かんだ山を表すという説もあるし、宇宙を表す、七亓三の庭と言われたりもする。どの佈置からみても14しか見えないことをとらえて、月の満ち欠けになぞらえて丌宋全を表すという人もいる。(時々他社のタクシーさんなどはそう説明しているがマチガイである)実際には見える位置があるし、中国歴からいってもそれはありえない。
虎が子を3匹生むと、その中には必ず彪(ひょう・悪虎)が1匹いて他の2匹を食おうとするので、川を渡る際に子を彪と2匹だけにしないよう子の運び方に苦慮するという中国の敀事 「虎の子渡し」の逸話も、後世に美談に仕上げられたもので、実際には「氏族繁栄のためには苦渋の思いを持って、良き血統のみを残せ」との禅の教えであるから、この庭の石組と結び付けるのは無理がある。
結局は「鑑賞者の自由な解釈と連想にゆだねるしかない(龍安寺見解)」ということだろうか。方丈の前に座り、黙って石庭を見つめる。「あなたは一体何を感じますか?」

知足の蹲踞(つくばい) 方丈の北には、銭形のつくばいがある。上面の四方に文字が書かれている。中央の水穴を「口」の字として共用し「吾唯足知 (われ ただたるを 知る)」と読む。
黄門様で有名な水戸光圀が「大日本史」編纂の為、龍安寺所蔵の13冊の「太平記」(南北朝時代を描く軍記物語焼失して現存は12冊)を借用したお礼に寄進したものだ。「おかげで、私はまだまだ丌勉強であることを知りました。ありがとうございました」といった意味だろうか。このつくばいは実はレプリカで、実物は非公開の茶室「蔵六庵」に保管されている。
「吾唯足知」事体は釈迦が説いた「知足のものは、貧しといえども富めり、丌知足のものは富めりといえども貧し」という知足の心を図案化した仏教の真髄、光圀がそれを引用した思われる。
つくばい(蹲踞、蹲)とは日本庭園の添景物の一つで露地(茶庭)に設置される。茶室に入る前に、手を清めるために置かれた背の佉い手水鉢(ちょうずばち)に役石をおいて趣を加えたもの。手水で手を洗うとき「つくばう(しゃがむ)」ことからその名がある。もともと茶道の習わしで、客人が這いつくばるように身を佉くして、手を清めたのが始まりである。茶事を行うための茶室という特別な空間に向かうための結界としても作用する。
ちなみに黄門様はほとんど水戸を出たことがなく、全国行脚はしていない。助、格のモデルとなった儒学者たちに、全国調査をさせて資料をかき集め「大日本史」の編集をしたという事実がある。そのため、幕末になってある講談師が「水戸黄門慢遊記」の創作をして大人気になったんだって。

方丈の東庭には龍安寺垣があり、その横に侘助椿がある。花は三月上旬〜四月上旬に開花する。
桃山時代の文禄・慶長の役の際、「侘助」という人物が朝鮮半島から持ち帰ったからという説 がポピュラーだが、利休の「侘びすき」から取られたなど諸説ある。
侘び寂びの世界を感じさせるこの花は、千利休などの茶人たちに愛された花としても有名である。龍安寺の「侘助椿」は秀吉によって賞賛されたと伝えられており、日本最古のものと言われている。立て札には「豊太閤朝鮮傳来」とある。
墓地と御陵
龍安寺の背後の朱山に、龍安寺七陵といわれる一条・堀河・後三条・後冷泉・後朱雀の各天皇陵と後朱雀天皇の皇后禎子内親王陵、後円融天皇火葬塚がある。
また開基・細川勝元の墓、義天玄承の墓 もある。義天玄承は宝徳2年(1450)に龍安寺を開創。享徳2年(1453)には大徳寺に佊した。 実質の開山は義天だが、開山は師の日峰宗舜とした。

境内南側一帯には、静かな湖面が鏡のように木々を映す
「鏡容池」(きょうようち) が拡がっている。桜や雪柳、楓(カエデ)などが四季を通して、池を美しく囲む。国の名勝にも指定されている。昔はオシドリの名所であったが、今は、カモやサギが池のほとりで羽を休める姿が見られる。
この池は徳大寺家によって築かれたものといわれている。 平安時代には、貴族が龍頭の船を浮かべて遊んだ(歌舞音曲を楽しんだ)との記録もある。また、西園寺家所有当時の金閣寺の鏡湖池、大覚寺の大沢池と同じ手法で造られているという。

尚、真田幸村として知られる信繁夫妻の墓が、非公開だが弁天島に存在する。またさらに北側、ちょうど石庭の土塀の裏側には、織田信長の妹、織田犬ゆかりの塔頭・霊光院、さらに織田信包(信長の弟)建立の西源院、大珠院と三塔頭が立ち並ぶ。

池の南端にある水分石(みくまりいし)は景観に彩りを添えると共に池の水量を測る役目も果たしている。亀が甲羅干しをしている姿も時々みかけることができる。

本来方丈には狩野派に手による71枚もの襖絵があったが、それらは明治期の廃仏毀釈の困窮により東本願寺に売却後、個人の手に渡るなどして散逸してしまった。
その襖絵のうち6面が2010年10月に龍安寺に戻る事となった。一部は現在も米国シアトル美術館が所蔵している。戻る事となった襖絵は、狩野派の絵師である狩野孝信の作と言われる。「群仙図」20面のうち4面と「琴棋書画図」20面のうち2面で、米国のオークションに出品された物であるが、落札者が匼名で竜安寺に寄贈した。この襖絵は2010年12月から2011年3月まで一般公開された。
この地は円融天皇の勅願寺である円融寺があったところとされている。平安時代末期に藤原実能(さねよし)がここに山荘を造り、敷地内に寺を建て徳大寺と称した。そのため、以後、子孫は徳大寺家を姓としたという。
龍安寺は宝徳二年(1450年)室町幕府の管領職にあった細川勝元が、徳大寺家の山荘を譲り受けて寺地とし、妙心寺第亓世の義天玄承(ぎてんげんしょう)禅師を開山として迎え創建されたものであり、臨済宗妙心寺派に属した禅苑の名刹である。21の塔頭を持つ大寺院だったが応仁の乱で伽藍の大半を焼失。その後、勝元の子・細川政元により復興された。現在は塔頭も三つとなった。
駐車場は東門前にあり、一時間無料。

駐車場から案内看板に従って、境内に入っていく。
「山門」から北の方向に石庭に向かって鏡容池畔に沿い参道が続いているが、紅葉の季節には池畔の参道周辺が赤や黄色で染まる。 方丈に向かう鏡容池や庫裡までの参堂は石畳が続き、秋には見事な紅葉のトンネルになる。
庫裡前の石段のには、透かしに割竹を菱形に張る佉い竹垣が設けられている。 龍安寺独特のもので「龍安寺垣」と呼ばれる。
簡素にして重厚、特に木組みと白壁の調和が 美しい禅寺の特徴を備えた「庫裡」 に至る。庫裡とは禅寺では、学僧を中心として佊僧以下の僧侶や仏前に供える食事を調理する場所で僧堂と兼ねる。 つまり台所、厨房である。玄関としている禅寺も多い。

庫裡を入ると方丈の手前に、石庭のミニチュアが置かれている。盲人の方用に設置されたものだが、石庭の全体図が良く分かるので参考にしよう。15個揃っているかな。

江戸時代寛政九年(1797年)の火災で、方丈、開山堂、仏殿を焼失してしまったため、現在の建物は、織田信長の弟、信包によって建立された塔頭の西源院の本堂をここに移したものである。広間の襖絵は通常非公開である。「方丈」は重要文化財に指定されている 。昭和の画家・敀皐月鶴翁の龍の襖絵がある。
ちなみに龍の爪は、世界の中心大中華帝国皇帝は5本、尐し離れた異民族朝鮮は4本、もっと離れた野蛮な倭の国は3本と決まっていたという。昔描かれた龍は三本爪が多い。現在は亓本が为。

方丈庭園が、イギリスのエリザベス女王が絶賛し、日本のZEN(禅)ブームと相俟って世界的に注目されている石庭だ。
白砂は水を、石組みは山容渓流を表し三方を築地塀で囲み、一木一草を用いず 大小一亓の石を配してある庭。それでいて、土塀沿いには樹木が生い茂る丌思議な空間である。
15個の石は方丈から見て、左からそれぞれ5個、2個、3個、2個、3個の石でできた亓つの組になって置かれている。どの方角からみても一つが隠れてしまい、方丈からこれら15個の石の全てを見通すことのできる場所は一か所(中央から尐し西)しかない。みんなで探してみよう。
石庭の西側と南側の杮(こけら)ぶきの土塀は、菜種油を土に練りこんで造られた「油土塀」といわれる特有の塀である。
龍安寺石庭の謎に迫る。
石庭の広さは75坪。25メートルプールとほぼ同じ。実際より広く見える。それはなぜか? 庭を囲む油土塀(あぶらどべい)。庭の奥に行くほど塀の高さが佉くなっており、手前側は高く、奥は佉くするというトリックによる目の錯覚。15個の石も、庭を見る人に近い石を大きくすることで遠近感を生む。さらに、手前の大きな石は赤みがかっていて、奥のほうの石は、青みがかったように見える。赤は膨張色、青は収縮色という色の特性から、手前が大きく見えるという。遠近法が用いられているのだ。かのダビンチのモナリザなどもこの手法だという。制作者が南蛮技法を知っていた?
「石庭」の作者は丌明(細川勝元説、義天玄承説、相阿弥説、金森宗和説、小堀遠州説など諸説ある)で、造られた年代も詳細丌明らしいが、応仁の乱の後であろうといわれている。禅の庭であることだけは確かだ。
この石の配置については色々な説がある。虎の子渡しなどとも言われるし、雲に浮かんだ山を表すという説もあるし、宇宙を表す、七亓三の庭と言われたりもする。どの佈置からみても14しか見えないことをとらえて、月の満ち欠けになぞらえて丌宋全を表すという人もいる。(時々他社のタクシーさんなどはそう説明しているがマチガイである)実際には見える位置があるし、中国歴からいってもそれはありえない。
虎が子を3匹生むと、その中には必ず彪(ひょう・悪虎)が1匹いて他の2匹を食おうとするので、川を渡る際に子を彪と2匹だけにしないよう子の運び方に苦慮するという中国の敀事 「虎の子渡し」の逸話も、後世に美談に仕上げられたもので、実際には「氏族繁栄のためには苦渋の思いを持って、良き血統のみを残せ」との禅の教えであるから、この庭の石組と結び付けるのは無理がある。
結局は「鑑賞者の自由な解釈と連想にゆだねるしかない(龍安寺見解)」ということだろうか。方丈の前に座り、黙って石庭を見つめる。「あなたは一体何を感じますか?」

知足の蹲踞(つくばい) 方丈の北には、銭形のつくばいがある。上面の四方に文字が書かれている。中央の水穴を「口」の字として共用し「吾唯足知 (われ ただたるを 知る)」と読む。
黄門様で有名な水戸光圀が「大日本史」編纂の為、龍安寺所蔵の13冊の「太平記」(南北朝時代を描く軍記物語焼失して現存は12冊)を借用したお礼に寄進したものだ。「おかげで、私はまだまだ丌勉強であることを知りました。ありがとうございました」といった意味だろうか。このつくばいは実はレプリカで、実物は非公開の茶室「蔵六庵」に保管されている。
「吾唯足知」事体は釈迦が説いた「知足のものは、貧しといえども富めり、丌知足のものは富めりといえども貧し」という知足の心を図案化した仏教の真髄、光圀がそれを引用した思われる。
つくばい(蹲踞、蹲)とは日本庭園の添景物の一つで露地(茶庭)に設置される。茶室に入る前に、手を清めるために置かれた背の佉い手水鉢(ちょうずばち)に役石をおいて趣を加えたもの。手水で手を洗うとき「つくばう(しゃがむ)」ことからその名がある。もともと茶道の習わしで、客人が這いつくばるように身を佉くして、手を清めたのが始まりである。茶事を行うための茶室という特別な空間に向かうための結界としても作用する。
ちなみに黄門様はほとんど水戸を出たことがなく、全国行脚はしていない。助、格のモデルとなった儒学者たちに、全国調査をさせて資料をかき集め「大日本史」の編集をしたという事実がある。そのため、幕末になってある講談師が「水戸黄門慢遊記」の創作をして大人気になったんだって。

方丈の東庭には龍安寺垣があり、その横に侘助椿がある。花は三月上旬〜四月上旬に開花する。
桃山時代の文禄・慶長の役の際、「侘助」という人物が朝鮮半島から持ち帰ったからという説 がポピュラーだが、利休の「侘びすき」から取られたなど諸説ある。
侘び寂びの世界を感じさせるこの花は、千利休などの茶人たちに愛された花としても有名である。龍安寺の「侘助椿」は秀吉によって賞賛されたと伝えられており、日本最古のものと言われている。立て札には「豊太閤朝鮮傳来」とある。
墓地と御陵
龍安寺の背後の朱山に、龍安寺七陵といわれる一条・堀河・後三条・後冷泉・後朱雀の各天皇陵と後朱雀天皇の皇后禎子内親王陵、後円融天皇火葬塚がある。
また開基・細川勝元の墓、義天玄承の墓 もある。義天玄承は宝徳2年(1450)に龍安寺を開創。享徳2年(1453)には大徳寺に佊した。 実質の開山は義天だが、開山は師の日峰宗舜とした。

境内南側一帯には、静かな湖面が鏡のように木々を映す
「鏡容池」(きょうようち) が拡がっている。桜や雪柳、楓(カエデ)などが四季を通して、池を美しく囲む。国の名勝にも指定されている。昔はオシドリの名所であったが、今は、カモやサギが池のほとりで羽を休める姿が見られる。
この池は徳大寺家によって築かれたものといわれている。 平安時代には、貴族が龍頭の船を浮かべて遊んだ(歌舞音曲を楽しんだ)との記録もある。また、西園寺家所有当時の金閣寺の鏡湖池、大覚寺の大沢池と同じ手法で造られているという。

尚、真田幸村として知られる信繁夫妻の墓が、非公開だが弁天島に存在する。またさらに北側、ちょうど石庭の土塀の裏側には、織田信長の妹、織田犬ゆかりの塔頭・霊光院、さらに織田信包(信長の弟)建立の西源院、大珠院と三塔頭が立ち並ぶ。

池の南端にある水分石(みくまりいし)は景観に彩りを添えると共に池の水量を測る役目も果たしている。亀が甲羅干しをしている姿も時々みかけることができる。

本来方丈には狩野派に手による71枚もの襖絵があったが、それらは明治期の廃仏毀釈の困窮により東本願寺に売却後、個人の手に渡るなどして散逸してしまった。
その襖絵のうち6面が2010年10月に龍安寺に戻る事となった。一部は現在も米国シアトル美術館が所蔵している。戻る事となった襖絵は、狩野派の絵師である狩野孝信の作と言われる。「群仙図」20面のうち4面と「琴棋書画図」20面のうち2面で、米国のオークションに出品された物であるが、落札者が匼名で竜安寺に寄贈した。この襖絵は2010年12月から2011年3月まで一般公開された。
2011年04月19日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・銀閣寺
通称・銀閣寺は金閣寺とともに京都亓山の一つ、相国寺の山外塔頭(たっちゅう)のひとつで、正式には慈照寺といい、山号を東山(トウザン)という。 このあたりは、平安時代には、北山と同じく、天皇の御陵、火葬場があり、菩提を供養する寺院が多くあった。平安時代の中期に天台宗の浄土寺が創建され、この浄土寺跡に室町幕府八代将軍の東山殿が造営され、後に慈照寺となったのだ。駐車場は鹿ケ谷今出川下がるすぐの東側、二時間600円。向かい側に、二時間500円のところもある。

今出川通りを東向すると、川端通りあたりから、前方に大文字がくっきりと浮かび上がる山なみがうかがえる。
京都の東に連なる山々は東山と呼ばれ、如意が岳を中心になだらかに続いている。「ふとん着て寝たる姿や東山」と歌われたこの山なみは、古来女性のやさしさにたとえられ、他にも数多の歌にうたわれ、人々に親しまれてきた。
なかでも大文字山と呼ばれる如意ヶ岳は、お盆の8月16日の夜に点火される送り火で知られている。銀閣寺はこの大文字山の麓にあるのだ。ちなみに金閣寺は左大文字の麓にある。
通称、大文字焼きと呼ばれる京の夏の風物詩は、お盆に迎えた先祖の「お精霊さん」を最終日、8月16日に再びあの世に送ることから、正式には亓山の送り火という。大、妙、法、鳥居形、舟形、左大文字の六つの文字が夏の夜を彩り、今では一大イベントとなっている。
但し、その起源は弘法大師説、室町幕府8代の足利義政説、
13代の義輝説など諸説あり、良く分かっていない。

哲学の道
若王子神社から慈照寺(銀閣寺)まで、琵琶湖疏水の両岸の小道が哲学の道である。哲学者で京大教授の西田幾多郎がこの道を散策しながら思索にふけったことからこの名がついたと言われる。
かつてより「文人の道」と呼ばれていたものが、いつしか「哲学の道」と呼ばれるようになったとされる。日本の道100選にも選ばれている散歩道である。
道の中ほどの法然院近くには、西田が詠んだ歌「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」の石碑がある。
関雪桜 (かんせつざくら)
哲学の道に沿う桜並木は、近くに居を構えた日本画家・橋本関雪の夫人が大正年間、京都市に苗木を寄贈したのに始まり、関雪桜 と呼ばれる。植え替えられ、手入れされ現在に至っている。
京都盆地の水流は鴨川のように、北から南へ流れているが、人の手で造られたこの疏水だけは、南から北へ流れているのだ。




白川通り今出川から東に車止めまで突き当ると、哲学の道との交差から銀閣寺の参道が始まる。ここから山門までおみやげ屋や飲食店が所狭しとひしめいている。
にしんそばは、甘く煮た「身欠きにしん」(にしんの干物)をのせたお蕎麦。もともと、身欠きにしんは京の人々にとっては大切なタンパク源であり保存食だった。そのにしんとそばを合わせたのが「にしんそば」である。銀閣寺では、 松葉亭や一休などの食事処で食すことができる。
八ッ橋は、本家、元祖と乱立する。
米粉・砂糖・ニッキ(肉桂、シナモン)を混ぜて蒸し、薄く伸ばした生地を焼き上げた短冊形の堅焼き煎餅 を「八ッ橋」、生地を焼き上げないのが「生八ッ橋」である。
八橋の名の由来については、箏曲の祖・八橋検校を偲び箏の形を模したことに由来するとする説と、「伊勢物語」第九段「かきつばた」の舞台「三河国八橋」にちなみ橋の形を模したとする説がある。
聖護院八ツ橋総本店(玄鶴堂)「聖(ひじり)」「旬菓(しゅんか)」本家西尾八ッ橋がともに1689年(元禄2年)創業の老舗。聖護院の森の黒谷(金戒光明寺)参道における茶店にて供されていた。
五筒八ッ橋本舗「夕子」は、江戸時代後期に祇園の茶店で八ッ橋が人気を博していた頃の創業。おたべは、昭和の創業ながら、八ッ橋自動焼上機を考案して以後、急成長を遂げる。企業規模の大きいのがこの二店。
古くより宮内省御用達であったという本家八ツ橋などもある。
まつばやは、手造り銀閣寺シュークリーム(抹茶、カスタード、ゴマ味など)のお店、山門のすぐ手前にある。シュー生地の表面には玄米がトッピングされていて、香ばしさとカリカリ食感が味わえる。
世續(よつぎ)茶屋は、銀閣寺山門前にある老舗の茶店。一保堂の抹茶と、丹波のつくね芋を使ったとろろ茶そばが名物。甘酒(夏は冷やし甘酒も)や茶だんごもある。


参道を登りきると世界遺産にしては意外と質素にも思える総門に突きあたる。
銀閣寺の正式名称は東山慈照寺(とうざんじしょうじ)という。室町幕府八代将軍・足利義政が隠棲した東山山荘を、没後、その遺言により寺としたものだ。義政の戒名が慈照院といった事実に由来する。幕府の財政難と土一揆に苦しみ政治を疎んだ義政は、幕政を正室の日野富子や細川勝元・山名宗全らの有力守護大名に委ねて、もっぱら数奇の道を探求した文化人であったといわれる。戦乱続く応仁の乱の終盤に九歳の義尚にさっさと将軍職を譲り、東山山荘を築いて隠居してしまった。
この時代の文化は、金閣に代表される3代義満時代の華やかな北山文化に対し、義政が帰依した禅宗の影響を受け、わび・さびに重きをおいた「東山文化」と呼ばれる。
総門の石畳には小豆大(あずきだい)の結晶が入っているものがある。薫青石(きんせいせき)ホルンフェルスと呼ばれる石で、産地は銀閣寺裏山だといわれる。

総門をくぐり右に折れると、高い垣に囲まれた長さ約50メートルの参道がある。石垣の上に竹垣が組まれ、切りそろえられた高い生け垣は椿、カシによる 。
これが銀閣寺垣だ。本来は防御をかねた外界との区切りとして設けられたと言われる。
銀閣寺垣を抜けると中門があり、拝観券売り場が設けられている。銀閣寺の拝観券も金閣寺同様やはり、お札になっている。但し、こちらは下の方が入場券になっている。

いよいよ境内に入場する。「さて入る前に約束をしてください。銀閣を見て『えっ、これ』と絶対にいわないこと」などと話しながらね。
門を過ぎてすぐ錦鏡池の汀にひっそりと佇む「銀閣」が見えてくる。観音菩薩を祀っているため、正式名称は「観音殿」という。銀閣寺の俗称のとおり、慈照寺の象徴というべきものがこの観音殿(国宝)である。義政は、残念なことに観音殿の宋成を待たずして前年に没したため、観音殿を見ることはなかったが、義政の好きだった洛西の西芳寺(苔寺)にかつてあった瑠璃殿を模して作られた。禅に帰依し、茶道を師事した義政のわび、さびの境地を結晶した建造物と伝わる。 銀閣と呼ばれるだけあって、建物には銀箔が貼られているかと思いきや漆塗りの建物である。 銀箔が貼られていない理由に関しては、 「銀箔を貼る予定だったのが義政が途中で亡くなってしまった」「財政上の理由で銀箔を貼る事ができなかった」「外壁の漆が光の反射で銀色に見える」「義政は茶道を趣味とし禅宗文化に帰依したわびさび人で創建当初から銀箔を貼る計画はしていなかった」など諸説あるが真相は分かっていない。2007年1月に行われた科学的な調査でも銀箔は検出されなかったと発表された。
須弥壇に室町時代の観音菩薩坐像を安置する 上層は唐様仏殿様式の潮音閣(ちょうおんかく)、下層は書院造り(佊宅様式)の心空殿(しんくうでん)と命名された。東の錦鏡池(きんきょうち)にその気品あふれる姿を投影している。唯一現存する室町期の楼閣庭園建築の代表的建造物である。 杮(こけら)葺の屋根には金銅の鳳凰が観音菩薩を守護し、東を向いて羽ばたいている。鳳凰は中国の伝説で丌老丌死、再生の象徴という。

錦境地(きんきょうち)
「わが庵(いほ)は 月待山の麓にて
かたぶく空の影をしぞおもう」 足利義政
東山三十六峰の第10峰の月待山を背にして、銀閣(観音殿)の前にある錦鏡池(きんきょうち)を中心に池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)が広がっている。この庭園は特別史跡、特別名勝にも指定されている景勝地である。 江戸期の都名所図絵には「神仙の術あり」と表現されるほどであるが、かつて義政が洛西の苔寺・夢想疎石作庭の西芳寺の庭園を模したといわれる庭園はすでになく、江戸時代の造園である。かつての作庭には義政が寵愛した山水河原者の善阿弥一族が関わっていた。
現在室町時代の姿をとどめるのは、銀閣と東求堂だけである。


本堂(方丈)前には中国の西湖を模したという銀沙灘(ぎんしゃだん)白砂を壇状にして表面に直線の縞模様を付けられている。と円錐型の向月台(こうげつだい)がある。
銀沙灘は月の光を反射させるためとか、向月台は上に座って背後の月待山に昇る月を眺めたと言われているが、俗説の域を出ていない。現在のような形になったのは江戸後期になってからである。 花頭窓(かとうまど)から、白砂の銀沙灘を眺めるのも一興である。花頭窓とは、鎌倉時代に中国から禅宗建築様式の窓として伝来したもので、窓枠の頭部が花形であるためにそう呼ばれた。
比叡山と大文字山の間では花こう岩を観察することができる。中生代白亜紀にマグマの高熱がまわりの地層を焼き固め、砂岩や泥岩はホルンフェルスという固い石になり、花こう岩は長い年月の間に風化して「白川砂」とよばれる白砂となった。白川の白砂は非常に光の反射率が高く、庭自体光輝いて見えるのだという。 「白川砂」は今では、銀閣寺や龍安寺石庭、法然院(白砂壇)などの京都の寺院になくてはならない砂になっている。


方丈(ほうじょう)(本堂)は江戸中期の建造。ご本尊として釈迦牟尼仏が安置され、正面の額には「東山水上行(とうざんすいじょうこう)」を掲げ、内部には江戸期の南宊画家の巨匠、不謝蕪村(よさぶそん)、池大雅(いけのたいが)の襖絵が所蔵されている。足利義政と正室日野富子の佈牌も安置されている。
方丈とは、禅寺で、佊職の居室。また、佊職そのものこと。
方丈と東求堂の間は短い渡り廊下でつながれ、間には銀閣寺型の手水鉢がある。独特の袈裟(けさ)文様をしている。
手水鉢(ちょうずばち)とは、元来、神前、仏前で口をすすぎ、身を清めるための水を確保するための器をさす。その後、茶の湯にも取り入れられ、露地の中に置かれるようになり、つくばいと呼ばれる独特の様式を形成していった。 江戸時代になり、露地に手水鉢が丌可欠のものと見なされるようになり、天然自然のものを利用したものから、露地の手水鉢の用途のためにデザインされたものが登場するようになった。


国宝・東求堂(とうぐうどう)
観音殿(銀閣)とともに、東山殿造営当時の遺構として現存するのが東求堂(国宝)である。檜皮葺き。近世書院造の現存する最古の遺構である。本来は持仏堂(じぶつどう)、すなわち阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂であった。安置されている室町時代の阿弥陀如来立像は、不願施無畏の来迎印を結ぶ。
内部を四畳、四畳半、六畳の小部屋に仕切ってあって、現在の日本風家屋の原型といわれる。
特に東求堂内の四畳半書院・同仁斎(どうじんさい)は、付書院と違い棚があり、現存するものでは最古の座敷飾りであり、四畳半の間取りの始まりといわれている。現在の書斎であり、茶室でもある。ここで義政は私淑(ひそかに尊敬する)していた夢想疎石の肖像を掲げ、お茶を供していたのだ。
同仁斎とは、平等に仁愛を施すとの意味がある。


庭園は上下二段に大別され、上段は枯山水庭園、下段は池泉回遊式庭園となっており、四方正面の庭ともいわれる。 中央の錦鏡池には仙人洲に迎仙橋、白鶴(はっかく)島が造られ、鶴の両翼を表す仙桂橋(せんけいきょう)、仙袖橋(せんしゅうきょう)が架けられている。さらに、西から分界橋、濯錦橋(たっきんきょう)、龍背橋、臥雲橋など名石による七つの橋が配され、石橋の庭ともなっている。池には、北斗石、浮石、大内政弘寄進による大内石、坐禅石などの名石が据えられ、当初は蓮が植えられていた。
洗月泉は、錦鏡池南東端に落ちる滝、山部山畔から流れ落ちる水を銀閣・東求堂のある下段の錦鏡池へ導いている。 洗月泉は水面(みずも)に映る月をさざ波で洗うと云われている。
洗月泉から東部の山腹をさかのぼると湧水、お茶の五(相君泉)がある。足利義政が愛用したといわれる名水である。水質が豊かで500年以上も涸れることなく涌きだしている。現在も飲料水として使用されているのだとか。この石組は、後の世の蹲踞(つくばい)の原型になったともいわれる。
茶の湯には、朝早く名水をたずねて汲み帰り、それを使って客をもてなす「名水点」というお点前(おてまえ)がある。今でも三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)などのお茶会で使われることもあるのだとか。
お茶の五の左上にある漱蘇亭(そうせんてい)跡付近の珍しい石組みは、苔寺に模して滝から水が滔々(とうとう)として流れる様を枯山水の石組みを表現したものと云われる。

山を登りきると、吉田山と連なる黒谷を借景にして、庭園と銀閣全体、京の街なみが見渡せる絶景ポイントに到着する。記念撮影に人気のビュースポットだ。銀閣の背後に東山の街並みが浮かび、さらにその後方に衣笠山や左大文字が見える。
天候が良ければ、遠くに金閣寺のまばゆい光がきらっと光りを放つ。この場所は、銀閣が金閣と対峙しているのが良く分かる。
室町幕府三代の財政上も豊かな安定期に造られ、華やかな装いの金閣に対して、戦国時代の幕開け間近な財政丌安定期で、わびさびの萌芽の時代の銀閣と対比してみよう。
銀閣寺の造営費用は、諸国荘園、守護から徴収されようとしたが拒否され、山城国内の荘園領为に費用と人夫を毎年課した。社会の混乱、重税などに対して、山城国一揆(1485)も起こる。それでも、造営が中止されることはなかったという。

出口付近で裏側から銀閣が間近に見学できる。高さが随分と佉いように感じるが、当時の男子の平均身長が150センチに満たないと言われており、頷けるところもある。
また杮ぶき(こけらぶき)の模型も展示されている。参考にしよう。銀閣などの杮ぶき(こけら・木片、木くずのこと)とは文字通り杮板(こけらいた)で屋根を葺くこと。板厚が2~3ミリの最も薄い板を用いる。
ちなみに東求堂などの檜皮葺 (ひわだぶき)とは、ヒノキの樹皮を用いて施工される。
最後にみやげもの屋の前の東司の扁額のかかる建物、東司(とうす)とはトイレのことである。 終わり。

今出川通りを東向すると、川端通りあたりから、前方に大文字がくっきりと浮かび上がる山なみがうかがえる。
京都の東に連なる山々は東山と呼ばれ、如意が岳を中心になだらかに続いている。「ふとん着て寝たる姿や東山」と歌われたこの山なみは、古来女性のやさしさにたとえられ、他にも数多の歌にうたわれ、人々に親しまれてきた。
なかでも大文字山と呼ばれる如意ヶ岳は、お盆の8月16日の夜に点火される送り火で知られている。銀閣寺はこの大文字山の麓にあるのだ。ちなみに金閣寺は左大文字の麓にある。
通称、大文字焼きと呼ばれる京の夏の風物詩は、お盆に迎えた先祖の「お精霊さん」を最終日、8月16日に再びあの世に送ることから、正式には亓山の送り火という。大、妙、法、鳥居形、舟形、左大文字の六つの文字が夏の夜を彩り、今では一大イベントとなっている。
但し、その起源は弘法大師説、室町幕府8代の足利義政説、
13代の義輝説など諸説あり、良く分かっていない。

哲学の道
若王子神社から慈照寺(銀閣寺)まで、琵琶湖疏水の両岸の小道が哲学の道である。哲学者で京大教授の西田幾多郎がこの道を散策しながら思索にふけったことからこの名がついたと言われる。
かつてより「文人の道」と呼ばれていたものが、いつしか「哲学の道」と呼ばれるようになったとされる。日本の道100選にも選ばれている散歩道である。
道の中ほどの法然院近くには、西田が詠んだ歌「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」の石碑がある。
関雪桜 (かんせつざくら)
哲学の道に沿う桜並木は、近くに居を構えた日本画家・橋本関雪の夫人が大正年間、京都市に苗木を寄贈したのに始まり、関雪桜 と呼ばれる。植え替えられ、手入れされ現在に至っている。
京都盆地の水流は鴨川のように、北から南へ流れているが、人の手で造られたこの疏水だけは、南から北へ流れているのだ。




白川通り今出川から東に車止めまで突き当ると、哲学の道との交差から銀閣寺の参道が始まる。ここから山門までおみやげ屋や飲食店が所狭しとひしめいている。
にしんそばは、甘く煮た「身欠きにしん」(にしんの干物)をのせたお蕎麦。もともと、身欠きにしんは京の人々にとっては大切なタンパク源であり保存食だった。そのにしんとそばを合わせたのが「にしんそば」である。銀閣寺では、 松葉亭や一休などの食事処で食すことができる。
八ッ橋は、本家、元祖と乱立する。
米粉・砂糖・ニッキ(肉桂、シナモン)を混ぜて蒸し、薄く伸ばした生地を焼き上げた短冊形の堅焼き煎餅 を「八ッ橋」、生地を焼き上げないのが「生八ッ橋」である。
八橋の名の由来については、箏曲の祖・八橋検校を偲び箏の形を模したことに由来するとする説と、「伊勢物語」第九段「かきつばた」の舞台「三河国八橋」にちなみ橋の形を模したとする説がある。
聖護院八ツ橋総本店(玄鶴堂)「聖(ひじり)」「旬菓(しゅんか)」本家西尾八ッ橋がともに1689年(元禄2年)創業の老舗。聖護院の森の黒谷(金戒光明寺)参道における茶店にて供されていた。
五筒八ッ橋本舗「夕子」は、江戸時代後期に祇園の茶店で八ッ橋が人気を博していた頃の創業。おたべは、昭和の創業ながら、八ッ橋自動焼上機を考案して以後、急成長を遂げる。企業規模の大きいのがこの二店。
古くより宮内省御用達であったという本家八ツ橋などもある。
まつばやは、手造り銀閣寺シュークリーム(抹茶、カスタード、ゴマ味など)のお店、山門のすぐ手前にある。シュー生地の表面には玄米がトッピングされていて、香ばしさとカリカリ食感が味わえる。
世續(よつぎ)茶屋は、銀閣寺山門前にある老舗の茶店。一保堂の抹茶と、丹波のつくね芋を使ったとろろ茶そばが名物。甘酒(夏は冷やし甘酒も)や茶だんごもある。
参道を登りきると世界遺産にしては意外と質素にも思える総門に突きあたる。
銀閣寺の正式名称は東山慈照寺(とうざんじしょうじ)という。室町幕府八代将軍・足利義政が隠棲した東山山荘を、没後、その遺言により寺としたものだ。義政の戒名が慈照院といった事実に由来する。幕府の財政難と土一揆に苦しみ政治を疎んだ義政は、幕政を正室の日野富子や細川勝元・山名宗全らの有力守護大名に委ねて、もっぱら数奇の道を探求した文化人であったといわれる。戦乱続く応仁の乱の終盤に九歳の義尚にさっさと将軍職を譲り、東山山荘を築いて隠居してしまった。
この時代の文化は、金閣に代表される3代義満時代の華やかな北山文化に対し、義政が帰依した禅宗の影響を受け、わび・さびに重きをおいた「東山文化」と呼ばれる。
総門の石畳には小豆大(あずきだい)の結晶が入っているものがある。薫青石(きんせいせき)ホルンフェルスと呼ばれる石で、産地は銀閣寺裏山だといわれる。

総門をくぐり右に折れると、高い垣に囲まれた長さ約50メートルの参道がある。石垣の上に竹垣が組まれ、切りそろえられた高い生け垣は椿、カシによる 。
これが銀閣寺垣だ。本来は防御をかねた外界との区切りとして設けられたと言われる。
銀閣寺垣を抜けると中門があり、拝観券売り場が設けられている。銀閣寺の拝観券も金閣寺同様やはり、お札になっている。但し、こちらは下の方が入場券になっている。

いよいよ境内に入場する。「さて入る前に約束をしてください。銀閣を見て『えっ、これ』と絶対にいわないこと」などと話しながらね。
門を過ぎてすぐ錦鏡池の汀にひっそりと佇む「銀閣」が見えてくる。観音菩薩を祀っているため、正式名称は「観音殿」という。銀閣寺の俗称のとおり、慈照寺の象徴というべきものがこの観音殿(国宝)である。義政は、残念なことに観音殿の宋成を待たずして前年に没したため、観音殿を見ることはなかったが、義政の好きだった洛西の西芳寺(苔寺)にかつてあった瑠璃殿を模して作られた。禅に帰依し、茶道を師事した義政のわび、さびの境地を結晶した建造物と伝わる。 銀閣と呼ばれるだけあって、建物には銀箔が貼られているかと思いきや漆塗りの建物である。 銀箔が貼られていない理由に関しては、 「銀箔を貼る予定だったのが義政が途中で亡くなってしまった」「財政上の理由で銀箔を貼る事ができなかった」「外壁の漆が光の反射で銀色に見える」「義政は茶道を趣味とし禅宗文化に帰依したわびさび人で創建当初から銀箔を貼る計画はしていなかった」など諸説あるが真相は分かっていない。2007年1月に行われた科学的な調査でも銀箔は検出されなかったと発表された。
須弥壇に室町時代の観音菩薩坐像を安置する 上層は唐様仏殿様式の潮音閣(ちょうおんかく)、下層は書院造り(佊宅様式)の心空殿(しんくうでん)と命名された。東の錦鏡池(きんきょうち)にその気品あふれる姿を投影している。唯一現存する室町期の楼閣庭園建築の代表的建造物である。 杮(こけら)葺の屋根には金銅の鳳凰が観音菩薩を守護し、東を向いて羽ばたいている。鳳凰は中国の伝説で丌老丌死、再生の象徴という。
錦境地(きんきょうち)
「わが庵(いほ)は 月待山の麓にて
かたぶく空の影をしぞおもう」 足利義政
東山三十六峰の第10峰の月待山を背にして、銀閣(観音殿)の前にある錦鏡池(きんきょうち)を中心に池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)が広がっている。この庭園は特別史跡、特別名勝にも指定されている景勝地である。 江戸期の都名所図絵には「神仙の術あり」と表現されるほどであるが、かつて義政が洛西の苔寺・夢想疎石作庭の西芳寺の庭園を模したといわれる庭園はすでになく、江戸時代の造園である。かつての作庭には義政が寵愛した山水河原者の善阿弥一族が関わっていた。
現在室町時代の姿をとどめるのは、銀閣と東求堂だけである。


本堂(方丈)前には中国の西湖を模したという銀沙灘(ぎんしゃだん)白砂を壇状にして表面に直線の縞模様を付けられている。と円錐型の向月台(こうげつだい)がある。
銀沙灘は月の光を反射させるためとか、向月台は上に座って背後の月待山に昇る月を眺めたと言われているが、俗説の域を出ていない。現在のような形になったのは江戸後期になってからである。 花頭窓(かとうまど)から、白砂の銀沙灘を眺めるのも一興である。花頭窓とは、鎌倉時代に中国から禅宗建築様式の窓として伝来したもので、窓枠の頭部が花形であるためにそう呼ばれた。
比叡山と大文字山の間では花こう岩を観察することができる。中生代白亜紀にマグマの高熱がまわりの地層を焼き固め、砂岩や泥岩はホルンフェルスという固い石になり、花こう岩は長い年月の間に風化して「白川砂」とよばれる白砂となった。白川の白砂は非常に光の反射率が高く、庭自体光輝いて見えるのだという。 「白川砂」は今では、銀閣寺や龍安寺石庭、法然院(白砂壇)などの京都の寺院になくてはならない砂になっている。


方丈(ほうじょう)(本堂)は江戸中期の建造。ご本尊として釈迦牟尼仏が安置され、正面の額には「東山水上行(とうざんすいじょうこう)」を掲げ、内部には江戸期の南宊画家の巨匠、不謝蕪村(よさぶそん)、池大雅(いけのたいが)の襖絵が所蔵されている。足利義政と正室日野富子の佈牌も安置されている。
方丈とは、禅寺で、佊職の居室。また、佊職そのものこと。
方丈と東求堂の間は短い渡り廊下でつながれ、間には銀閣寺型の手水鉢がある。独特の袈裟(けさ)文様をしている。
手水鉢(ちょうずばち)とは、元来、神前、仏前で口をすすぎ、身を清めるための水を確保するための器をさす。その後、茶の湯にも取り入れられ、露地の中に置かれるようになり、つくばいと呼ばれる独特の様式を形成していった。 江戸時代になり、露地に手水鉢が丌可欠のものと見なされるようになり、天然自然のものを利用したものから、露地の手水鉢の用途のためにデザインされたものが登場するようになった。


国宝・東求堂(とうぐうどう)
観音殿(銀閣)とともに、東山殿造営当時の遺構として現存するのが東求堂(国宝)である。檜皮葺き。近世書院造の現存する最古の遺構である。本来は持仏堂(じぶつどう)、すなわち阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂であった。安置されている室町時代の阿弥陀如来立像は、不願施無畏の来迎印を結ぶ。
内部を四畳、四畳半、六畳の小部屋に仕切ってあって、現在の日本風家屋の原型といわれる。
特に東求堂内の四畳半書院・同仁斎(どうじんさい)は、付書院と違い棚があり、現存するものでは最古の座敷飾りであり、四畳半の間取りの始まりといわれている。現在の書斎であり、茶室でもある。ここで義政は私淑(ひそかに尊敬する)していた夢想疎石の肖像を掲げ、お茶を供していたのだ。
同仁斎とは、平等に仁愛を施すとの意味がある。


庭園は上下二段に大別され、上段は枯山水庭園、下段は池泉回遊式庭園となっており、四方正面の庭ともいわれる。 中央の錦鏡池には仙人洲に迎仙橋、白鶴(はっかく)島が造られ、鶴の両翼を表す仙桂橋(せんけいきょう)、仙袖橋(せんしゅうきょう)が架けられている。さらに、西から分界橋、濯錦橋(たっきんきょう)、龍背橋、臥雲橋など名石による七つの橋が配され、石橋の庭ともなっている。池には、北斗石、浮石、大内政弘寄進による大内石、坐禅石などの名石が据えられ、当初は蓮が植えられていた。
洗月泉は、錦鏡池南東端に落ちる滝、山部山畔から流れ落ちる水を銀閣・東求堂のある下段の錦鏡池へ導いている。 洗月泉は水面(みずも)に映る月をさざ波で洗うと云われている。
洗月泉から東部の山腹をさかのぼると湧水、お茶の五(相君泉)がある。足利義政が愛用したといわれる名水である。水質が豊かで500年以上も涸れることなく涌きだしている。現在も飲料水として使用されているのだとか。この石組は、後の世の蹲踞(つくばい)の原型になったともいわれる。
茶の湯には、朝早く名水をたずねて汲み帰り、それを使って客をもてなす「名水点」というお点前(おてまえ)がある。今でも三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)などのお茶会で使われることもあるのだとか。
お茶の五の左上にある漱蘇亭(そうせんてい)跡付近の珍しい石組みは、苔寺に模して滝から水が滔々(とうとう)として流れる様を枯山水の石組みを表現したものと云われる。

山を登りきると、吉田山と連なる黒谷を借景にして、庭園と銀閣全体、京の街なみが見渡せる絶景ポイントに到着する。記念撮影に人気のビュースポットだ。銀閣の背後に東山の街並みが浮かび、さらにその後方に衣笠山や左大文字が見える。
天候が良ければ、遠くに金閣寺のまばゆい光がきらっと光りを放つ。この場所は、銀閣が金閣と対峙しているのが良く分かる。
室町幕府三代の財政上も豊かな安定期に造られ、華やかな装いの金閣に対して、戦国時代の幕開け間近な財政丌安定期で、わびさびの萌芽の時代の銀閣と対比してみよう。
銀閣寺の造営費用は、諸国荘園、守護から徴収されようとしたが拒否され、山城国内の荘園領为に費用と人夫を毎年課した。社会の混乱、重税などに対して、山城国一揆(1485)も起こる。それでも、造営が中止されることはなかったという。

出口付近で裏側から銀閣が間近に見学できる。高さが随分と佉いように感じるが、当時の男子の平均身長が150センチに満たないと言われており、頷けるところもある。
また杮ぶき(こけらぶき)の模型も展示されている。参考にしよう。銀閣などの杮ぶき(こけら・木片、木くずのこと)とは文字通り杮板(こけらいた)で屋根を葺くこと。板厚が2~3ミリの最も薄い板を用いる。
ちなみに東求堂などの檜皮葺 (ひわだぶき)とは、ヒノキの樹皮を用いて施工される。
最後にみやげもの屋の前の東司の扁額のかかる建物、東司(とうす)とはトイレのことである。 終わり。
2011年02月14日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・三十三間堂
平安後期、第77代天皇として即位した後白河天皇は、わずか3年で二条天皇に位を譲って以後、上皇として「院政」を行った。約30年の間、院政を行った後白河上皇が、法住寺殿(ほうじゅうじどの)と呼ばれる院御所内に、当時、権勢を誇った平清盛に命じて創建させたのが三十三間堂である。
当時は、他に五重塔、不動堂などの諸堂を整備し、北は七条通、南は泉湧寺通り、西は大和大路通り、東は東山山麓付近までの広大な地域をしめていた。
その後、焼失、再建、修復を繰り返され、桃山時代には、天下人となった豊臣秀吉が、大仏殿方広寺を三十三間堂の北隣に造営し、堂や後白河上皇の御陵をも、その境内に取り込んで土塀を築いたことから、再び歴史の舞台へと引きずり出されることとなった。秀吉没後は、天台宗妙法院の管理下に置かれている。
現在、周辺には、妙法院、智積院、養源院、豊国神社、方広寺、耳塚、七条仏所跡、正面通りと貴重な文化遺産や当時の歴史を物語る曰くのある寺社などがあり、一大観光スポットとなっている。

国宝 三十三間堂
開門時間 8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)
駐車場は、東門から警備員の誘導に従って入場する。拝観券売り場の前が無料駐車場となっている。
妙法院を本坊とする蓮華王院の本堂が通称「三十三間堂」と呼ばれる。南北にのびる内陣の柱間が三十三あるからである。
ちなみに三十三という数字は、観音菩薩は、苦難に遭遇している数多の衆生を救うために、相手に応じて 三十三の姿に変化するからだ。柱間の数もこれにあわせたもので、また観音霊場が三十三所となっているのもこれによる。
奥行き22m、地上16m、南北120m、入母屋造り本瓦葺き。

基礎地盤には、砂と粘土を層状に堆積して地震時の地下震動を吸収する「版築・はんちく」を用い、堂内の屋台骨は、柱間を2本の梁でつなぐ「二重虹梁・にじゅうこうりょう」とし、外屋の上部も内・外柱に二重の梁をかけて堅固に造られている。
構架材の柱や長押、梁は地震や災害などの「揺れ」を予測しており、土壁面積を極力小さくした上で、溝を切った柱に板壁として横板を落し込む「羽目板・はめいた」がなされ、本堂は波に揺れて浮ぶ筏のごとく揺れを吸収する免震工法が施こされている。

三十三間堂発行絵葉書より
重文 千体千手観音立像 (せんたいせんじゅかんのんりゅうぞう)
前後10列の階段状の壇上に、等身大の1000体の観音立像が整然と並ぶ。各像は、頭上に十一の顔と両脇に四十手をもつ通形で、中尊の千手千眼観音坐像と同様の造像法で作られている。
124体は平安期の尊像で本堂焼失の際にも難を逃れた。その他が、鎌倉期にかけて再興された像である。
約500体には作者名が残され、運慶、快慶を輩出した慶派をはじめ、院派、円派も含め、国家的規模で70人もの、仏所の仏師たちが名を連ねる。166㎝前後の寄木造である。
観音像の中には、すでにこの世にいない人のうち、会いたい人に似た像が必ずあるとも伝えられている。

三十三間堂発行絵葉書より

三十三間堂発行絵葉書より
風神・雷神
観音二十八部衆に風神・雷神を加えた30体の等身大の尊像が千体観音像の前に安置されている。
古代インドに起源をもつ神々で千手観音に従って仏教と、その信者を守るとされる。天衣の女神や甲冑をつけた神将、動物や楽器を神格化したものなど変化に富む。
これらは、檜材の寄木造り、玉眼を用いた彩色像で、鎌倉彫刻の傑作である。
風神と雷神は インド最古の聖典とされる「リグ・ヴェーダ」に登場する神々である。その名が示すように風と雷を神格化したもの。風の袋を両肩に回し担いだ風神は、「ヴァーユ」と呼ばれ、馬車で天を駆け、悪神を追い払い、人々に富と名誉を授ける神とされている。後背に小太鼓の輪を担いだ雷神は、「ヴァルナ」という水の神である。
仏教では、仏法を守り、悪をこらしめ、善を勧めて風雨を調(ととのえる)神だと信じられているのだとか。俵屋宗達が描いた風神雷神図屏風はこれがモデルと言われる。



三十三間堂発行絵葉書より
国宝 千手観音坐像(こくほう せんじゅかんのんざぞう)
左右の千手観音立像や二十八部衆の中央に安置されているのが、中尊と呼ばれる丈六の坐像、千手観音坐像である。
像高が3メートル余、檜材の寄木造りで全体に漆箔が施されている。
十一面四十二臂 (手)の通例の像形で、鎌倉期の再建時に、大仏師・湛慶(たんけい)が、84歳で没する2年前に慶派の弟子たちを率いて完成させたものだ。鎌倉後期の代表的作品である。
温雅な表情 像の均整が保たれ、重厚感ののある尊顔は湛慶の特徴的作風とされ、観音の慈徳を余すところ無く表現するという。
42本の手の内2本は胸前で合掌し、他の2本は腹前で組み合わせて宝鉢(ほうはつ)を持つ(宝鉢手)。他の38本の脇手にはそれぞれ法輪、錫杖(しゃくじょう)、水瓶(すいびょう)など様々な持物(じもつ)を持つ。
千手観音のはなし
「十一面千手観音」「千手千眼(せんげん)観音」「十一面千手千眼観音」「千手千臂(せんぴ)観音)」など様々な呼び方がある。観音菩薩の変化身である。
観音とは 「遠くの音を聞く」 という意味であり、遠くというのは、物理的距離を指すのではなく、ありとあらゆる次元、人の心の奥や、物事の真実を観るという意味である。 したがって「千手千眼」の名は、千本の手のそれぞれの掌に一眼をもつとされ、千本の手は、すべてを見通し、どのような衆生をも漏らさず救済しようとする、観音の慈悲と力の広大さを表している。
密教の曼荼羅では観音像は「蓮華部」に分類されている。千手観音を「蓮華王」とも称するのは観音の王であるとの意味で、蓮華王院(京都の三十三間堂の正式名称)の名はこれに由来する。
坐像、立像ともにあり、実際に千本の手を表現した作例もあるが、十一面四十二臂(手)にて千手を表現するものが一般的である 。
胸前で合掌する2本の手を除いた40本の手が、それぞれ25の世界を救うものであり、「25×40=1,000」であると説明されている。「25の世界」とは、天上界から地獄まで25の世界があるという仏教の「三界二十五有(う)」のこと。
ちなみに俗に言う「有頂天」とは二十五の有の頂点にある天上界のことを指すという。

四天王のはなし
三十三間堂の千手観音を始め、釈迦三尊像など本尊の尊名に関係なく 、メインとなる仏像の置かれる須弥壇の四隅には、たいてい邪鬼を踏みしめて立つ四天王像が配置されている。
須弥山の頂上の宮殿に住む帝釈天の部下として、自身も龍神、夜叉、羅刹を始めとする多数の眷属 (けんぞく・配下)を従えて四方の門を守っている。
東・持国天、南・増長天、西・広目天、北・多聞天(毘沙門天)を固める方位の守護神 である。(とんなんしゃぺじぞうこうたと覚えよう)持物は様々であり剣・鉾・戟・宝塔・宝棒等を持つが広目天は巻子と筆を、多聞天は宝塔を持つ場合が多い 。
太閤秀吉と三十三間堂

当時、交通の要所だったこの地に目を向け、後白河院や清盛の栄華にあやかろうと思い立った秀吉は、その権勢を天下に誇示するため(諸説ある・注1)奈良大仏を模した大仏殿方広寺を三十三間堂の北隣に造営し、本堂や後白河上皇の御陵をも、その境内に取り込んで土塀を築いた。今も、その遺構として南大門・太閤塀(ともに重要文化財)が残る。
本堂の修理も千体仏をはじめとして念入りに遂行され、その意志を継いだ秀頼の代まで続いた。大仏殿は、文禄4年(1595)9月に完成し、千人の僧侶により落慶供養されたという。 秀吉は、死後「豊国大明神・とよくにだいみょうじん」という神格として祀られ、三十三間堂東隣の阿弥ケ峯には壮麗な社殿が造営された。
注1、惣無事令(そうぶじれい)において大名間の私闘を禁じ、刀狩と太閤検地、海賊禁止令などで農村部他の武装を解き、統制を敷いた秀吉は天下支配の手段として宗教統制にものりだした。当時、奈良の大仏は再建されておらず、秀吉は京の都に諸宗の中枢となるべき大仏殿を築き、その千僧供養においては、主たる宗派からは百人ずつ、千人の僧を出仕させ、忠節の値踏みとしたのである。
これにより比叡山や本願寺を徹底的に攻撃し武装解除した信長を引き継ぎ、金剛峯寺(木食応其の斡旋)、根来寺(攻撃)を武装解除した秀吉がさらに宗教勢力の牙を抜いて、天下人秀吉の前に屈伏させたと言われる。

通し矢と矢数帳
いつごろから始まったのかは分かっていない。桃山時代には、すでに行なわれたと伝えられる。
「通し矢・とおしや」は、本堂西縁の南端から120メートルの距離を弓で射通し、その矢数を競ったもので、矢数をきめて的中率を競う「百射」「千射」等があった。今でも、当時の矢傷を庇や柱に見ることができる。
江戸時代になると、殊に町衆に人気を博したのが、夕刻に始めて翌日の同刻まで、一昼夜に何本通るかを競う「大矢数・おおやかず」で、御三家の尾張藩と紀州藩による功名争いは、さらに人気に拍車をかけ、京都の名物行事となった。
「矢数帳」には、通し矢法を伝承した〈日置六流・へきろくりゅう〉の江戸期の試技者氏名、月日、矢数などが編年で書き留められており、最高記録は、貞享3年(1686)4月、紀州・和佐大八郎(試技年齢は18歳という)の総矢13,053本、通し矢8,133本であったという。仏像群の裏側の通路には、大きな扁額が展示されている。
現在、毎年の成人の日には、全国の新成人によって弓道大会が行われている。

方広寺大仏殿跡公園 方広寺の裏側
天正14年(1586年)、豊臣秀吉は奈良の東大寺にならって大仏の建立を計画し、大仏殿と大仏の造営を始めた。大仏殿は2000年の発掘調査により東西約55m、南北約90mの規模であったことが判明している。現在その場所は公園となっている。
文禄4年(1595年)、大仏殿がほぼ完成し、高さ約19メートルの木製金漆塗坐像大仏が安置された。しかし、慶長元年(1596年)に起きた大地震により、開眼前の大仏は倒壊した。 慶長3年(1598年)、秀吉は法要を待たずに死去し、同年、大仏の無い大仏殿で開眼法要が行われた。
境内は、現在の方広寺境内のみならず、豊国神社、京都国立博物館、三十三間堂を含む、広大なものであったという。

正面通の分断
豊臣秀吉は、没後、神格化されるために、阿弥陀が峰に西向きに豊国廟(秀吉の墓)を建てさせ、そこから真西に向かって、ふもとに豊国神社、その西に、淀君との最初の子で早世した 鶴松を祀った祥雲寺、その西に、方広寺大仏殿、さらに真西に向かったところに、本願寺に土地を与えて、西向きに阿弥陀堂を建てさせ、一直線上に配置した。正面通は、方広寺から、鴨川の正面橋を渡り、本願寺まで続いていた。
徳川家康は、豊臣秀吉の神格化をふせぐために、豊国廟、豊国神社を壊滅させ、参道をふさぐように新日吉神宮を建てさせ、祥雲寺を、秀吉が壊滅した根来寺由来の智積院に与え、方広寺は妙法院の管理とした。さらに、方広寺と本願寺の間には、かつて秀吉が隠居させた教如に東本願寺を創建させ、本願寺を分裂し、東向きに阿弥陀堂を建てさせた。さらにその間に、東本願寺に土地を与え、渉成苑を建てさせたのである。
秀吉が神となって西方浄土へ赴く、また衆生が秀吉を参拝するとされた、豊国廟から本願寺の直線を、ことごとく分断したのはやはり家康であった。
しかし、江戸時代中期頃になってから、方広寺から西本願寺へ向かうこの道が「正面通」と称されるようになった。

方広寺銘鐘事件
慶長19年(1614年)、豊臣家が再建していた京都の方広寺大仏殿はほぼ完成し、梵鐘も完成した。総奉行の片桐且元は、梵鐘の銘文を南禅寺の文英清韓に選定させた。
家康は家臣の本多正純を通じて、梵鐘銘文の文中に不吉な語句があるとして、大仏供養を延期させた。家康は五山の僧(金地院崇伝ら)や林羅山に鐘銘文を解読させる。崇伝らは、文中に「国家安康」「君臣豊楽」とあったものを、「国家安康」は家康の諱を分断し、「君臣豊楽」は豊臣家の繁栄を願い徳川家に対する呪詛が込められていると断定した。
この後、大坂夏の陣にて豊臣家は滅亡する。この事件は、豊臣家攻撃の口実とするため、家康が崇伝らと画策して問題化させたものであるとの考え方が一般的である。


智 積 院
真言宗智山派の総本山である。阿弥陀ヶ峰を背景にして、諸堂伽藍立ち並ぶ 。
智積院には、桃山時代に長谷川等伯とその弟子達によって描かれ、祥雲禅寺の客殿を飾っていた金碧障壁画が残され「楓図」「桜図」「松と葵の図」「松に秋草図」は国宝である。
また、大書院東側の名勝庭園は、桃山時代に造られた庭園で、中国の廬山を形どって作られた利休好みの庭である。豊臣秀吉が建立した祥雲禅寺(智積院の前身の寺)時代に原形が造られた。
大書院はこの庭園に面して建ち、平安期の寝殿造りの釣殿のように、庭園の池が書院の縁の下に入り込んでいる。その大書院より眺める庭園は、四季折々の美しさ特に、ツツジの花の咲く5月下旬から6月下旬にかけて一段と華やぐ。
智積院は、鎌倉時代の中頃に、高野山から分かれた根来寺の塔頭(たっちゅう)寺院のなかの学頭寺院であった。
織豊時代、豊臣秀吉と対立することとなり、秀吉の軍勢により、根来山内の堂塔のほとんどが灰燼に帰す。その時、智積院の住職であった玄宥(げんゆう)僧正は、難を京都洛北に逃れた。
慶長6年(1601)、今度は徳川家康の命により、玄宥僧正に東山の豊国神社境内の坊舎と土地が与えられ、智積院が再興された。その後、秀吉が夭折した鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲禅寺を拝領し、境内伽藍が拡充された。再興された智積院の正式の名称は「五百佛山(いおぶさん)根来寺智積院」という。

耳塚 豊国神社門前にある史跡で鼻塚とも呼ばれる。
豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)戦功の証として討ち取った、2万人分の朝鮮・明国兵の耳や鼻を持ち帰ったものを葬った塚。古墳状の盛り土をした上に五輪塔が建てられ周囲は石柵で囲まれている。
当時は戦功の証として、敵の高級将校は死体の首をとって検分したが、一揆や足軽など身分の低いものは鼻(耳)でその数を証した。検分が終われれば、戦没者として供養しその霊の災禍を防ぐのが古来よりの日本の慣習であった。

七条仏所跡 河原町七条西入南側
平安時代中期の仏師(仏像彫刻家)定朝(じょうちょう)をはじめ、その一族・子孫(慶派)が居住して仏像製作をした「仏所」のあったところ。鎌倉時代に入って、この仏所から運慶、湛慶(たんけい)快慶ら相ついであらわれ、戦国時代には信長木像(大徳寺総見院)を造った康清などがいた。しかし、この仏所も21代康正のとき、豊臣秀吉の命で四条烏丸に移転した。その後、幕末の兵乱に火災にあい仏所の遺構は完全に失われた。
養源院
淀殿が創建して、江が再建した、豊臣ゆかりで徳川の菩提所である。蓮華王院(三十三間堂)の東向かいに位置する。
寺名は浅井長政の院号から採られた。秀吉の側室・淀殿が長政の供養のために成伯法印(長政の従弟で比叡山の僧)を開山として創建。その後、火災により焼失するが、今度は、徳川秀忠の正室・崇源院(江)の願により再興された。以後、徳川家の菩提所となった。 本堂は伏見城の移築、鳥居元忠以下の血天井もある。
当時は、他に五重塔、不動堂などの諸堂を整備し、北は七条通、南は泉湧寺通り、西は大和大路通り、東は東山山麓付近までの広大な地域をしめていた。
その後、焼失、再建、修復を繰り返され、桃山時代には、天下人となった豊臣秀吉が、大仏殿方広寺を三十三間堂の北隣に造営し、堂や後白河上皇の御陵をも、その境内に取り込んで土塀を築いたことから、再び歴史の舞台へと引きずり出されることとなった。秀吉没後は、天台宗妙法院の管理下に置かれている。
現在、周辺には、妙法院、智積院、養源院、豊国神社、方広寺、耳塚、七条仏所跡、正面通りと貴重な文化遺産や当時の歴史を物語る曰くのある寺社などがあり、一大観光スポットとなっている。

国宝 三十三間堂
開門時間 8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)
駐車場は、東門から警備員の誘導に従って入場する。拝観券売り場の前が無料駐車場となっている。
妙法院を本坊とする蓮華王院の本堂が通称「三十三間堂」と呼ばれる。南北にのびる内陣の柱間が三十三あるからである。
ちなみに三十三という数字は、観音菩薩は、苦難に遭遇している数多の衆生を救うために、相手に応じて 三十三の姿に変化するからだ。柱間の数もこれにあわせたもので、また観音霊場が三十三所となっているのもこれによる。
奥行き22m、地上16m、南北120m、入母屋造り本瓦葺き。
基礎地盤には、砂と粘土を層状に堆積して地震時の地下震動を吸収する「版築・はんちく」を用い、堂内の屋台骨は、柱間を2本の梁でつなぐ「二重虹梁・にじゅうこうりょう」とし、外屋の上部も内・外柱に二重の梁をかけて堅固に造られている。
構架材の柱や長押、梁は地震や災害などの「揺れ」を予測しており、土壁面積を極力小さくした上で、溝を切った柱に板壁として横板を落し込む「羽目板・はめいた」がなされ、本堂は波に揺れて浮ぶ筏のごとく揺れを吸収する免震工法が施こされている。

三十三間堂発行絵葉書より
重文 千体千手観音立像 (せんたいせんじゅかんのんりゅうぞう)
前後10列の階段状の壇上に、等身大の1000体の観音立像が整然と並ぶ。各像は、頭上に十一の顔と両脇に四十手をもつ通形で、中尊の千手千眼観音坐像と同様の造像法で作られている。
124体は平安期の尊像で本堂焼失の際にも難を逃れた。その他が、鎌倉期にかけて再興された像である。
約500体には作者名が残され、運慶、快慶を輩出した慶派をはじめ、院派、円派も含め、国家的規模で70人もの、仏所の仏師たちが名を連ねる。166㎝前後の寄木造である。
観音像の中には、すでにこの世にいない人のうち、会いたい人に似た像が必ずあるとも伝えられている。

三十三間堂発行絵葉書より
三十三間堂発行絵葉書より
風神・雷神
観音二十八部衆に風神・雷神を加えた30体の等身大の尊像が千体観音像の前に安置されている。
古代インドに起源をもつ神々で千手観音に従って仏教と、その信者を守るとされる。天衣の女神や甲冑をつけた神将、動物や楽器を神格化したものなど変化に富む。
これらは、檜材の寄木造り、玉眼を用いた彩色像で、鎌倉彫刻の傑作である。
風神と雷神は インド最古の聖典とされる「リグ・ヴェーダ」に登場する神々である。その名が示すように風と雷を神格化したもの。風の袋を両肩に回し担いだ風神は、「ヴァーユ」と呼ばれ、馬車で天を駆け、悪神を追い払い、人々に富と名誉を授ける神とされている。後背に小太鼓の輪を担いだ雷神は、「ヴァルナ」という水の神である。
仏教では、仏法を守り、悪をこらしめ、善を勧めて風雨を調(ととのえる)神だと信じられているのだとか。俵屋宗達が描いた風神雷神図屏風はこれがモデルと言われる。


三十三間堂発行絵葉書より
国宝 千手観音坐像(こくほう せんじゅかんのんざぞう)
左右の千手観音立像や二十八部衆の中央に安置されているのが、中尊と呼ばれる丈六の坐像、千手観音坐像である。
像高が3メートル余、檜材の寄木造りで全体に漆箔が施されている。
十一面四十二臂 (手)の通例の像形で、鎌倉期の再建時に、大仏師・湛慶(たんけい)が、84歳で没する2年前に慶派の弟子たちを率いて完成させたものだ。鎌倉後期の代表的作品である。
温雅な表情 像の均整が保たれ、重厚感ののある尊顔は湛慶の特徴的作風とされ、観音の慈徳を余すところ無く表現するという。
42本の手の内2本は胸前で合掌し、他の2本は腹前で組み合わせて宝鉢(ほうはつ)を持つ(宝鉢手)。他の38本の脇手にはそれぞれ法輪、錫杖(しゃくじょう)、水瓶(すいびょう)など様々な持物(じもつ)を持つ。
千手観音のはなし
「十一面千手観音」「千手千眼(せんげん)観音」「十一面千手千眼観音」「千手千臂(せんぴ)観音)」など様々な呼び方がある。観音菩薩の変化身である。
観音とは 「遠くの音を聞く」 という意味であり、遠くというのは、物理的距離を指すのではなく、ありとあらゆる次元、人の心の奥や、物事の真実を観るという意味である。 したがって「千手千眼」の名は、千本の手のそれぞれの掌に一眼をもつとされ、千本の手は、すべてを見通し、どのような衆生をも漏らさず救済しようとする、観音の慈悲と力の広大さを表している。
密教の曼荼羅では観音像は「蓮華部」に分類されている。千手観音を「蓮華王」とも称するのは観音の王であるとの意味で、蓮華王院(京都の三十三間堂の正式名称)の名はこれに由来する。
坐像、立像ともにあり、実際に千本の手を表現した作例もあるが、十一面四十二臂(手)にて千手を表現するものが一般的である 。
胸前で合掌する2本の手を除いた40本の手が、それぞれ25の世界を救うものであり、「25×40=1,000」であると説明されている。「25の世界」とは、天上界から地獄まで25の世界があるという仏教の「三界二十五有(う)」のこと。
ちなみに俗に言う「有頂天」とは二十五の有の頂点にある天上界のことを指すという。

四天王のはなし
三十三間堂の千手観音を始め、釈迦三尊像など本尊の尊名に関係なく 、メインとなる仏像の置かれる須弥壇の四隅には、たいてい邪鬼を踏みしめて立つ四天王像が配置されている。
須弥山の頂上の宮殿に住む帝釈天の部下として、自身も龍神、夜叉、羅刹を始めとする多数の眷属 (けんぞく・配下)を従えて四方の門を守っている。
東・持国天、南・増長天、西・広目天、北・多聞天(毘沙門天)を固める方位の守護神 である。(とんなんしゃぺじぞうこうたと覚えよう)持物は様々であり剣・鉾・戟・宝塔・宝棒等を持つが広目天は巻子と筆を、多聞天は宝塔を持つ場合が多い 。
太閤秀吉と三十三間堂
当時、交通の要所だったこの地に目を向け、後白河院や清盛の栄華にあやかろうと思い立った秀吉は、その権勢を天下に誇示するため(諸説ある・注1)奈良大仏を模した大仏殿方広寺を三十三間堂の北隣に造営し、本堂や後白河上皇の御陵をも、その境内に取り込んで土塀を築いた。今も、その遺構として南大門・太閤塀(ともに重要文化財)が残る。
本堂の修理も千体仏をはじめとして念入りに遂行され、その意志を継いだ秀頼の代まで続いた。大仏殿は、文禄4年(1595)9月に完成し、千人の僧侶により落慶供養されたという。 秀吉は、死後「豊国大明神・とよくにだいみょうじん」という神格として祀られ、三十三間堂東隣の阿弥ケ峯には壮麗な社殿が造営された。
注1、惣無事令(そうぶじれい)において大名間の私闘を禁じ、刀狩と太閤検地、海賊禁止令などで農村部他の武装を解き、統制を敷いた秀吉は天下支配の手段として宗教統制にものりだした。当時、奈良の大仏は再建されておらず、秀吉は京の都に諸宗の中枢となるべき大仏殿を築き、その千僧供養においては、主たる宗派からは百人ずつ、千人の僧を出仕させ、忠節の値踏みとしたのである。
これにより比叡山や本願寺を徹底的に攻撃し武装解除した信長を引き継ぎ、金剛峯寺(木食応其の斡旋)、根来寺(攻撃)を武装解除した秀吉がさらに宗教勢力の牙を抜いて、天下人秀吉の前に屈伏させたと言われる。
通し矢と矢数帳
いつごろから始まったのかは分かっていない。桃山時代には、すでに行なわれたと伝えられる。
「通し矢・とおしや」は、本堂西縁の南端から120メートルの距離を弓で射通し、その矢数を競ったもので、矢数をきめて的中率を競う「百射」「千射」等があった。今でも、当時の矢傷を庇や柱に見ることができる。
江戸時代になると、殊に町衆に人気を博したのが、夕刻に始めて翌日の同刻まで、一昼夜に何本通るかを競う「大矢数・おおやかず」で、御三家の尾張藩と紀州藩による功名争いは、さらに人気に拍車をかけ、京都の名物行事となった。
「矢数帳」には、通し矢法を伝承した〈日置六流・へきろくりゅう〉の江戸期の試技者氏名、月日、矢数などが編年で書き留められており、最高記録は、貞享3年(1686)4月、紀州・和佐大八郎(試技年齢は18歳という)の総矢13,053本、通し矢8,133本であったという。仏像群の裏側の通路には、大きな扁額が展示されている。
現在、毎年の成人の日には、全国の新成人によって弓道大会が行われている。
方広寺大仏殿跡公園 方広寺の裏側
天正14年(1586年)、豊臣秀吉は奈良の東大寺にならって大仏の建立を計画し、大仏殿と大仏の造営を始めた。大仏殿は2000年の発掘調査により東西約55m、南北約90mの規模であったことが判明している。現在その場所は公園となっている。
文禄4年(1595年)、大仏殿がほぼ完成し、高さ約19メートルの木製金漆塗坐像大仏が安置された。しかし、慶長元年(1596年)に起きた大地震により、開眼前の大仏は倒壊した。 慶長3年(1598年)、秀吉は法要を待たずに死去し、同年、大仏の無い大仏殿で開眼法要が行われた。
境内は、現在の方広寺境内のみならず、豊国神社、京都国立博物館、三十三間堂を含む、広大なものであったという。
正面通の分断
豊臣秀吉は、没後、神格化されるために、阿弥陀が峰に西向きに豊国廟(秀吉の墓)を建てさせ、そこから真西に向かって、ふもとに豊国神社、その西に、淀君との最初の子で早世した 鶴松を祀った祥雲寺、その西に、方広寺大仏殿、さらに真西に向かったところに、本願寺に土地を与えて、西向きに阿弥陀堂を建てさせ、一直線上に配置した。正面通は、方広寺から、鴨川の正面橋を渡り、本願寺まで続いていた。
徳川家康は、豊臣秀吉の神格化をふせぐために、豊国廟、豊国神社を壊滅させ、参道をふさぐように新日吉神宮を建てさせ、祥雲寺を、秀吉が壊滅した根来寺由来の智積院に与え、方広寺は妙法院の管理とした。さらに、方広寺と本願寺の間には、かつて秀吉が隠居させた教如に東本願寺を創建させ、本願寺を分裂し、東向きに阿弥陀堂を建てさせた。さらにその間に、東本願寺に土地を与え、渉成苑を建てさせたのである。
秀吉が神となって西方浄土へ赴く、また衆生が秀吉を参拝するとされた、豊国廟から本願寺の直線を、ことごとく分断したのはやはり家康であった。
しかし、江戸時代中期頃になってから、方広寺から西本願寺へ向かうこの道が「正面通」と称されるようになった。

方広寺銘鐘事件
慶長19年(1614年)、豊臣家が再建していた京都の方広寺大仏殿はほぼ完成し、梵鐘も完成した。総奉行の片桐且元は、梵鐘の銘文を南禅寺の文英清韓に選定させた。
家康は家臣の本多正純を通じて、梵鐘銘文の文中に不吉な語句があるとして、大仏供養を延期させた。家康は五山の僧(金地院崇伝ら)や林羅山に鐘銘文を解読させる。崇伝らは、文中に「国家安康」「君臣豊楽」とあったものを、「国家安康」は家康の諱を分断し、「君臣豊楽」は豊臣家の繁栄を願い徳川家に対する呪詛が込められていると断定した。
この後、大坂夏の陣にて豊臣家は滅亡する。この事件は、豊臣家攻撃の口実とするため、家康が崇伝らと画策して問題化させたものであるとの考え方が一般的である。

智 積 院
真言宗智山派の総本山である。阿弥陀ヶ峰を背景にして、諸堂伽藍立ち並ぶ 。
智積院には、桃山時代に長谷川等伯とその弟子達によって描かれ、祥雲禅寺の客殿を飾っていた金碧障壁画が残され「楓図」「桜図」「松と葵の図」「松に秋草図」は国宝である。
また、大書院東側の名勝庭園は、桃山時代に造られた庭園で、中国の廬山を形どって作られた利休好みの庭である。豊臣秀吉が建立した祥雲禅寺(智積院の前身の寺)時代に原形が造られた。
大書院はこの庭園に面して建ち、平安期の寝殿造りの釣殿のように、庭園の池が書院の縁の下に入り込んでいる。その大書院より眺める庭園は、四季折々の美しさ特に、ツツジの花の咲く5月下旬から6月下旬にかけて一段と華やぐ。
智積院は、鎌倉時代の中頃に、高野山から分かれた根来寺の塔頭(たっちゅう)寺院のなかの学頭寺院であった。
織豊時代、豊臣秀吉と対立することとなり、秀吉の軍勢により、根来山内の堂塔のほとんどが灰燼に帰す。その時、智積院の住職であった玄宥(げんゆう)僧正は、難を京都洛北に逃れた。
慶長6年(1601)、今度は徳川家康の命により、玄宥僧正に東山の豊国神社境内の坊舎と土地が与えられ、智積院が再興された。その後、秀吉が夭折した鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲禅寺を拝領し、境内伽藍が拡充された。再興された智積院の正式の名称は「五百佛山(いおぶさん)根来寺智積院」という。
耳塚 豊国神社門前にある史跡で鼻塚とも呼ばれる。
豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)戦功の証として討ち取った、2万人分の朝鮮・明国兵の耳や鼻を持ち帰ったものを葬った塚。古墳状の盛り土をした上に五輪塔が建てられ周囲は石柵で囲まれている。
当時は戦功の証として、敵の高級将校は死体の首をとって検分したが、一揆や足軽など身分の低いものは鼻(耳)でその数を証した。検分が終われれば、戦没者として供養しその霊の災禍を防ぐのが古来よりの日本の慣習であった。
七条仏所跡 河原町七条西入南側
平安時代中期の仏師(仏像彫刻家)定朝(じょうちょう)をはじめ、その一族・子孫(慶派)が居住して仏像製作をした「仏所」のあったところ。鎌倉時代に入って、この仏所から運慶、湛慶(たんけい)快慶ら相ついであらわれ、戦国時代には信長木像(大徳寺総見院)を造った康清などがいた。しかし、この仏所も21代康正のとき、豊臣秀吉の命で四条烏丸に移転した。その後、幕末の兵乱に火災にあい仏所の遺構は完全に失われた。
養源院
淀殿が創建して、江が再建した、豊臣ゆかりで徳川の菩提所である。蓮華王院(三十三間堂)の東向かいに位置する。
寺名は浅井長政の院号から採られた。秀吉の側室・淀殿が長政の供養のために成伯法印(長政の従弟で比叡山の僧)を開山として創建。その後、火災により焼失するが、今度は、徳川秀忠の正室・崇源院(江)の願により再興された。以後、徳川家の菩提所となった。 本堂は伏見城の移築、鳥居元忠以下の血天井もある。
2011年02月01日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・伏見稲荷大社
東山三十六峰の最南端に位置する稲荷山に鎮座するのが、伏見稲荷大社である。全国に四万社近くある稲荷社の総本宮だ。「病弘法、欲稲荷」ということわざがある。病気のことなら弘法大師、金儲けのことならお稲荷さんにという意味 だ。
奈良時代に、秦氏が稲荷山に奉った神が始まりとされ、稲荷山の山上山下の一帯が稲荷信仰の原域 、御神体である。伏見稲荷の祭神は宇迦之御魂神、五穀豊穣の穀物の神である。五柱を奉る。
稲荷の語源は稲が成る(稲成)から来ており、元々は五穀豊穣を願う農耕の神。今でも田植え神事などが引き継がれている。後に米が商取り引きの中心になり、石高で流通価値を表すようになっていった経過から、商売繁盛の神としても崇められていくようになる。
深草の里が早くから開拓されて、人の住むところであったことは深草弥生遺跡に見ることができる。ここへ秦氏族が住みつき、在地の小豪族として勢力を伸ばしていったと考えられている。
駐車場は師団街道稲荷新道から東に、京阪伏見稲荷駅を越えて、稲荷大社の総門をくぐった社務所前、参集殿あたりに数箇所隣接している。参集殿は宿泊、食事なども行える。
「『山城国風土記』の逸文によると、古くからこの地域に住んで、一族が繁栄を極めていた秦氏の長者・伊呂具(いろぐ)は、和銅四年(711)2月初午の日、驕富(きょうふ)におごって餅を的にして矢を射たところ、的はたちまち白鳥と化して飛びたち、後ろの山の三ヶ峯の頂上にとどまった。するとそこにたちまち「稲が奈利生(なりお)う」という奇瑞がおこり、その後は、秦氏の家運が傾きはじめたので、伊呂具は驕慢(きょうまん)の心を悔いて杉を神木として稲の精霊を祀り、再び家運を挽回することが出来た。
この霊験のあらたかさに感じて、この精霊を「稲成(いなり)の神」と崇め、山を神山(こうやま)として崇め、元明天皇の和銅4年(711)に、その麓に社殿を営むことになった。そして伊呂具の後裔にあたる秦忌寸(はたのいみき)の一統が代々祖神祭祀の聖地として祭祀にたずさわってきたのである。」
http://www.fusimi-inari.com/store/map01.asp
「伏見稲荷参道商店街」のウェブガイド」

京阪電車の伏見稲荷駅からして稲荷色だ。駅のイメージが、あの鳥居の朱色なのである。朱(あか)は魔よけの色である。元来、稲荷の鳥居は社殿と同じく「稲荷塗」といわれ、朱をもって彩色するのが慣習となっています。ちなみにJR稲荷から続くのが表参道、京阪から続くのが裏参道である。参道には稲荷らしいお土産物店が並ぶ。伏見人形、稲荷寿司、キツネの煎餅、びっくりするのはスズメ、ウズラの姿焼き。

深草は、良土を産出し、古くから土人形のふるさとと言われる。(5世紀中ごろから7世紀前半)土器が造られ、土師部(はじべ‐埴輪や土器を造る職人)が、奈良の菅原(西大寺の南)から移住した記録があり、遺跡も発掘された。さらに、豊臣秀吉の伏見城建造時(1594年)、播州(今の兵庫県)などから瓦を造る人々が深草に移り住んだ。
これらの人々から伏見人形が起こった。伏見人形(稲荷人形・深草人形)は、日本各地の土人形・郷土玩具の原型となった。
「饅頭食い人形」は、ある人が幼児に「お父さんとお母さんどちらが大切か」と問うたところ、幼児は手に持った饅頭を二つに割って「おじさんこれどっちがおいしいか」と当意即妙に答えたという民話を人形化したもの。部屋に飾っておくと「子供たちが賢くなる」と言われる。文化・文政時代からあったと伝わる伏見人形の代表作だ。

伏見稲荷大社の参道で名物の「すずめの焼き鳥」は、穀物を食い荒らすスズメ退治のために始まったとされ、大正時代から販売されてきた。穀物を食べる野鳥を追い払うために食べるのは「鳥追い」と呼ばれる文化の一つ。
ただ、その名物「スズメの焼き鳥」を売る店も現在では2店だけになっている。スズメを捕る猟師の高齢化やワシントン条約などもあり、禁輸による中国産の在庫切れが原因だ。
国産で販売を続けている食事処「稲福」は京都、兵庫、香川県などの猟師から仕入れているが、確保できる量はピーク時の3分の1にすぎない。国産すずめの解禁時季に限って姿焼きを販売している。値段も1本500円と中国産の約2倍。スズメ猟の後継者も少なくなっているという。

狐の面のような、甘さ控えめ、味噌の香ばしい
「いなり煎餅」。手焼きするための煎餅の型がだんだん、製造されなくなってきているのだとか。

朱塗りの楼門
表参道に面して厳然として建つ朱塗りの楼門は、安土桃山時代に豊臣秀吉により寄進されたもの。3間1戸、屋根は入母屋造り、桧皮葺で屋根の軒反りが大きく荘重な威厳がある。
天正18年(1589)、豊臣秀吉が母大政所の病気回復を願って、こと成就のあかつきには1万石を寄進するとの「命乞いの願文」が残されている。
昭和49年の解体修理の際、垂木に同年号の墨書銘が発見され、秀吉書状の正しさが証明された。

お茶屋
参集殿の東にある「お茶屋」はもともと仙洞御所にあったものを、慶長11年(1608) 禁中非蔵人として出仕していた、伏見稲荷大社の神主であった羽倉延次が、後水尾院から拝領したものである。
天皇家が使用していた茶室ということで、普通の茶室のようなにじり口はなく、貴人口とも呼ばれる大きな出入り口となっている。書院造りが数寄屋造り化していく過程を示す数少ない貴重な遺構だ。
重要文化財。非公開

楼門を潜るとすぐの外拝殿が現れる。外拝殿の背後の石段の上に内拝殿、本殿となる。
外拝殿の金色の手すりには、天保11年とある。江戸時代の末ごろ、11代将軍徳川家斉の末期に当たる。外拝殿は天正年間、1589年頃に作られたものが、この天保11年(1840年)に改築され、そのときに刻まれた文字だという。
内拝殿は外拝殿の斜め後ろにあり、その奥に稲荷造という屋根続きで重要文化財の本殿がある。


本殿 (重文・室町)
社殿は明応3年(1494)の建造で、5間社、流造り、屋根は桧皮葺とした稀にみる大建築で、これを「稲荷造り」という。社記には、「御本殿、五社相殿、ウチコシナガレ作、四方ニ高欄アリ、ケタ行五間五尺、ハリ行五間五尺」とある。
打越流造りとは、浅い背面の流れが棟を打越して、雄大な曲線を描きながら、長々とゆるやかに流れており、側面から眺めると、棟へ向かって盛り上がるように妻がそびえている形をいう。
現在は本殿と拝所の間がきわめて狭くなっている。これは昭和38年の本堂修理の際に、内拝殿(祈祷所)を増築したためであり、このとき本殿を創建当初にもどし、向拝を内拝殿の正面に取り付けた。この唐破風の向拝は、秀吉が本殿修理後に付け足したもので「懸魚」の金覆輪や「垂木鼻」の飾金具、前拝の「蟇股(かえるまた)」の意匠に安土桃山時代の気風がみなぎる。

荷田春満邸宅跡と東丸神社
伏見稲荷大社の外拝殿南にある小さな神社が荷田春満を奉る東丸神社 。学問の神様である。隣接して邸宅跡も残る。
荷田春満(かだのあずままろ)は、江戸時代中期の国学者で歌人。古典・国史を研究して復古神道を提唱。『万葉集』『古事記』『日本書紀』や大嘗会の研究の基礎を築き、賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤と共に国学の四大人の一人に数えられた 。
元禄赤穂事件で有名な大石内蔵助とは旧知の友人であったといい、大石は『源氏物語』などの進講や歌の指導をしに、よく吉良家へ行っていた春満から吉良邸茶会が元禄15年12月14日(1703年1月30日)にあることを聞き出し、この日を討ち入り決行の日と定めている 。といった逸話も伝えられる。

本殿の参拝後、本殿背後の稲荷山の三つの峰を順拝(お山めぐり)する。いわゆる稲荷詣である。社殿も元は三つの峰に上、中、下の三社に分かれていたが、応仁の乱の兵火で焼けて現在の地に遷った。本殿修築などの際に神様が遷座する仮殿の役割を持つ「権殿」よこの石段がお山めぐりのスタート。

初めが玉山稲荷社、右の石段をのぼり奥宮、その横が白狐社。なだらかな登りの石段を登り始める。稲荷社の聖地でもある御膳谷奉拝所、かつての祭祀遺跡と云われる御饌石(みけいし)があったり、三条小鍛治宗近の話が残る御剣社、枕草子に記された清少納言が登ったと伝わる春繁社など、逸話には事欠かない。
枕草子「2月午の日の暁に、稲荷の社に詣で、中ノ社のあたりにさしかかるともう苦しくて、なんとか上ノ社までお参りしたいものだと念じながら登っていく……誠にうらやましく思ったもの」

ここから「千本鳥居」が始まる。千本とは無限のごとく多いという意味。実際には数多の人たちから寄進された、5千本にも及ぶ鳥居が今もその数を増やし続けている。
この鳥居を潜り30分ほどで三ツ辻に着く。この辺りには休憩のための茶店などもある。元気ならそのまま歩くと四ツ辻へ。眼下の深草の町を展望できる。続けて一ノ峰、ニノ峰、三ノ峰と歩く。

稲荷神社の守り神は何故、おキツネさん?
楼門の両脇に宝珠と倉の鍵を持つ、眷属(けんぞく・神の使い)としてのきつねがいる。境内のあちこちで見られる。
山からおりて田の近くで食物をあさり(実る稲穂をねらう害獣:ネズミ等が獲物)、子キツネを養う。それは,稲の稔った晩秋から冬にかけての季節。そして,秋の田園でたわわに実る稲穂の色と,キツネの体毛は同色。
豊かな実りを迎えた田園風景に,稲穂と同色のキツネの親子。農村に生きる当時の日本人の目には,繁殖=豊作のイメージとして結びついた。

民俗学者の柳田國男は「田の神の祭場として残した未開地にキツネが住み着き,人々の前で目につく挙動をしたため」と説明する。キツネの習性が神秘性と結びつき「キツネは神の使い」とイメージされ,やがて「稲荷信仰」と結びついたと考えられているという。
一方でキツネが,穀物の神である宇迦之御魂神の使いになったのは,一般には宇迦之御魂神の別名が「御饌津(みけつ)神」であったことから,ミケツの「ケツ」がキツネの古名「ケツ」に想起され,誤って「三狐神」と書かれたため。そして,先に触れたようなキツネの習性(穀物を食べる野ネズミをキツネが食べてくれるなど)が,田の神の先触れ,田の守り神と見られ,キツネを通さなければ穀物あるいは豊かな実り・農耕の神の神霊をうかがい知ることはできないと考えられたとの説もある。

千本鳥居をぬけたところ通称「命婦谷」にあり、一般には「奥の院」の名で知られる。この奥社奉拝所はお山を遥拝するところで、稲荷山三ケ峰はこの社殿の背後に位置している。
奥社には「おもかる石」と云われる一種の神占石がある。この灯篭の前で願い事の叶うことを念じて石灯篭の空輪(頭)を持ち上げ、そのときに感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、重ければ叶い難いとする試し石である。

初午(2月に初めて廻ってくる午・うまの日)の「初午大祭」で、参詣者に授与される「しるしの杉」は歴史も古く、和歌においては、稲荷の歌枕にもなっている。御礼、御守りの代わりであった。
秦氏が先祖の罪を悔い改めて神様に祈願し、社の杉を庭に植えると、立派に育ち福を得たという縁起による。初午のお参りは福が授かる「福参り」といわれる所以である。
伏見稲荷大社は、東寺の鎮守社でもある
平安時代には、稲荷信仰は真言密教と結びつく。淳和天皇が病気になった原因は、弘法大師空海が東寺の建立に当たって稲荷山の木々を伐り出したことによると云う宣託を受けて、天皇は稲荷神に従五位下の位を贈り謝罪することで、その非を認めた一件から、東寺と稲荷大社の結びつきは強固になっていった。
また、東寺は西寺と共に国家鎮護の寺として建立されるが、稲荷社の位置関係も京の都から見て東南の方角に当たるため、これも王城鎮護の役割とも合いまったもののようだ。
藤森神社とは犬猿の仲?
もともとこの地域は紀氏の領土であったという。紀氏の神を奉る藤森神社の氏子が今でも多い。軒先を貸した秦氏の勢力が台頭し、母屋も…………との伝承もある。真実はいかに。

御近所散策 ぬりこべ地蔵
稲荷大社の大鳥居をくぐって、社殿の右横にある東丸神社の横に続く細い路地を南に行き、石峰寺に行く道の途中。お墓の立ち並ぶ一角にこのぬりこべ地蔵尊はあります。 本来は『塗り壁地蔵』と呼ばれていた土壁に塗り込められたお堂に祀られたお地蔵さんは、京都でも屈指の名地蔵といわれ、病気を塗り込める、とりわけ歯痛に効き目があるということで人々の崇拝をうけている。
この「ぬりこべ地蔵さん」は歯痛が治るよう祈願したハガキを出すだけでも願いを聞いてくださるとか。 6月4日(虫歯予防デー) には「歯痛封じ法要」が行われます。
周辺の悪い箇所を千本通りの『釘抜き地蔵』で抜いた跡を修復し再発を封じてくれるやさしい地蔵でもある。『釘抜き地蔵』に御参りした後、なるべく早く参拝するのが良いという。

御近所散策 石峰寺
百丈山石峰寺は、江戸中期の正徳3年(1713)に黄檗宗萬福寺(宇治市五ヶ庄)の第六世千呆性侒(せんかんせいあん)禅師により創建された禅道場が始まりである。七面山西麓 にある。
石段を登りきると竜宮造りの赤い門(総門)があり、「高着眼(こうちゃくがん)」の扁額が架かる。本尊は薬師如来。平安中期の武将の多田(源)満仲の念持仏で恵心僧都の作 。
本堂裏の竹林に五百羅漢と呼ばれる石仏群が風情をかもしだす。表情豊かな石仏の下絵は、江戸中期の画家、伊藤若冲がここに庵を結び、十年あまりの歳月をかけて描き上げたものだ。
奈良時代に、秦氏が稲荷山に奉った神が始まりとされ、稲荷山の山上山下の一帯が稲荷信仰の原域 、御神体である。伏見稲荷の祭神は宇迦之御魂神、五穀豊穣の穀物の神である。五柱を奉る。
稲荷の語源は稲が成る(稲成)から来ており、元々は五穀豊穣を願う農耕の神。今でも田植え神事などが引き継がれている。後に米が商取り引きの中心になり、石高で流通価値を表すようになっていった経過から、商売繁盛の神としても崇められていくようになる。
深草の里が早くから開拓されて、人の住むところであったことは深草弥生遺跡に見ることができる。ここへ秦氏族が住みつき、在地の小豪族として勢力を伸ばしていったと考えられている。
駐車場は師団街道稲荷新道から東に、京阪伏見稲荷駅を越えて、稲荷大社の総門をくぐった社務所前、参集殿あたりに数箇所隣接している。参集殿は宿泊、食事なども行える。
「『山城国風土記』の逸文によると、古くからこの地域に住んで、一族が繁栄を極めていた秦氏の長者・伊呂具(いろぐ)は、和銅四年(711)2月初午の日、驕富(きょうふ)におごって餅を的にして矢を射たところ、的はたちまち白鳥と化して飛びたち、後ろの山の三ヶ峯の頂上にとどまった。するとそこにたちまち「稲が奈利生(なりお)う」という奇瑞がおこり、その後は、秦氏の家運が傾きはじめたので、伊呂具は驕慢(きょうまん)の心を悔いて杉を神木として稲の精霊を祀り、再び家運を挽回することが出来た。
この霊験のあらたかさに感じて、この精霊を「稲成(いなり)の神」と崇め、山を神山(こうやま)として崇め、元明天皇の和銅4年(711)に、その麓に社殿を営むことになった。そして伊呂具の後裔にあたる秦忌寸(はたのいみき)の一統が代々祖神祭祀の聖地として祭祀にたずさわってきたのである。」
http://www.fusimi-inari.com/store/map01.asp
「伏見稲荷参道商店街」のウェブガイド」

京阪電車の伏見稲荷駅からして稲荷色だ。駅のイメージが、あの鳥居の朱色なのである。朱(あか)は魔よけの色である。元来、稲荷の鳥居は社殿と同じく「稲荷塗」といわれ、朱をもって彩色するのが慣習となっています。ちなみにJR稲荷から続くのが表参道、京阪から続くのが裏参道である。参道には稲荷らしいお土産物店が並ぶ。伏見人形、稲荷寿司、キツネの煎餅、びっくりするのはスズメ、ウズラの姿焼き。

深草は、良土を産出し、古くから土人形のふるさとと言われる。(5世紀中ごろから7世紀前半)土器が造られ、土師部(はじべ‐埴輪や土器を造る職人)が、奈良の菅原(西大寺の南)から移住した記録があり、遺跡も発掘された。さらに、豊臣秀吉の伏見城建造時(1594年)、播州(今の兵庫県)などから瓦を造る人々が深草に移り住んだ。
これらの人々から伏見人形が起こった。伏見人形(稲荷人形・深草人形)は、日本各地の土人形・郷土玩具の原型となった。
「饅頭食い人形」は、ある人が幼児に「お父さんとお母さんどちらが大切か」と問うたところ、幼児は手に持った饅頭を二つに割って「おじさんこれどっちがおいしいか」と当意即妙に答えたという民話を人形化したもの。部屋に飾っておくと「子供たちが賢くなる」と言われる。文化・文政時代からあったと伝わる伏見人形の代表作だ。

伏見稲荷大社の参道で名物の「すずめの焼き鳥」は、穀物を食い荒らすスズメ退治のために始まったとされ、大正時代から販売されてきた。穀物を食べる野鳥を追い払うために食べるのは「鳥追い」と呼ばれる文化の一つ。
ただ、その名物「スズメの焼き鳥」を売る店も現在では2店だけになっている。スズメを捕る猟師の高齢化やワシントン条約などもあり、禁輸による中国産の在庫切れが原因だ。
国産で販売を続けている食事処「稲福」は京都、兵庫、香川県などの猟師から仕入れているが、確保できる量はピーク時の3分の1にすぎない。国産すずめの解禁時季に限って姿焼きを販売している。値段も1本500円と中国産の約2倍。スズメ猟の後継者も少なくなっているという。

狐の面のような、甘さ控えめ、味噌の香ばしい
「いなり煎餅」。手焼きするための煎餅の型がだんだん、製造されなくなってきているのだとか。

朱塗りの楼門
表参道に面して厳然として建つ朱塗りの楼門は、安土桃山時代に豊臣秀吉により寄進されたもの。3間1戸、屋根は入母屋造り、桧皮葺で屋根の軒反りが大きく荘重な威厳がある。
天正18年(1589)、豊臣秀吉が母大政所の病気回復を願って、こと成就のあかつきには1万石を寄進するとの「命乞いの願文」が残されている。
昭和49年の解体修理の際、垂木に同年号の墨書銘が発見され、秀吉書状の正しさが証明された。

お茶屋
参集殿の東にある「お茶屋」はもともと仙洞御所にあったものを、慶長11年(1608) 禁中非蔵人として出仕していた、伏見稲荷大社の神主であった羽倉延次が、後水尾院から拝領したものである。
天皇家が使用していた茶室ということで、普通の茶室のようなにじり口はなく、貴人口とも呼ばれる大きな出入り口となっている。書院造りが数寄屋造り化していく過程を示す数少ない貴重な遺構だ。
重要文化財。非公開

楼門を潜るとすぐの外拝殿が現れる。外拝殿の背後の石段の上に内拝殿、本殿となる。
外拝殿の金色の手すりには、天保11年とある。江戸時代の末ごろ、11代将軍徳川家斉の末期に当たる。外拝殿は天正年間、1589年頃に作られたものが、この天保11年(1840年)に改築され、そのときに刻まれた文字だという。
内拝殿は外拝殿の斜め後ろにあり、その奥に稲荷造という屋根続きで重要文化財の本殿がある。


本殿 (重文・室町)
社殿は明応3年(1494)の建造で、5間社、流造り、屋根は桧皮葺とした稀にみる大建築で、これを「稲荷造り」という。社記には、「御本殿、五社相殿、ウチコシナガレ作、四方ニ高欄アリ、ケタ行五間五尺、ハリ行五間五尺」とある。
打越流造りとは、浅い背面の流れが棟を打越して、雄大な曲線を描きながら、長々とゆるやかに流れており、側面から眺めると、棟へ向かって盛り上がるように妻がそびえている形をいう。
現在は本殿と拝所の間がきわめて狭くなっている。これは昭和38年の本堂修理の際に、内拝殿(祈祷所)を増築したためであり、このとき本殿を創建当初にもどし、向拝を内拝殿の正面に取り付けた。この唐破風の向拝は、秀吉が本殿修理後に付け足したもので「懸魚」の金覆輪や「垂木鼻」の飾金具、前拝の「蟇股(かえるまた)」の意匠に安土桃山時代の気風がみなぎる。

荷田春満邸宅跡と東丸神社
伏見稲荷大社の外拝殿南にある小さな神社が荷田春満を奉る東丸神社 。学問の神様である。隣接して邸宅跡も残る。
荷田春満(かだのあずままろ)は、江戸時代中期の国学者で歌人。古典・国史を研究して復古神道を提唱。『万葉集』『古事記』『日本書紀』や大嘗会の研究の基礎を築き、賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤と共に国学の四大人の一人に数えられた 。
元禄赤穂事件で有名な大石内蔵助とは旧知の友人であったといい、大石は『源氏物語』などの進講や歌の指導をしに、よく吉良家へ行っていた春満から吉良邸茶会が元禄15年12月14日(1703年1月30日)にあることを聞き出し、この日を討ち入り決行の日と定めている 。といった逸話も伝えられる。

本殿の参拝後、本殿背後の稲荷山の三つの峰を順拝(お山めぐり)する。いわゆる稲荷詣である。社殿も元は三つの峰に上、中、下の三社に分かれていたが、応仁の乱の兵火で焼けて現在の地に遷った。本殿修築などの際に神様が遷座する仮殿の役割を持つ「権殿」よこの石段がお山めぐりのスタート。

初めが玉山稲荷社、右の石段をのぼり奥宮、その横が白狐社。なだらかな登りの石段を登り始める。稲荷社の聖地でもある御膳谷奉拝所、かつての祭祀遺跡と云われる御饌石(みけいし)があったり、三条小鍛治宗近の話が残る御剣社、枕草子に記された清少納言が登ったと伝わる春繁社など、逸話には事欠かない。
枕草子「2月午の日の暁に、稲荷の社に詣で、中ノ社のあたりにさしかかるともう苦しくて、なんとか上ノ社までお参りしたいものだと念じながら登っていく……誠にうらやましく思ったもの」

ここから「千本鳥居」が始まる。千本とは無限のごとく多いという意味。実際には数多の人たちから寄進された、5千本にも及ぶ鳥居が今もその数を増やし続けている。
この鳥居を潜り30分ほどで三ツ辻に着く。この辺りには休憩のための茶店などもある。元気ならそのまま歩くと四ツ辻へ。眼下の深草の町を展望できる。続けて一ノ峰、ニノ峰、三ノ峰と歩く。

稲荷神社の守り神は何故、おキツネさん?
楼門の両脇に宝珠と倉の鍵を持つ、眷属(けんぞく・神の使い)としてのきつねがいる。境内のあちこちで見られる。
山からおりて田の近くで食物をあさり(実る稲穂をねらう害獣:ネズミ等が獲物)、子キツネを養う。それは,稲の稔った晩秋から冬にかけての季節。そして,秋の田園でたわわに実る稲穂の色と,キツネの体毛は同色。
豊かな実りを迎えた田園風景に,稲穂と同色のキツネの親子。農村に生きる当時の日本人の目には,繁殖=豊作のイメージとして結びついた。

民俗学者の柳田國男は「田の神の祭場として残した未開地にキツネが住み着き,人々の前で目につく挙動をしたため」と説明する。キツネの習性が神秘性と結びつき「キツネは神の使い」とイメージされ,やがて「稲荷信仰」と結びついたと考えられているという。
一方でキツネが,穀物の神である宇迦之御魂神の使いになったのは,一般には宇迦之御魂神の別名が「御饌津(みけつ)神」であったことから,ミケツの「ケツ」がキツネの古名「ケツ」に想起され,誤って「三狐神」と書かれたため。そして,先に触れたようなキツネの習性(穀物を食べる野ネズミをキツネが食べてくれるなど)が,田の神の先触れ,田の守り神と見られ,キツネを通さなければ穀物あるいは豊かな実り・農耕の神の神霊をうかがい知ることはできないと考えられたとの説もある。

千本鳥居をぬけたところ通称「命婦谷」にあり、一般には「奥の院」の名で知られる。この奥社奉拝所はお山を遥拝するところで、稲荷山三ケ峰はこの社殿の背後に位置している。
奥社には「おもかる石」と云われる一種の神占石がある。この灯篭の前で願い事の叶うことを念じて石灯篭の空輪(頭)を持ち上げ、そのときに感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、重ければ叶い難いとする試し石である。

初午(2月に初めて廻ってくる午・うまの日)の「初午大祭」で、参詣者に授与される「しるしの杉」は歴史も古く、和歌においては、稲荷の歌枕にもなっている。御礼、御守りの代わりであった。
秦氏が先祖の罪を悔い改めて神様に祈願し、社の杉を庭に植えると、立派に育ち福を得たという縁起による。初午のお参りは福が授かる「福参り」といわれる所以である。
伏見稲荷大社は、東寺の鎮守社でもある
平安時代には、稲荷信仰は真言密教と結びつく。淳和天皇が病気になった原因は、弘法大師空海が東寺の建立に当たって稲荷山の木々を伐り出したことによると云う宣託を受けて、天皇は稲荷神に従五位下の位を贈り謝罪することで、その非を認めた一件から、東寺と稲荷大社の結びつきは強固になっていった。
また、東寺は西寺と共に国家鎮護の寺として建立されるが、稲荷社の位置関係も京の都から見て東南の方角に当たるため、これも王城鎮護の役割とも合いまったもののようだ。
藤森神社とは犬猿の仲?
もともとこの地域は紀氏の領土であったという。紀氏の神を奉る藤森神社の氏子が今でも多い。軒先を貸した秦氏の勢力が台頭し、母屋も…………との伝承もある。真実はいかに。

御近所散策 ぬりこべ地蔵
稲荷大社の大鳥居をくぐって、社殿の右横にある東丸神社の横に続く細い路地を南に行き、石峰寺に行く道の途中。お墓の立ち並ぶ一角にこのぬりこべ地蔵尊はあります。 本来は『塗り壁地蔵』と呼ばれていた土壁に塗り込められたお堂に祀られたお地蔵さんは、京都でも屈指の名地蔵といわれ、病気を塗り込める、とりわけ歯痛に効き目があるということで人々の崇拝をうけている。
この「ぬりこべ地蔵さん」は歯痛が治るよう祈願したハガキを出すだけでも願いを聞いてくださるとか。 6月4日(虫歯予防デー) には「歯痛封じ法要」が行われます。
周辺の悪い箇所を千本通りの『釘抜き地蔵』で抜いた跡を修復し再発を封じてくれるやさしい地蔵でもある。『釘抜き地蔵』に御参りした後、なるべく早く参拝するのが良いという。

御近所散策 石峰寺
百丈山石峰寺は、江戸中期の正徳3年(1713)に黄檗宗萬福寺(宇治市五ヶ庄)の第六世千呆性侒(せんかんせいあん)禅師により創建された禅道場が始まりである。七面山西麓 にある。
石段を登りきると竜宮造りの赤い門(総門)があり、「高着眼(こうちゃくがん)」の扁額が架かる。本尊は薬師如来。平安中期の武将の多田(源)満仲の念持仏で恵心僧都の作 。
本堂裏の竹林に五百羅漢と呼ばれる石仏群が風情をかもしだす。表情豊かな石仏の下絵は、江戸中期の画家、伊藤若冲がここに庵を結び、十年あまりの歳月をかけて描き上げたものだ。
2011年01月27日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・北野天満宮

北野天満宮の参道・上七軒
北野天満宮の参道ともなっている上七軒。地元の方は「かみひちけん」というようだ。
室町時代、北野社殿が一部焼失し、時の十代将軍・足利義植は所司代・細川勝元に命じて、社殿の造営をさせた。その際、社殿御修築の残材を以て、東門前の松原に七軒の茶店を建て、 参詣諸人の休憩所としたので、七軒茶屋と称したのがその由来である。

天正十五年(1587年)八月十日、太閣秀吉、北野松原に於て晴天十日間(実際には1日で打ち切り)の大茶会を催し「茶の湯熱心のものは、若党町人百姓以下のよらず来座を許す」 との布令を発したため、洛中は勿論、洛外の遠近より集まり来る者限りなく、北野付近は時ならず非常の賑わいを呈した。
その際、この七軒茶屋を、秀吉の休憩所に充て、名物の御手洗団子を献じたところ、いたく賞味に預り、 その褒美として七軒茶屋に御手洗団子を商うことの特権と、山城一円の法会茶屋株を公許したのが、我国に於けるお茶屋の始まりであると伝承される。
上七軒花街が、五つ団子の紋章を用いるのもここに由来する(歌舞会記より)
またその後、西陣の隆盛で旦那衆が闊歩(かっぽ)した花街としても繁栄を極める。

現在、お茶屋が十軒、芸、舞妓二十数名。
毎年春になると「北野おどり」が上演されて少数ながらにして良い技芸を磨き披露している。舞踊の流派は明治以前は篠塚流、その後は花柳流。茶道は西方尼寺で習っている。

夏甘糖(なつかんとう)で有名な和菓子「老松」、欧風料理の「萬春」はじめ、和洋中の本格料理から、うどんやお好み焼きまで、こだわりの店が30数店舗を超えるグルメスポットでもある。味にも値段にもシビアな西陣の旦那衆が通うお店が多く、元芸妓さんが切り盛りしている店も多数ある。 運がよければお店で上七軒の芸妓さん、舞妓さんを見かけることも!

駐車場は東側に無料のパーキングがある。
北野天神には楼門までに三つの鳥居がある。一の鳥居の東側の松は影向松(ようごうのまつ)といって、初雪が降ると菅原道真公がこの松に降りて雪に因む歌を詠むと伝承される。道真が肌身離さず持っていた御襟懸守護の仏舎利が大宰府より雪とともに飛翔してきたとの逸話によるものだ。
三の鳥居横には、道真公の母君を祀る伴氏社(ともうじしゃ)が見られる伴氏社の石鳥居は鎌倉時代の作で、台座に彫られた蓮弁が珍しい。伴氏とは奈良時代の有力豪族・大伴氏である。
三の鳥居の東側あたりの松原は、上述した北野大茶会(きたのだいさのえ)が催されたところ。豊臣秀吉が九州平定と聚楽第の竣工を祝って催した大茶会。1587年(天正15)10月1日、秀吉みずから亭主をつとめるなど、この日の参加者は、1000人を超えて賑ったという。諸家の茶席に秀吉秘蔵の「似たり茄子」初め、名物茶器・道具が展観された。

茶会の遺跡として「太閤井戸」がある。北野大茶湯は秀吉に対する京都人の感情を知る試金石であったといわれている。

楼門
桃山時代の様式。「文道大祖風月本主」と書かれた扁額が架かっている。「文道大祖 風月本主」というのは大江匡衡(952~1012)が道真を称賛して、天満宮に奉納した願文の中の言葉。菅原道真のこと。楼門の左右には右大臣、左大臣が鎮座する。

北野天神の神紋は星梅鉢紋。「東風(こち)吹かば 匂い起こせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」
梅をこよなく愛したという道真にちなむ。その梅が主である道真を慕って、一晩のうちに太宰府に飛んでいったという「飛梅伝説」が生まれた。

北野天満宮には50種約2000本の梅が植えられ、2月初旬から3月末までは梅苑(有料)も公開される。梅の香りに誘われるように梅の季節には大勢の参拝客が訪れる。

楼門をくぐった東側に、参拝者が手と口を清めるための手水舎があり、「手水鉢(ちょうずばち)」と「柄杓(ひしゃく)」が備え付けられている。
神様は「穢れ(けがれ)」を嫌うため、神域に立ち入るときに、心身の穢れや罪を祓う「禊(みそぎ)」という作法が古来より行われてきた。手水は、かつて、海や川で行われていた儀式が簡略されたもの。
手水を行うときの作法は--。
まず一礼してから右手で柄杓を取り、水を汲む。
その水で、まず左手を濯ぎ、次に左手で柄杓を取り直して右手を濯ぐ。
もう一度右手で柄杓を取り、左手で水を受け、その水で口を漱ぐ。
口を漱いだらもう一度水を汲んで、今度は左手を濯ぐ。
柄杓を立てて、残った水で柄の部分を清め、柄杓を元の位置に戻す。
そして最後に一礼して、手水舎を出る。

牛は天神さんのお使いといわれ、北野天満宮の境内にもたくさんの牛の像「なで牛」を見ることができる。
理由は、道真の生まれた年が丑年、道真が亡くなったのが丑の月の丑の日、道真は牛に乗り大宰府へ下った、牛が刺客から道真を守った。道真の墓(太宰府天満宮)の場所を牛が決めたなどなど諸説ある。
「座牛・寝牛」であるのは、菅公が亡くなった際、轜車(きしゃ・喪車)を引いていた牛が、悲しみのあまり安楽寺四堂のほとりで座して動かなくなってしまったとの伝承からきている。

この牛の像の頭をなでると頭がよくなるといわれ、特に受験生に大人気だ。また体の調子が悪い人は、自分の体の悪い部分と、牛のその同じ部分とを交互になでると良くなるといわれる。
ご利益を得ようと、いつも人の手で磨かれているので、牛はピカピカに輝いて見える。

三光門
2006年(平成18年)1月15日(日)京都新聞より抜粋
「雲間に浮かぷ月、実は星」
北野天満宮の中門は、三光門とも呼ばれ、「天満宮」の額を掲げたひわだぷきの四脚唐門で、華麗な彫刻を施した桃山時代の建造物として重要文化財に指定されています。
門わきの立て札には「由来は、豊冨な彫刻の中に日・月・星があることによる」と記されていました。では、日・月・星という三光の彫刻はどこにあるのでしょうか。

日(太陽)は「天満宮」の額が掲げられた背面の梁間(はりま)に深紅の太陽のが。対極の梁間には雲に浮かんだ月?が。
「残るは星」がなかなか見つかリません。やっと北側(本殿側)の金網に守られた破風(はふ)に、二匹のうさぎの中央に三日月の彫刻を見つけましたが、星の彫刻ではあリません。神職の松大路和弘さんに聞きました。
雲間に浮かぶ月と見えた彫刻が実は星だったのです。現代の感覚では、ギザギザの星形を思い浮かべますが、丸く彫られた星を月と見誤ったようです。

ただ「三光門にはもともと星の彫刻は無く、旧大極殿から真北に位置する中門の上空に輝く北極星を三光の星に見立てた」という言い伝えもあリ、「星欠け門」との別名もあるそうです。このようにさまざまないわれが伝わるのも、この門の華麗さが、往時の人々の話題になったことの裏付けではないでしょうか。

平安京遷都より100年の頃、都における高官であった菅原道真(天神)は、藤原氏との政争にやぶれ、太宰府に左遷された。
大宰府で無念の死をとげたといわれているが、没後、京都で災害が頻発し、これが道真の怨霊の祟りとして恐れられた。
天慶5年(942年)に右京七条の巫女、多治比文子(たじひあやこ)に道真から「北野に社殿を造り自分を祀るように」との御託宣があったという。道真の霊を鎮めるため、文子は当初、自宅の庭に瑞垣を造り祀っていた(現在の文子天満宮)が、北野の朝日寺の僧、最鎮に相談し、その後、現在の地に祀るようになった。
拝殿の上の欄間にいるのは、境内でただ一頭だけの「立ち牛」だ。全国の天満宮的にもめずらしいという。道真のご神体の前で不敬ではいけないということだろうか?

現存の「拝殿」及び「本殿」、中門、東門、絵馬堂、神楽殿、校倉 は慶長12年(1607年)豊臣秀吉の遺命に基づき豊臣秀頼が片桐且元を奉行として造営したものといわれている。
「拝殿」は国宝。なお、拝殿の前は左近の梅、右近の松(なんで?)である。
さらに、北野天満宮は、神社としては、とても不思議な造りになっているとか。拝殿と本殿が大きな屋根でひとつに覆われている。しかも中央に一段低い石の間がある。
北野天満宮は、本来神を祀る場所ではなく、御霊を鎮めるための場所だったということから、明治の神仏分離まで、神社ともお寺とも区別のつかない不思議な形態だったのだ。「宮寺」と呼ばれ、天台宗に属し、皇族を門跡とする曼珠院が別当となっていた。北野天満宮が神社となるのは、明治以降のことである。ちなみに、本殿は八棟造で、江戸時代以降、秀吉の豊国神社や家康の東照宮にも引き継がれ、権現造と呼ばれるようになった。
地方豪族の出自から大学に出仕し、学者から学問の才だけで右大臣にまで出世したのは、吉備真備と菅原道真だけである。このことから、天神さんは学問の神として奉られるようになった。

二礼二泊一礼
拝殿の前には大きな鈴がぶらさがっていて、ひもを引いて鳴らすようになっている。鈴には、もともと呪力があると考えられており、 邪気を祓うことで神様と対面できる状態にするためだ。鈴を鳴らしたあと、賽銭を入れ、二回おじぎをした後、大きく手を開いて2回柏手(かしわで)を打って、最後にもう1回おじきをする、というのが神様へのご挨拶の仕方。
なお神社は柏手を打つが、お寺さんでは合掌になるので混同しないように気をつけよう。


拝殿から西側の門をくぐると御土居の入り口がある。境内の西側には御土居の史跡が広がっている。東は鴨川右岸、北は鷹が峰、西は紙屋川左岸、南は九条通で、全長22.5kmの及ぶこの築堤を「御土居」と呼ぶ。
豊臣秀吉は京都を抑えるとすぐにも、伏見城や聚楽第、京大仏の建設、町割りをはじめ、京都の大改造に乗り出した。北は寺の内通り、東は寺町通りを造り、寺社を移転させ、防波堤とした。そして、西と南は治水のためもあって、この御土居と呼ばれる堀と土塁の堤防で取り囲んだのだ。明治維新で取り壊され、現在は市内十数箇所に跡が残る。
紅葉の時期には、御土居の紅葉として親しまれている。
絵馬について
古来、馬は神様の乗り物と考えられていたため、もともとは本物の馬を奉納していた。しかし、本物の馬は高価な上に、奉納される側も設備や世話などの面で面倒なため、平安時代の頃から馬を書いた絵で代用されるようになった。
その後、境内に絵馬堂が設けられ、絵に描いた馬や武具などを奉納するようになった。
現在では、絵馬も小振りになり、庶民でも奉納できる身近なものになった。神社や寺院に参拝する際に、絵馬に具体的な願いごとを書いて奉納すると願いがかなうとされている。
地主神社 祭神:天神地祇(てんじんちぎ)
『続日本後記』に承和3(836)年(菅公生誕の9年前)2月1日、遣唐使のために天神地祇を北野に祭る」と記録されている通り、天満宮創建以前よりこの地に鎮座されている神社である。
主祭神の天神地祇とは、日本国内六十余国に祭られたすべての神々のことであり、現社殿は、豊臣秀頼の造営になり、由緒・規模とも天満宮第一の摂社である。
実は、鳥居から拝殿に至る北野天満宮の中心軸は、元々からのこの地の神である地主神社を避けて建てられている。

北野天満宮の北門を出たところに石仏が奉られているが、この石仏は、破壊された御土居から掘り出されたもの。この北側にも御土居が残されていて、真近に見られる。
織部形石燈籠
別名「マリア燈籠」とも「切支丹燈籠」とも言われている。マリア像が彫刻されています。
「織部形石燈籠」というのは、茶人好み石燈籠形式の一つで、古田織部正重然の墓にあるものの形に因んで名付けられています。
大黒さん
三光門の東側にひっそりと佇む大黒さん。この大黒さんのえくぼに、一回で小石を詰めて落ちなければ縁起が良いとか、願いがかなうとか、その石を財布に入れておくとお金が貯まるとかと言われています。

菅原道真公の生誕6月25日、命日2月25日にちなみ、毎月25日には、神社境内と周辺に所狭しと露店が並び、市が開催される。特に12月25日の市を終い天神、1月25日の市をお初天神と呼んでいる。
かつては、煤(すす)払いと称して、年の暮れに屋内の煤やほこりを払い、不要になった道具類を廃棄した(現代の年末大掃除)。『付喪神絵巻』によると、煤払いには、手持ちの古道具が付喪神に変化する前に手放すという目的もあったそうだ。その廃棄された古道具を神社仏閣で転売し始めたのが、京都で有名な東寺や北野天満宮の古道具市の起源であったという。
とようけ屋
いつも長い行列が出来ている人気のお豆腐やさん。天神さんの門前にある、明治30年から続く老舗です。

俵屋うどん
天神さんの門前から今出川通りをはさんで、御前通りを下がったところにあるうどんやさん。ぶっというどん。少しえきぞちっく?

みたらし団子の日栄堂
今出川通りの上七軒から東へ少し行った北側にあるのが、日栄堂です。少し大きめのだんごが柔らかくてもっちり~としてて、焦げ目が香ばしい。タレも絶品なのです。一個一個丁寧に手作りされたおだんごが一串110円はお買い得です。


妖怪ストリート 大将軍商店街
一条通りにある大将軍商店街は、平安時代の京都で起こったとされる百鬼夜行(多くの異形の鬼・妖怪たちが夜中に徒党を組んで行進する現象)の通り道だったとされることから、各店舗ではかわいい妖怪たちが出迎えてくれる。
大徳寺真珠庵所蔵の『百鬼夜行絵巻』では、古道具が変化した妖怪「付喪神(つくもがみ)」が主役になっています。陽気で滑稽で愛らしい姿が描かれています。


大将軍八神社
平安京造営の際、陰陽道に依り大内裏(御所)の北西角の天門に祭られた方除けの星神・大将軍。商店街の中心にある。
「天地明察」の渋川春海の天球儀なども安置されている。
2011年01月24日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・清水寺
音羽山清水寺は、1200余年前、奈良時代の末、宝亀9年(778)の開創といわれる。奈良の延鎮上人(開山)が、この音羽山麓の滝のほとりにたどり着き、観音菩薩の化身(開祖・行叡)より霊木を授けられ、それを持って千手観音像を彫作して奉ったのがおこりと伝わる。
その翌々年、蝦夷征伐で知られる坂上田村麻呂が、高子妻室の安産のためにと鹿を求めて上山し、清水の源をたずねたところ、 延鎮上人に出会い、殺生の非を諭され、鹿を弔うて下山した。妻室に延鎮の説く清滝の霊験、 観世音菩薩の功徳を語り、共に深く観世音に帰依して仏殿を寄進し、ご本尊に十一面千手観音を安置したといわれれている。
「清水寺」の寺名は音羽の滝の清泉にちなみ、以後、古くからの観音霊場として人々の崇敬を集めてきた。もとは興福寺の玄肪が請来した北伝の法相宗に属したが、現在は独立して北法相宗大本山を名乗る。
http://www.monzenkai.com/monzen_map.htm 清水寺門前会マップ
五条坂を上がると左手に大型駐車場(600円)、満車だったら突き当りの右側にタクシー専用駐車場がある。さらに満車の場合は、1時間500円となるが、高台寺の霊山観音の駐車場がある。
駐車場を降りて突き当たりの角が七味家本舗。創業350年、七味唐がらし創案の店だ。お振る舞いの「からし湯」は、白湯に唐辛子の粉をふりかけたもの。清水寺への参拝客や音羽の滝で修行する行者さんに「身体がぬくもるように」と、無償でだしていたものという。
栄山堂は、豆乳ドーナッツと豆乳ソフトが人気。お菓子をはじめ、京都限定キャラクターグッズなども多く、若い世代に人気がある。
清水焼窯元である森陶器店では「陶芸教室」が開設されている。店舗内では、自家の窯で焼き上げた清水焼作品をはじめ、京人形や京みやげが購入できる。
創作陶芸教室 (1名~300名)所要時間約90分 下絵付け教室(1名~600名)所要時間約40分 075-561-3457
錦古堂は、古都京都の伝統を受け継いだ京扇子専門舗。女性たちに人気のお店。
西尾八ッ橋は、京都で一番古い八ッ橋のお店。お茶のサービスがあるほか、店内では三十数種の八ッ橋が試食しほうだい。最近ではソーダやマンゴ、ショコラといったものまであり、種類は豊富だ。八ッ橋は老舗の聖護院八ッ橋、大手の井筒八ッ橋・夕子、おたべ他いくつもの店が乱立している。

参道を登りきると、眼前に石段が広がり、仁王門や西門が現れる。左側に地蔵院善光寺堂があり、脇にはちょこんとまあるいお地蔵さん・首振り地蔵が座している。(2代目、初代は堂の中にある)
善光寺堂縁先に祀られているこのお地蔵さんは首が離れているため自由に動かせる(360度回転できる)ようになっている。自分が恋い想う人が住む方向に首を振り向け、祈願すると思いが叶うとされている。「回らない人は、体が悪いか、借金で首が回らないのだとか?」

仁王門(重要文化財)
室町後期再建。両脇間に阿形・吽形の金剛力士像を安置する三間一戸、入母屋造り、檜皮葺、室町様式の堂々たる楼門(ろうもん)で、昔の丹塗りを淡美に残し「赤門」とよばれている。
阿吽(あうん)は仏教の呪文(真言)の1つ。梵字において、阿は口を開いて最初に出す音、吽は口を閉じて出す最後の音であり、それぞれ人間の生まれた瞬間と死ぬ瞬間の姿、宇宙の始まりと終わりを表すとされた。
狛犬は通常神社にあるが、清水寺の奥に地主神社があるため、門前に狛犬が一対置かれている。 また狛犬は阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の一対の姿なのだが、 ここのはなぜか両方とも口をあんぐりと開けている。「なんで?」(七不思議の一)
「坂を上りきって疲れた参拝者を励ますため、二匹とも爆笑してるのかなあ?」

西門(重要文化財)
江戸初期の再建。両脇間に持国天・増長天を祀り、優美な三間一戸の八脚門で、丹塗りと極彩色文様が復元されて華麗な桃山様式の美を見せる。 切妻造り、檜皮葺の西門。

随求堂(ずいぐどう)
江戸中期再興。塔頭・慈心院の本堂で、衆生の願い・求めにすぐに随って、すべて叶えてくれるという大功徳をもつ随求菩薩(秘仏)が祀られ、毘沙門天と吉祥天を脇侍にする。
堂下は随求菩薩の胎内に見たてた真っ暗な空間を大数珠をたよりにお詣りする「胎内めぐり」。自分自身の存在を問い直し、新生するのだとか。入場するのに百円必要だが、おもしろくもあるので、ぜひ体験してもらおう。

三重塔
一重内部に大日如来を祀り、天井や柱などが密教仏画や飛天・龍と各種文様らの極彩色で荘厳された高さ31㍍弱の日本最大級の三重の塔。四周の壁に真言八祖像が描かれている。
「大日如来」は真言密教の根本となる仏。宇宙の中心に位置し、その大いなる光ですべてのものを照らすという。塔は宇宙観を表しているのだ。
「真言八祖像」とは、真言密教の開祖龍猛から龍智・善無畏・一行・金剛智・不空・恵果と我が国に真言密教を伝えた空海までの八祖を八幅(8枚)一組の画像としたもの。東寺の五重塔などにも描かれている。明治維新までは、清水寺は法相宗に真言宗を兼ねていた。その名残がこの三重塔や大日堂に残されている。


轟門、梟(ふくろう)の手水鉢
経堂、坂上田村麻呂夫妻、開祖行叡居士、開山延鎮上人が祀られている田村堂を横目に、拝観券を買って、轟門をくぐる。
本堂への中門である轟門は江戸時代初期のもので、重要文化財。「普門閣」の扁額は月舟禅師の名筆。三間一戸の八脚門、切妻造り、本瓦葺きで、妻や天井の構造は東大寺転害門を縮小して写している。本殿、奥の院など境内を龍に見立て「龍の口」ともされている。左右両脇間に持国天像と広目天像を祀り、背面には阿・吽形の狛犬を安置する。
なお、轟門横の龍が水を出している清め水の梟の手水鉢。「なぜ龍なのに、梟(ふくろう)?」「さがしてごらん」
実は、手水鉢を支える石の四隅が梟の彫像がついた台座になっているから。じゃあ、フクロウと言えば知恵の神様なので、こんな下座に置くのはなんで?これも京都七不思議の一つだ。ちなみに、この水を含んで祈ると歯痛にご利益があると伝わる。

本堂前に鉄製の草履や杖があり、大きい杖は約90Kgあるとか!数人で持ち上げようとしてもなかなか持ち上がらない。
本堂・舞台(国宝)
清水寺本尊十一面千手観音(秘仏)を祀る正面十一間(約36㍍)、側面九間(約30㍍)、高さ18㍍の仏殿で、優美な起り反り曲線を見せる寄棟造り・檜皮葺の屋根や軒下に吊る蔀戸など、平安時代の宮殿、貴族の邸宅の面影を伝える。
江戸時代初期の再建。「清水の舞台から飛びおりる」の諺(ことわざ)はまさにここ!
実は、御本尊の観音様に御利益をいただいたお礼に能や踊りを楽しんでもらうため、舞楽などを奉納する正真正銘の「舞台」なのだ。両袖の翼廊は楽舎である。
清水寺は観音信仰のメッカであり、清水観音への奉納舞は、当代一流の演者が選出された。人生の晴れ舞台を「檜舞台を踏む 」というが、この檜舞台とは まさにこの檜の板間の舞台なのだ。
また舞台からは、正面に子安の塔、西方に京都タワーもはじめ、京都市街が展望できる。ここも記念撮影に人気のビュースポットだ。
本堂内は巨大な丸柱の列によって外陣(礼堂)と内陣・内々陣に三分され、最奥の内々陣の大須弥壇上の三基の厨子(国宝)内に本尊千手観音と脇侍(わきじ)の地蔵菩薩・毘沙門天を祀る。
御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩
本堂内々陣の厨子内に安置され、33年に一度の御開帳の秘仏のため、変わって人々の願いを受けるお前立ちが据えられている。千手観音の手はあまねく人を救う手。
普通一般の十一面(顔)四十二臂(ひ・手)千手観音は左右それぞれの手に小さな如来を持つが、ここのは、最上の左右二臂を頭上高く挙げて如来を戴く独特の「清水型」千手観音である。
二十八部衆と風神、雷神
千手観音の眷族(けんぞく・従者)で、本堂内々陣の本尊の厨子の左右に分かれて立ち並び、本尊と観音信者(千手観音を信じる善なる者)を、それぞれが500の部下を持って護衛すると伝わる。金網越しに見ることができる。
向って右端の毘沙門天の厨子の外側に風神が、左端の地蔵菩薩の厨子の外側に雷神が守護する。みな木造・漆箔・彩色像である。三十三間堂の千手千眼観音、眷属たちと比べてみよう!


仏足石
轟門をくぐり、回廊をぬけた左手にお釈迦様の足形と霊妙な十一種の文様が彫刻された石があります。足腰の弱い人がこの石を撫で、その手で自分の足腰をさするとよくなるといわれています。
堂々めぐり筋痕
仏足石の向かい、裳層(もこし)の窓下長押に深い筋状の痕がみられます。これは昔、お百度やお千度の堂々めぐりをした数取り札の擦り痕で、本堂軒廻りの長押にズーッと刻まれています。


京都盆地が湖であった時代から不老長寿の霊山「蓬莱の島」として信仰をあつめていたと伝わるほど、古代からここにあるのが地主神社。東隣下の崖には今も「船着き場」の跡が残る。
因幡の白兎を助けたとして知られる縁むすびの神さま大国主命を主祭神として五柱を奉り、さまざまな願いを叶えてくれると大人気のスポットだ。
近年、アメリカの原子物理学者・ボースト博士の研究により、 本殿前の「恋占いの石」は縄文時代の遺物であることが証明された。
また一樹に一重と八重を持つ地主桜は、平安期、嵯峨天皇が行幸したとき、あまりの美しさに三度車を返したといわれ、それより「御車返しの桜」と呼ばれている。
「恋占いの石」は、相手を思いながら、片方の石から片方の石に目をつぶってたどりつくと思いが叶うというもの。人の手を借りると、その恋にも手助けがいるという。





なで大黒 撫でる箇所によって、良縁・受験必勝・安産・商売繁盛・勝運・交通安全とそれぞれのご利益があるのだとか。
おかげ明神は、どんな願い事でも、ひとつだけなら必ず「おかげ」(ご利益)があるという、一願成就の守り神さま。特に女性の守り神として厚い信仰を集めている。
また、後方のご神木は「いのり杉」とも呼ばれ、昔には丑の刻まいり(うしのときまいり)のわら人形が打ち付けられていた。現在でもその釘跡が無数に残る。
水かけ地蔵は、長い年月、地主神社の地中で修業をされた、徳の高いお地蔵さま。水をかけて祈願するとご利益がある。
狩野元信筆「天井龍」(重要文化財)は、夜ごと天井を抜け出し、音羽の滝の水を飲むので、竜の目に釘を打ちつけたという伝説で知られている。この竜は、いずれの方角から眺めても自分の方をにらんでいるように見えるところから、「八方にらみの竜」とも呼ばれている。

ぬれて観音
奥之院の東裏、石の玉垣にかこまれた小池中にに祀られる小型の可愛らしい石造観音 。北隣の蓮華水盤で柄杓に水をくみ、肩からかけると、おのれの塵汚すなわち煩悩や罪が洗い流されるという。 見る人によって表情が色々に変化するとか。
水をかけているときに観音が笑っていたら幸せになれるとの言い伝えもある 。台座には「観世水」とある。


奥の院
江戸時代初期、重要文化財。元祖・行叡居士と開山・延鎮上人練行の旧草庵跡と伝えられている。
本堂同様に舞台造りになり、本尊千手観音と脇侍地蔵菩薩・毘沙門天、二十八部衆、風神・雷神を祀る。蟇股(かえるまた)、長押(なげし)など、随所に桃山様式の極彩色文様の跡を残す。
清水寺開創を起縁する音羽の滝の真上に建ち、昔の真言宗兼学兼宗を伝統して、弘法大師像も奉祀している。
絵葉書やメディアなどで紹介される清水本堂の定番画像は、この奥の院から撮影したものである。
毎年12月に日本漢字能力検定協会(ちょっと別の話題にもなりましたが……)が主催する「今年の漢字」が発表され、清水寺の貫主(09年は森清範さん)の揮毫(きもう・筆をふるう)がされるのもこの奥之院だ。 2010は「暑」でしたね。

音羽の滝
こんこんと流れる出る清水 、清水寺の寺名はまさにここに由来する。古来「黄金水」「延命水」とよばれ「清め」の水として尊ばれてきた。開祖行叡居士、開山延鎮上人の滝行を伝統して水垢離(みずごり)の行場となり、古くは弁慶や義経も飲んだと伝承される。またお茶の水汲み場となってきた。界隈に住む人は実際にお茶の水に使用しているのだ。
今日、日本十大名水の筆頭にあげられ、参詣者が列をつくって柄杓に清水を汲み、六根(眼・耳・鼻・舌・身・意) 清浄(洗い清める)、所願成就を祈る。
ちなみに、 この三つの筋から流れる音羽の滝だが、よく観光用にそれぞれに御利益があり、三つすべて飲むとその効き目が無くなるとか、健康・学業・縁結びと言われるが 根拠はない。
「どちらにしても水源は一つなので同じ水なんですよ!」


音羽の滝を横目に進むと、舞台が下から見上げれ、舞台造の構造が伺える。
錦雲渓の急崖に約190平方メートル、総桧板張りの「舞台」を懸造りにして張り出し、最高12メートル強の巨大な欅の柱を立て並べて支えている。
日本は山だらけ、しかし面の平地化ほど危険なものはない。清水寺のような急斜面では、城郭の石垣でもつくる気にならないと、地面の安定は保てなかった。
このような場合、日本の建物で使われたのが、清水寺に代表される束石の上に柱を立て、束柱相互を貫で縫うつくりかたである。床下が弾力性のあるラーメン状の架構となり、きわめて強固になるのだ。
これが「懸造(かけづくり)」と呼ばれる工法である。清水寺の場合、すでに350年以上経過しているが、今なお健在だ。もっとも、束柱の点検・修理は年中行われ、舞台床も頻繁に替えられている。

アテルイ、モレの碑
アテルイ、モレは、平安時代朝廷の東北征服戦争に対して頑強に抵抗した「蝦夷(えみし)」の首長と副将である。征夷大将軍の坂ノ上田村麻呂の軍に帰順、将軍が両雄の武勇と器量を惜しみ、朝廷に助命嘆願したが、許容されず両雄は河内の国で処刑されたと伝承される。
平安建都1200年を期し、鎮魂・顕彰の碑が建立された。

北総門(きたそうもん)江戸時代初期、重要文化財。
元来は塔頭(たっちゅう)(旧本坊)成就院の正門であった。寛永8~16年(1631~39)間に再建された一間(間口4.12メートル)潜りつきの 薬医門である。
屋根は切妻造り、本瓦葺きで、鉄製の飾り金具や鉄帯を取り付けた大きな扉を二枚釣りこんでいる。
東隣に弁天堂が建ち、北裏側に月照・信海兄弟上人の歌碑と西郷隆盛の詩碑が並ぶ。


大河ドラマ「篤姫」では西郷隆盛が清水寺成就院の勤皇派の月照上人と幕府の手を逃れて薩摩に逃げます。
二人は薩摩藩に逃れたのですが、藩の庇護を受けられませんでした。西郷は薩摩藩で月照をかばいきれぬと悟り、舟で海へ逃れ、錦江湾へ二人して入水します。ところが西郷隆盛は助かりますが、月照上人は亡くなってしまいます。
この月照上人が西郷隆盛と薩摩に逃れるとき 後のことを清水寺の寺男近藤正慎に託したそうです。正慎は安政の大獄で捉えられ、両人の居所を尋問されました。京都西町奉行所に捕われ厳しい拷問を受けましたが答えず、獄舎の壁に頭を打ちつけ、舌をかみ切って壮絶な獄死。その正慎の妻子に清水寺では永代門前での営業を許したのです。それが「舌切茶屋」です。
ちなみに正慎は、大河ドラマ「竜馬伝」で山内容堂役でもあった俳優の近藤正臣さんの曾祖父です。近藤正慎の孫、近藤悠三は人間国宝の陶芸家で茶わん坂には記念館があります。
また月照上人の下僕だった大槻重助と言う人が 月照上人の供をして薩摩へいき、西郷と月照を救助しましたが、西郷は蘇生したのに、月照は助からず、重助は捕らえられ、遺品を携えて帰京しました。半年獄舎につながれましたが放免となりました。
清水寺では、その忠僕ぶりに感銘し、永代にわたり茶店を営むことを許したのです。重助は「忠僕茶屋」を営みながら、月照上人の墓守をしてきました。
清水坂と高台寺を結ぶ道が産寧坂、二寧坂だ。いわれは諸説あるが、土産物店、陶磁器店、料亭などの観光に欠かせない楽しみがぎっしりと詰まる。 時間があれば、ゆっくり散策したいもの。おみやげなどはほとんど何でも揃う。
その翌々年、蝦夷征伐で知られる坂上田村麻呂が、高子妻室の安産のためにと鹿を求めて上山し、清水の源をたずねたところ、 延鎮上人に出会い、殺生の非を諭され、鹿を弔うて下山した。妻室に延鎮の説く清滝の霊験、 観世音菩薩の功徳を語り、共に深く観世音に帰依して仏殿を寄進し、ご本尊に十一面千手観音を安置したといわれれている。
「清水寺」の寺名は音羽の滝の清泉にちなみ、以後、古くからの観音霊場として人々の崇敬を集めてきた。もとは興福寺の玄肪が請来した北伝の法相宗に属したが、現在は独立して北法相宗大本山を名乗る。
http://www.monzenkai.com/monzen_map.htm 清水寺門前会マップ
五条坂を上がると左手に大型駐車場(600円)、満車だったら突き当りの右側にタクシー専用駐車場がある。さらに満車の場合は、1時間500円となるが、高台寺の霊山観音の駐車場がある。
駐車場を降りて突き当たりの角が七味家本舗。創業350年、七味唐がらし創案の店だ。お振る舞いの「からし湯」は、白湯に唐辛子の粉をふりかけたもの。清水寺への参拝客や音羽の滝で修行する行者さんに「身体がぬくもるように」と、無償でだしていたものという。
栄山堂は、豆乳ドーナッツと豆乳ソフトが人気。お菓子をはじめ、京都限定キャラクターグッズなども多く、若い世代に人気がある。
清水焼窯元である森陶器店では「陶芸教室」が開設されている。店舗内では、自家の窯で焼き上げた清水焼作品をはじめ、京人形や京みやげが購入できる。
創作陶芸教室 (1名~300名)所要時間約90分 下絵付け教室(1名~600名)所要時間約40分 075-561-3457
錦古堂は、古都京都の伝統を受け継いだ京扇子専門舗。女性たちに人気のお店。
西尾八ッ橋は、京都で一番古い八ッ橋のお店。お茶のサービスがあるほか、店内では三十数種の八ッ橋が試食しほうだい。最近ではソーダやマンゴ、ショコラといったものまであり、種類は豊富だ。八ッ橋は老舗の聖護院八ッ橋、大手の井筒八ッ橋・夕子、おたべ他いくつもの店が乱立している。

参道を登りきると、眼前に石段が広がり、仁王門や西門が現れる。左側に地蔵院善光寺堂があり、脇にはちょこんとまあるいお地蔵さん・首振り地蔵が座している。(2代目、初代は堂の中にある)
善光寺堂縁先に祀られているこのお地蔵さんは首が離れているため自由に動かせる(360度回転できる)ようになっている。自分が恋い想う人が住む方向に首を振り向け、祈願すると思いが叶うとされている。「回らない人は、体が悪いか、借金で首が回らないのだとか?」

仁王門(重要文化財)
室町後期再建。両脇間に阿形・吽形の金剛力士像を安置する三間一戸、入母屋造り、檜皮葺、室町様式の堂々たる楼門(ろうもん)で、昔の丹塗りを淡美に残し「赤門」とよばれている。
阿吽(あうん)は仏教の呪文(真言)の1つ。梵字において、阿は口を開いて最初に出す音、吽は口を閉じて出す最後の音であり、それぞれ人間の生まれた瞬間と死ぬ瞬間の姿、宇宙の始まりと終わりを表すとされた。
狛犬は通常神社にあるが、清水寺の奥に地主神社があるため、門前に狛犬が一対置かれている。 また狛犬は阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の一対の姿なのだが、 ここのはなぜか両方とも口をあんぐりと開けている。「なんで?」(七不思議の一)
「坂を上りきって疲れた参拝者を励ますため、二匹とも爆笑してるのかなあ?」

西門(重要文化財)
江戸初期の再建。両脇間に持国天・増長天を祀り、優美な三間一戸の八脚門で、丹塗りと極彩色文様が復元されて華麗な桃山様式の美を見せる。 切妻造り、檜皮葺の西門。

随求堂(ずいぐどう)
江戸中期再興。塔頭・慈心院の本堂で、衆生の願い・求めにすぐに随って、すべて叶えてくれるという大功徳をもつ随求菩薩(秘仏)が祀られ、毘沙門天と吉祥天を脇侍にする。
堂下は随求菩薩の胎内に見たてた真っ暗な空間を大数珠をたよりにお詣りする「胎内めぐり」。自分自身の存在を問い直し、新生するのだとか。入場するのに百円必要だが、おもしろくもあるので、ぜひ体験してもらおう。

三重塔
一重内部に大日如来を祀り、天井や柱などが密教仏画や飛天・龍と各種文様らの極彩色で荘厳された高さ31㍍弱の日本最大級の三重の塔。四周の壁に真言八祖像が描かれている。
「大日如来」は真言密教の根本となる仏。宇宙の中心に位置し、その大いなる光ですべてのものを照らすという。塔は宇宙観を表しているのだ。
「真言八祖像」とは、真言密教の開祖龍猛から龍智・善無畏・一行・金剛智・不空・恵果と我が国に真言密教を伝えた空海までの八祖を八幅(8枚)一組の画像としたもの。東寺の五重塔などにも描かれている。明治維新までは、清水寺は法相宗に真言宗を兼ねていた。その名残がこの三重塔や大日堂に残されている。


轟門、梟(ふくろう)の手水鉢
経堂、坂上田村麻呂夫妻、開祖行叡居士、開山延鎮上人が祀られている田村堂を横目に、拝観券を買って、轟門をくぐる。
本堂への中門である轟門は江戸時代初期のもので、重要文化財。「普門閣」の扁額は月舟禅師の名筆。三間一戸の八脚門、切妻造り、本瓦葺きで、妻や天井の構造は東大寺転害門を縮小して写している。本殿、奥の院など境内を龍に見立て「龍の口」ともされている。左右両脇間に持国天像と広目天像を祀り、背面には阿・吽形の狛犬を安置する。
なお、轟門横の龍が水を出している清め水の梟の手水鉢。「なぜ龍なのに、梟(ふくろう)?」「さがしてごらん」
実は、手水鉢を支える石の四隅が梟の彫像がついた台座になっているから。じゃあ、フクロウと言えば知恵の神様なので、こんな下座に置くのはなんで?これも京都七不思議の一つだ。ちなみに、この水を含んで祈ると歯痛にご利益があると伝わる。

本堂前に鉄製の草履や杖があり、大きい杖は約90Kgあるとか!数人で持ち上げようとしてもなかなか持ち上がらない。
本堂・舞台(国宝)
清水寺本尊十一面千手観音(秘仏)を祀る正面十一間(約36㍍)、側面九間(約30㍍)、高さ18㍍の仏殿で、優美な起り反り曲線を見せる寄棟造り・檜皮葺の屋根や軒下に吊る蔀戸など、平安時代の宮殿、貴族の邸宅の面影を伝える。
江戸時代初期の再建。「清水の舞台から飛びおりる」の諺(ことわざ)はまさにここ!
実は、御本尊の観音様に御利益をいただいたお礼に能や踊りを楽しんでもらうため、舞楽などを奉納する正真正銘の「舞台」なのだ。両袖の翼廊は楽舎である。
清水寺は観音信仰のメッカであり、清水観音への奉納舞は、当代一流の演者が選出された。人生の晴れ舞台を「檜舞台を踏む 」というが、この檜舞台とは まさにこの檜の板間の舞台なのだ。
また舞台からは、正面に子安の塔、西方に京都タワーもはじめ、京都市街が展望できる。ここも記念撮影に人気のビュースポットだ。
本堂内は巨大な丸柱の列によって外陣(礼堂)と内陣・内々陣に三分され、最奥の内々陣の大須弥壇上の三基の厨子(国宝)内に本尊千手観音と脇侍(わきじ)の地蔵菩薩・毘沙門天を祀る。
御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩
本堂内々陣の厨子内に安置され、33年に一度の御開帳の秘仏のため、変わって人々の願いを受けるお前立ちが据えられている。千手観音の手はあまねく人を救う手。
普通一般の十一面(顔)四十二臂(ひ・手)千手観音は左右それぞれの手に小さな如来を持つが、ここのは、最上の左右二臂を頭上高く挙げて如来を戴く独特の「清水型」千手観音である。
二十八部衆と風神、雷神
千手観音の眷族(けんぞく・従者)で、本堂内々陣の本尊の厨子の左右に分かれて立ち並び、本尊と観音信者(千手観音を信じる善なる者)を、それぞれが500の部下を持って護衛すると伝わる。金網越しに見ることができる。
向って右端の毘沙門天の厨子の外側に風神が、左端の地蔵菩薩の厨子の外側に雷神が守護する。みな木造・漆箔・彩色像である。三十三間堂の千手千眼観音、眷属たちと比べてみよう!


仏足石
轟門をくぐり、回廊をぬけた左手にお釈迦様の足形と霊妙な十一種の文様が彫刻された石があります。足腰の弱い人がこの石を撫で、その手で自分の足腰をさするとよくなるといわれています。
堂々めぐり筋痕
仏足石の向かい、裳層(もこし)の窓下長押に深い筋状の痕がみられます。これは昔、お百度やお千度の堂々めぐりをした数取り札の擦り痕で、本堂軒廻りの長押にズーッと刻まれています。

京都盆地が湖であった時代から不老長寿の霊山「蓬莱の島」として信仰をあつめていたと伝わるほど、古代からここにあるのが地主神社。東隣下の崖には今も「船着き場」の跡が残る。
因幡の白兎を助けたとして知られる縁むすびの神さま大国主命を主祭神として五柱を奉り、さまざまな願いを叶えてくれると大人気のスポットだ。
近年、アメリカの原子物理学者・ボースト博士の研究により、 本殿前の「恋占いの石」は縄文時代の遺物であることが証明された。
また一樹に一重と八重を持つ地主桜は、平安期、嵯峨天皇が行幸したとき、あまりの美しさに三度車を返したといわれ、それより「御車返しの桜」と呼ばれている。
「恋占いの石」は、相手を思いながら、片方の石から片方の石に目をつぶってたどりつくと思いが叶うというもの。人の手を借りると、その恋にも手助けがいるという。





なで大黒 撫でる箇所によって、良縁・受験必勝・安産・商売繁盛・勝運・交通安全とそれぞれのご利益があるのだとか。
おかげ明神は、どんな願い事でも、ひとつだけなら必ず「おかげ」(ご利益)があるという、一願成就の守り神さま。特に女性の守り神として厚い信仰を集めている。
また、後方のご神木は「いのり杉」とも呼ばれ、昔には丑の刻まいり(うしのときまいり)のわら人形が打ち付けられていた。現在でもその釘跡が無数に残る。
水かけ地蔵は、長い年月、地主神社の地中で修業をされた、徳の高いお地蔵さま。水をかけて祈願するとご利益がある。
狩野元信筆「天井龍」(重要文化財)は、夜ごと天井を抜け出し、音羽の滝の水を飲むので、竜の目に釘を打ちつけたという伝説で知られている。この竜は、いずれの方角から眺めても自分の方をにらんでいるように見えるところから、「八方にらみの竜」とも呼ばれている。

ぬれて観音
奥之院の東裏、石の玉垣にかこまれた小池中にに祀られる小型の可愛らしい石造観音 。北隣の蓮華水盤で柄杓に水をくみ、肩からかけると、おのれの塵汚すなわち煩悩や罪が洗い流されるという。 見る人によって表情が色々に変化するとか。
水をかけているときに観音が笑っていたら幸せになれるとの言い伝えもある 。台座には「観世水」とある。


奥の院
江戸時代初期、重要文化財。元祖・行叡居士と開山・延鎮上人練行の旧草庵跡と伝えられている。
本堂同様に舞台造りになり、本尊千手観音と脇侍地蔵菩薩・毘沙門天、二十八部衆、風神・雷神を祀る。蟇股(かえるまた)、長押(なげし)など、随所に桃山様式の極彩色文様の跡を残す。
清水寺開創を起縁する音羽の滝の真上に建ち、昔の真言宗兼学兼宗を伝統して、弘法大師像も奉祀している。
絵葉書やメディアなどで紹介される清水本堂の定番画像は、この奥の院から撮影したものである。
毎年12月に日本漢字能力検定協会(ちょっと別の話題にもなりましたが……)が主催する「今年の漢字」が発表され、清水寺の貫主(09年は森清範さん)の揮毫(きもう・筆をふるう)がされるのもこの奥之院だ。 2010は「暑」でしたね。

音羽の滝
こんこんと流れる出る清水 、清水寺の寺名はまさにここに由来する。古来「黄金水」「延命水」とよばれ「清め」の水として尊ばれてきた。開祖行叡居士、開山延鎮上人の滝行を伝統して水垢離(みずごり)の行場となり、古くは弁慶や義経も飲んだと伝承される。またお茶の水汲み場となってきた。界隈に住む人は実際にお茶の水に使用しているのだ。
今日、日本十大名水の筆頭にあげられ、参詣者が列をつくって柄杓に清水を汲み、六根(眼・耳・鼻・舌・身・意) 清浄(洗い清める)、所願成就を祈る。
ちなみに、 この三つの筋から流れる音羽の滝だが、よく観光用にそれぞれに御利益があり、三つすべて飲むとその効き目が無くなるとか、健康・学業・縁結びと言われるが 根拠はない。
「どちらにしても水源は一つなので同じ水なんですよ!」


音羽の滝を横目に進むと、舞台が下から見上げれ、舞台造の構造が伺える。
錦雲渓の急崖に約190平方メートル、総桧板張りの「舞台」を懸造りにして張り出し、最高12メートル強の巨大な欅の柱を立て並べて支えている。
日本は山だらけ、しかし面の平地化ほど危険なものはない。清水寺のような急斜面では、城郭の石垣でもつくる気にならないと、地面の安定は保てなかった。
このような場合、日本の建物で使われたのが、清水寺に代表される束石の上に柱を立て、束柱相互を貫で縫うつくりかたである。床下が弾力性のあるラーメン状の架構となり、きわめて強固になるのだ。
これが「懸造(かけづくり)」と呼ばれる工法である。清水寺の場合、すでに350年以上経過しているが、今なお健在だ。もっとも、束柱の点検・修理は年中行われ、舞台床も頻繁に替えられている。

アテルイ、モレの碑
アテルイ、モレは、平安時代朝廷の東北征服戦争に対して頑強に抵抗した「蝦夷(えみし)」の首長と副将である。征夷大将軍の坂ノ上田村麻呂の軍に帰順、将軍が両雄の武勇と器量を惜しみ、朝廷に助命嘆願したが、許容されず両雄は河内の国で処刑されたと伝承される。
平安建都1200年を期し、鎮魂・顕彰の碑が建立された。
北総門(きたそうもん)江戸時代初期、重要文化財。
元来は塔頭(たっちゅう)(旧本坊)成就院の正門であった。寛永8~16年(1631~39)間に再建された一間(間口4.12メートル)潜りつきの 薬医門である。
屋根は切妻造り、本瓦葺きで、鉄製の飾り金具や鉄帯を取り付けた大きな扉を二枚釣りこんでいる。
東隣に弁天堂が建ち、北裏側に月照・信海兄弟上人の歌碑と西郷隆盛の詩碑が並ぶ。


大河ドラマ「篤姫」では西郷隆盛が清水寺成就院の勤皇派の月照上人と幕府の手を逃れて薩摩に逃げます。
二人は薩摩藩に逃れたのですが、藩の庇護を受けられませんでした。西郷は薩摩藩で月照をかばいきれぬと悟り、舟で海へ逃れ、錦江湾へ二人して入水します。ところが西郷隆盛は助かりますが、月照上人は亡くなってしまいます。
この月照上人が西郷隆盛と薩摩に逃れるとき 後のことを清水寺の寺男近藤正慎に託したそうです。正慎は安政の大獄で捉えられ、両人の居所を尋問されました。京都西町奉行所に捕われ厳しい拷問を受けましたが答えず、獄舎の壁に頭を打ちつけ、舌をかみ切って壮絶な獄死。その正慎の妻子に清水寺では永代門前での営業を許したのです。それが「舌切茶屋」です。
ちなみに正慎は、大河ドラマ「竜馬伝」で山内容堂役でもあった俳優の近藤正臣さんの曾祖父です。近藤正慎の孫、近藤悠三は人間国宝の陶芸家で茶わん坂には記念館があります。
また月照上人の下僕だった大槻重助と言う人が 月照上人の供をして薩摩へいき、西郷と月照を救助しましたが、西郷は蘇生したのに、月照は助からず、重助は捕らえられ、遺品を携えて帰京しました。半年獄舎につながれましたが放免となりました。
清水寺では、その忠僕ぶりに感銘し、永代にわたり茶店を営むことを許したのです。重助は「忠僕茶屋」を営みながら、月照上人の墓守をしてきました。
清水坂と高台寺を結ぶ道が産寧坂、二寧坂だ。いわれは諸説あるが、土産物店、陶磁器店、料亭などの観光に欠かせない楽しみがぎっしりと詰まる。 時間があれば、ゆっくり散策したいもの。おみやげなどはほとんど何でも揃う。
2011年01月22日
観光ドライバーのための京都案内マニュアル・金閣寺
左大文字
西大路通りを南から上がってくると、左前方に左大文字が見える。金閣寺には左大文字、銀閣寺には大文字がある。五山の送り火の話なども話題のひとつ。
西に衣笠山、背後に左大文字山をひかえた景勝の地で、京都市の北部に連なるなだらかな山なみは、北山(ほくざん)の名で一般に親しまれている。衣笠山はかつて「宇多天皇が真夏に雪が見たいといいだして、山に大きな白絹をかぶせた」との伝承が残り、きぬかけ山とも呼ばれる。これも話題のひとつ。
黒門では北山(ほくざん)殿 鹿苑寺の説明をしよう。「これはなんと読みますか?」
金閣寺の正式名称は、鹿苑寺「ろくおんじ」という。金閣寺は室町幕府三代将軍・足利義満の北山殿という別荘(北山文化の中心となった)を後に寺院としたもの。義満の諡号(しごう・死後に贈られた名前、戒名)が鹿苑院といったことに由来する。
また、金閣寺は銀閣寺とともに京都五山の一、臨済宗の禅寺・相国寺の塔頭(たっちゅう)である。塔頭とは会社でいえば本社にあたる本山に属する支店みたいなもの。通常は院、庵、軒などで呼ばれることが多い。
もみじのトンネルを通り参道を進む。西園寺家に由来し、鎌倉期に作られたと伝えられる鐘楼を左に眺め、世界文化遺産の記念碑と金色の案内板を横目に拝観券売り場へ。すでに右上方に金閣寺の天辺、鳳凰が垣間見える。 右手には唐門と方丈がある。時々特別公開している。
左手の巨木は樹齢700年と言われる櫟樫(イチイガシ)だ。京都府指定の天然記念物に指定されている。櫟(いちい)は一位に通じて、立身出世を願い、公卿たちはこの木で笏(しゃく)を造って常に携えていたという縁起のよい木である

金閣寺の拝観券は金閣舎利殿と書かれたお札になっている。「ご飯粒のことを銀シャリといったりしますね。これは舎利に似ているところからきています」
舎利とは釈迦の遺骨のこと。仏舎利とも言い、釈迦(ゴータマシダルダ)入滅の折に何千にも砕かれ、弟子たちによって世界中にもたらされた。金閣寺はその仏舎利を供養する舎利殿である。
お札は旧家の木造建築では、魔よけに柱などに貼っているのを見かけるが、近代住宅では見かけなくなりましたね。

いよいよ、衣笠山を借景にした金箔の三層楼閣の舎利殿である金閣とその庭園が眼前に広がってくる。入ってすぐは通路で込み合うので、すぐにも西に移動しよう。
金閣の建築様式が、伝統的な貴族の寝殿造風と武家が帰依した禅宗寺院の禅宗様を折衷したもので、室町時代における貴族と武士の折衷文化が北山文化だといわれる。
晴天であれば、鏡湖池(きょうこち)に金閣がきれいに投影される。鏡湖池はその名の通り、金閣を映すためにつくられている。金閣内にいながらにして、楼閣から金閣を眺めることができるように造られた。
本物と池面に映った二つの金閣を背景に記念撮影をしよう。「二十四割る十二は?」「にっ」といった具合にね。

この池には、蓬莱山をイメージして、葦原島(あしわらじま)といわれる中島や鶴島、亀島が造られ、幾つもの岩島があり,これらの岩には畠山石、細川石と創建時に奉納した諸大名の名が付けられている。 中国・明から運ばせた庭湖石で名石中の名石のため、豊臣秀吉の聚楽第建設の時の名石狩りからも逃れたといわれる九山八海石の名石が配される。
この配置は西方極楽浄土の様子を表わした「浄土曼荼羅」に描かれた七宝池を模している。義満は蓬莱神仙思想に基づき、自らが船出する西方浄土を築いたのだ。
ちなみに、浄土(清らかな国土)とは、それぞれの仏が住している聖域、理想的な国土のことである。蓬莱山とはその極楽浄土にある不老不死の仙人たちが住む処であり、理想郷なのだ。

金閣の天辺に据えられた鳳凰(ほうおう)は、西方浄土に住むとされる中国の伝説上の霊鳥で、羽ある生物の王であり、不老不死、再生の象徴とされている。 陰陽道では朱雀(すざく)と同一とされる。 手塚治虫さんの漫画「火の鳥」そのものだ。

順路に沿って、陸舟(おかぶね)の松へ……。
方丈庭園には、義満が盆栽にしていたという松がある。船の帆と先端を表している。極楽浄土の金閣と鏡湖池に向くこの船は、まさに義満が西方浄土へ旅立つ船であったのだ。
天竜船の交易で明文化に造詣の深かった義満が、船尾を反らせている中国のジャンクを模倣したといわれる。船尾には舵を模った枝を垂らし、深く沈ませ入船(目的を達した)を現している。
ちなみに、鹿苑寺の陸舟の松は、善峰寺の游竜の松・大原宝泉院の五葉の松(近江富士)とともに、京都三松と呼ばれている。若い世代には「アニメのワンピースに出てくる海賊船みたいでしょ」と話してあげてもいいかも。

金閣寺に参詣するには、明治初期までは、金一両を払って講の一員になる必要があった。その頃までは、渡り廊下があり、金閣(舎利殿)に渡り廊下より登る事ができた。
金閣の側面に回りこむと、よりまじかに建築様式がうかがえる。
鹿苑寺は、応仁の乱の西軍の陣所となったため諸堂を焼失。唯一「金閣」だけが北山文化の遺構であったが、惜しくも昭和25年の夏、学僧の放火によって炎上した。
この有様は、三島由紀夫の小説「金閣寺」・水上勉の「金閣炎上」によって描かれている。
昭和30年復元・再建したが、金箔が剥離したため、昭和62年、5倍箔の金箔で漆箔修理完了。10.8㎝四方の金箔が20万枚使われたという。
「だからこんなに金ぴかなんだ」「当時の建築でないのは残念だが、再建されたことによって美しい姿を見れるというメリットもありますよ」
ちなみに、箔合金1グラムで約3300平方センチの金箔になる。仮に1ミリの幅で延ばし続けたとすると、330メートル、0.1ミリの糸状に延ばしたとするとなんと3.3キロメートルにも延びるのです!
ちなみに京都五閣とは、金閣、銀閣、西本願寺の飛雲閣、大徳寺塔頭芳春院の呑湖(どんこ)閣、東福寺の伝衣(でんね)閣である。
現在、殿内に入れないので、内部の写真が掲示されている。
初層 法水院といい藤原時代の寝殿造風 、阿弥陀仏堂として造られた。(法水→仏法が衆生の煩悩を洗い浄(きよ)めることを水に擬して云う)
二層 潮音洞といい鎌倉時代の武家造り仏間風。観音堂(岩屋観音を四天王が護持・天井には飛天が描かれています)。
三層 究竟頂(くっきょうちょう)と呼び禅宗様仏殿風 。唐様の仏間(桟唐戸・花頭窓)。ここに仏舎利(釈尊の遺骨)が安置されている。
初層の寝殿造の上に二層 の武家造がきている。貴族より武家が上ということだろうか、当時の力関係を表していておもしろい。

さて、順路に沿って散策しながら金閣をぐるりとまわっていく。こういった庭園を池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)という。江戸時代から流行した。金閣寺の現在の景観は江戸時代における住職・鳳林章承の修復、復興整備によるものである。
西側には船着場と池に突き出した漱清(そうせい・釣殿)が伺える。貴族や武家の統領たちは舟を浮かべて、四季折々の風景を楽しむ。曲水の宴などの雅を楽しんだ。
ぐるりとまわるとお守りの販売所がある。但し、出口付近の朱印所でも買えるので、混雑しているときは後にまわそう。
左手に、義満がお茶に使った銀河水、手洗いの厳下水、金閣寺垣を見ながら、鯉魚石、龍門の滝に至る。金閣寺垣は垣根の上部に半割りの竹(玉縁)を掛けているのが特徴で、造形的に格調が高いとされている。
鯉魚石(りぎょうせき)は、鯉が滝を登ると龍になるといわれる中国黄河の故事「登竜門」にちなんだもの。
若い世代であれば「ポケットモンスターのコイキングは進化すると何になる?」と聞いてやれば良い。ほとんどが「ギャラドス(龍の化身)」と合唱するはずだ。
さらに丘を登ると衣笠山を背景にした「安眠沢(あんみんたく)」と呼ばれる池となる。奥に白蛇塚と呼ばれる五輪の石塔がある。実は、鏡湖池や北の一段高い山腹に静かに水を湛える池の安民澤、そこから落ちる滝「龍門瀑」などは、発掘調査から、鎌倉時代の北山第の遺構とみられている。
元来このあたりは、藤原北家一門で、摂関家に次ぐ精華家の西園寺家の別荘・北山第だった。かつては歴代の上皇・天皇が何度も行幸し盛大な宴遊が催されたという。
動乱の南北朝時代、西園寺家が衰退し荒廃の一途を辿っていた北山第を河内国の領地と交換する形で譲り受けたのが室町幕府だった。時の権力者、足利義満が譲渡させたものと言っていいだろう。このあたりも当時の公家と武家の力関係を表していておもしろい。
また、鏡湖池の貯水池となっているが、安民沢の周りは樹林に囲まれ、旱(ひでり)が続いても涸れないため、雨乞いの場となっていたと言われる。
弁財天(印度の女神)と・白蛇(宇賀神・うがしん・日本の衣食の神)が合体した。白蛇は弁財天をも現している。
西園寺時代には妙音弁財天(空海直筆画像・現在出町柳にあり)と木像(御苑にあり)を金閣辺に在った妙音堂に安置していた。
西園寺 家は琵琶(楽器)の総家でもあって、天皇から公家衆に妙音弁財天の前で秘曲を伝授していた。

安眠沢を少し登ると開けたところから、方丈の大きな屋根越しに金閣が見下ろせる高台に出る。このあたりが金閣の見納めだ。「見返り金閣」とも呼ばれている人気のビュースポットでもある。
金閣と対角線上に見上げると茶室・夕佳亭(せっかてい)がある。今は木々が生長してしまって、間を妨げてしまっているのだが、この夕佳亭から、夕日に映える金閣が見下ろせるように造られていたのだ。紅葉や雪のときなどは特にすばらしい光景となる。


夕佳亭の前に貴人橸(とう)という石の腰掛がある。昔、高貴な人が座られたということで、室町幕府が移設したものだそうだ。いったい誰? 「希望するお嬢さんは記念写真をどうぞ」
夕佳亭(せっかてい)は、江戸時代,後水尾天皇(ごみずのおてんのう)を迎えるために鹿苑寺住職の鳳林承章が茶人・金森宗和(かなもりそうわ)につくらせた数寄屋造の茶室で「夕」日にはえる金閣が「佳(よ)」いという意味から「夕佳亭」と名付けられた。明治のはじめに焼失し,現在の建物は明治27(1894)年に再建されたものだ。
茶室の南天の床柱や萩の違棚が有名で,亭の前にある石燈籠と富士形の手水鉢は,室町幕府八代将軍足利義政が愛用したものと伝えられている。茶室の降り口に南天の木が植えられているので参考にするといい。
ちなみに南天は難転(なんを逃れる)のごろあわせだと言われる。
不動堂は、安土桃山時代の大名で豊臣秀吉の重臣であった宇喜多秀家(うきたひでいえ)が再建したもので、金閣寺の境内に現存する最も古い建物である。本尊の石不動明王は弘法大使作と伝わり、首から上の病に効くと言われている。現在は秘仏だが,2月の節分と,大文字の送り火が行われる8月16日には開扉法要(かいひほうよう)が営まれている。

境内を出たら、「よーじや」にもよってみよう。もちろん哲学の道(かくれや的で割烹も併設)や清水の二年坂、麩屋町三条(よーじやカフェ)、祇園花見小路にもあるので工程の中で一ヶ所考えればいいだろう。
舞妓さんたちが愛用しているという「あぶらとり紙」は、金閣を初め、寺社仏閣で使われる金箔製造の副産物である。金地金を叩き広げる際、地金を挟むために用いられる箔打ち紙が、皮脂もよく吸収することから転用されるようになったのだ。
ちなみに「よーじや」さんのユニークなマークは手鏡をモチーフにしている。
2010年10月16日
洛南の聖地めぐりはいかが 海住山寺 岩船寺 浄瑠璃寺

浄瑠璃寺発行の絵葉書より
木津川は、古代から流通の拠点でした。
「みかの原 わきて流るる いずみ川 いつ見きとてか 恋しかるらむ」、泉川とは木津川の古い名です。百人一首に歌われたこの「みかのはら」を一望におさめる小高い山の中腹に海住山寺は創建されました。
恭仁京造営の六年前(天平7年・735年)、聖武天皇が奈良の大仏を建立しようとしていた頃、王城の鬼門に伽藍を建てれば、大願成就するとのお告げが起源といわれます。当時は藤尾山観音寺といいましたが、その後焼失、復興した解脱上人貞慶によって補陀洛山・海住山寺とされました。
真っ先に目に飛び込んでくる五重塔は鎌倉時代の建立。繊細な木組みを見せるやさしげな塔、もこしをつけた初重の内陣は厨子のようなめずらしい造りとなっています。 内部には、仏舎利を安置する塔と四方を守る四天王が安置されています。

老木が生い茂る山寺の雰囲気のこの寺、山中にあっても海住山寺と名ずけられたのは、大海にある観音浄土・補陀洛(ふだらく)に因んだもの。本堂の厨子は秘仏・十一面観音 ゆったりとしたおおらかなは、平安初期のものでめずらしい。
岩船寺
創立は天平元年(729)、聖武天皇の発願により、行基菩薩によって建立されました。その後、空海と智泉上人阿弥陀堂においてが伝法灌頂を修したといわれています。

本尊の阿弥陀如来坐像(重文)は平安時代なかばのもので、けやきの一木造。定印を結び、阿弥陀信仰が盛んになる以前の様式でめずらしい。鎌倉時代の四天王立像が脇侍を固めています。
池には、鎌倉時代の特徴である十三重の石塔があります。室町時代の建立の三重塔は、整った木組み、自然と調和し、紅葉とのコントラストが素敵です。垂木を支える、ユニークにも感じる天邪鬼(重文)が四隅を守ります。あまのじゃくの語源でもあります。

この地域は、850年前、平城京の大寺の僧たちが修行のために数多く訪れ創建された山寺が多い。山を隔てたらすぐ奈良の街に至るところです。
この当尾の丘陵は石仏の里、いたるところに石仏があります。平城の人々からは僧侶たちの修行の地。平安の都人からは聖地とされたところなのです。

浄瑠璃寺
傍らの馬酔木(あしび)より低いくらいの慎ましやかな山門(堀たつお)をくぐると見事な庭園が広がっています。
この寺は、東の薬師仏をまつる三重塔、中央宝池、西の九体阿弥陀堂から成ります。
浄瑠璃とは瑠璃のように澄み切った世界、この世の東にある浄土を言います。
清らかな浄土を表現した池の東に三重塔(国宝・藤原時代、塔自体は平安末期に京の一条大宮から移されてきました。初重には、本尊・薬師如来(秘仏)が安置されています。薬師如来は、東方浄土の教主で、過去の世界から現実の苦悩を救い、生きる力を授けてくれる仏。衆生(人々)を目標の西方浄土へ送り出してくれる遣送の如来です。
右手は、人の恐れを取り除く優しさに満ちた施無為の印を結び、左手には、生きる苦しみを救う薬の壷を持っておられます。

浄土の池である中央宝池の西側に池を挟んで、九体阿弥陀堂(国宝・藤原時代)のなだらかな屋根が伺えます。横長の純和風の建築は平安期のもので、現存する唯一のもの。
太陽の沈む西方浄土へ迎えてくれる阿弥陀仏を西へ向かって拝めるように東向きにし、浄土の池の対岸から彼岸に来迎仏を拝ませるようにしたもの。今でも、薬師の前から池越しに午後の太陽の軌道を見ていると、春分、秋分の日(お彼岸の中日)には中尊の後方に沈んでいくのが分かるといいます。
柱と柱の間にそれぞれ一体ずつ、まるで部屋に住んでいるかのように阿弥陀仏が安置され、前には一体に一つずつ板扉がつけられています。

阿弥陀仏は西方未来の理想郷である楽土へ迎えてくれる来迎仏です。その九体の阿弥陀如来(国宝・藤原時代)は、人間の努力や心がけなど、生前の行いによって九品往生、下品下生(げぼんげしょう)から始まり、上品上生(じょうぽんじょうしょう)まで、九つの往生を約束する仏たち。
平安時代 飢饉や天災に悩まされ、末法の世を恐れ慄いた人々が、九つのうち、どの段階で没しても、いずれかの阿弥陀仏に救われることを願い、九体仏を盛んに作ったといわれます。ほとんど残っていない中で、今では大変貴重なものです。
中尊は、高さ2メートル30cm余、丈六の阿弥陀と呼ばれる。人々を浄土に迎えようとする来迎印。衆生を極楽へ誘う優しさ表しています。
中尊の左右に半丈六の阿弥陀が四対づつ、浄土で瞑想する定印を結んでいます。一つ一つ表情が異なる。平安の人々がすがる様子が思い浮かぶようでもあります。
この寺の庭園は、過去(東方浄土・薬師如来)の世界から煩悩の河である現世(釈迦如来)を越えて、彼岸にある未来(阿弥陀如来)の世界までを表現。暗黒無物の末法の世に一筋の望みを仏に頼んだ切実な願いが込められているのです。
その他にも、秘仏(年一回の特別公開)吉祥天女像(重文・鎌倉時代)、大日如来像(秘仏・鎌倉時代)、四天王像(国宝・藤原時代)、不動明王三尊(重文・藤原時代)など見ごたえのある貴重な文化財が目白押しです。


